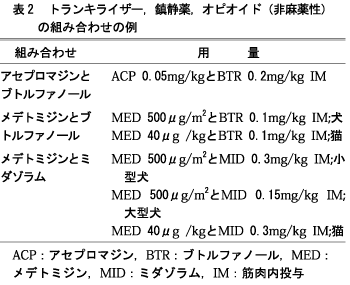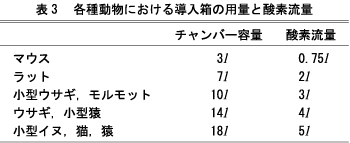II ケタミンを用いない鎮静,麻酔,鎮痛法
前述のようにケタミンは筋肉あるいは皮下投与が可能で,かつ通常量では重篤な呼吸・循環器抑制を引き起こさないため,臨床では幅広く用いられている.おそらくその使い勝手のよさから,その使用目的をあまりはっきりさせないで使われている場合も少なくないものと考えられる.しかし,ケタミンと同等の性質を持つ麻酔薬は存在しない.したがって,ケタミンを用いないで,鎮静,麻酔,鎮痛を行う場合には,必要な状態が鎮静なのか麻酔なのか,鎮痛なのかをよく見極め,それぞれ最適な薬剤を選択していく必要がある.
|
1 ケタミンを用いない鎮静法
取り扱いが難しい猫では(あるいは時に犬においても),しばしば化学保定を目的にケタミンが用いられる.このような場合に,ケタミンを用いないとすると,最も有用性が高いのは鎮静剤のメデトミジンである.また使用範囲が限られ,国内市販もないがトランキライザーであるアセプロマジンも利用できる.さらにこれらの薬剤にミダゾラム,あるいはブトルファノールを組み合わせるとより強力な作用が得られる.以下に利用できる薬剤の特徴と実際の使用について簡単に述べる.
1)トランキライザー
a)フェノチアジン(アセプロマジン,プロピオニルプロマジン):比較的強力な鎮静と筋弛緩作用を得られる.末梢血管拡張作用が強く,低血圧や低体温を生じやすい.てんかん発作の閾値を下げる可能性があることから,てんかん発作経歴のある犬猫への使用は控える.
b)ブチロフェノン(ドロペリドール):中等度の鎮静作用と筋弛緩作用を得られる.末梢血管拡張作用はあるが,フェノチアジンほど強くない.てんかん発作の閾値も下げない.
c)ベンゾジアゼピン(ジアゼパム,ミダゾラム,フルニトラゼパム):向精神薬として取り扱われ,軽度の鎮静作用と比較的強い筋弛緩作用を得られる.呼吸循環系の抑制作用が軽微なので,リスクの高い犬猫にも使用できる.フルマゼニルで拮抗できる.
2)鎮静薬:α2-作動薬(キシラジン,メデトミジン)
強い鎮静,鎮痛,筋弛緩作用があり,鎮静薬としては理想的な薬物である.しかしながら,徐脈や末梢血管収縮作用による血圧上昇など心血管系の変動が大きく(特に犬),また嘔吐,血糖値上昇なども伴うため,全身状態のよい老齢でない犬猫だけに使用すべきである.投与5〜10分後に心拍数が減少しない場合には,心拍出量の顕著な低下による低血圧が生じている可能性があるので,アチパメゾールによる拮抗を考慮する.抗コリン作動薬のアトロピンの併用は,特に犬では重度の高血圧を招くため禁忌となる.
3)トランキライザー,鎮静薬,オピオイド(非麻薬性)の組み合わせ
ドロペリドールとフェンタニルといった神経遮断薬と麻薬性鎮痛薬の組み合わせにより,意識を失わせること無く手術可能な鎮痛作用を得ることができる.この方法をニューロレプト鎮痛(neurolept-analgesia,NLA)と呼んでいるが,この方法は,麻薬を用いなくても実施可能である.獣医学領域でもトランキライザー,鎮静薬とオピオイドなどの組み合わせが広く用いられ,トランキライザーや鎮静薬を単独で用いるよりも使用頻度が高くなっている.これは,複数の薬剤をそれぞれ少ない用量で組み合わせると,より強力な作用をより少ない副作用で得られるためである.これらの組み合わせは,強力な鎮静薬や安定した麻酔前投薬として用いられることが多く,最近ではメデトミジンとミダゾラムといった,NLAの概念に該当しない組み合わせも広く用いられるようになっている.このようにこれらの組み合わせにはさまざまな種類があり,用途や対象動物の状態によって最も適切なものが選択される.トランキライザー,鎮静薬,オピオイドの組み合わせとして,表2にその例を示す.
前述のように,これらの組み合わせの中で,ケタミンに期待する鎮静状態に匹敵する効果を得られるのは,メデトミジンの組み合わせである.しかし,組み合わせ使用した場合にも,その注意事項は前述のメデトミジン単独で使用した場合と同様であり,適応範囲を守って使用する必要がある.多くの場合,これらの組み合わせで鎮痛,筋弛緩作用を伴った強力な鎮静効果が得られるが,メデトミジン-ミダゾラムを投与しても効果が不十分な場合あるいはより強力な効果を得たい場合には,ブトルファノール(0.1mg/kg)を加えるとさらなる効果の増強が得られる.アセプロマジン-ブトルファノールの組み合わせでも中程度の鎮静効果が得られるが,ケタミンに期待するような強い効果を得ることは多くの場合難しい.
|
2 ケタミンを用いない麻酔導入方法
前述のように,一般的に筋肉内投与できる注射麻酔薬は存在しない.したがって麻酔を導入するためには,静脈内に薬剤を投与するか吸入麻酔薬を吸入させて導入する必要がある.留置針が入れられない場合には,必要に応じて麻酔前投薬を投与して鎮静を得た後,留置針を留置し,チオペンタールあるいはプロポフォールを静脈内投与して導入するか,吸入麻酔薬をマスクあるいは導入箱を用いて投与して導入する.注射麻酔薬として利用できるのは,チオペンタール,チアミラール,プロポフォールなどがある.ケタミンとこれらの薬剤の大きな違いは,筋肉内(皮下)投与ができないことの他,鎮痛効果が非常に弱いことである.したがって,ケタミンを使用しない場合には,状況(導入後の麻酔方法や作業内容)に応じて鎮痛薬を併用する必要がある.
1)注射麻酔薬による麻酔導入
上述の注射麻酔薬中で最も頻繁に用いられている薬剤は,プロポフォールであろう.プロポフォール(2,6-ジイソプロピルフェノール)は,アルキルフェノール系の薬剤であり,一回投与による全身麻酔の導入,あるいは間欠投与もしくは持続投与による維持麻酔や鎮静に用いられている.プロポフォールは,分布,代謝,排泄が早く,麻酔の導入・覚醒が超短時間型バルビツレイト(チオペンタール,チアミラール)よりも迅速である.またバルビツレイトと異なり反復・持続投与しても蓄積作用は少ない.プロポフォールはほとんど水に溶けないため大豆油,グリセロール,卵レシチン(静注用脂肪乳剤とほぼ同一組成)との縣濁液の形で供給されている.多くの製剤は,保存剤を含まないため,細菌が増殖しやすいため,その取り扱いには注意が必要である.プロポフォールは,通常の輸液剤のラインから混合して投与しても問題はない.
a)プロポフォールの臨床応用:プロポフォールは,麻酔導入の他,短時間の麻酔によるX線検査,簡単な歯科処置,小手術,バイオプシーなどにも応用可能である.プロポフォールは,超短時間型バルビツレイトを投与すると覚醒時間が延長する視覚犬でも,迅速な覚醒が得られるため使用しやすく,覚醒時にトラブルを起こすことの多い短頭種でも使いやすい.また低用量で用いれば,短時間の鎮静状態が得られ,喉頭麻痺の検査,アレルギーの皮内反応試験にも用いることができる.
犬で麻酔導入薬として用いる場合の必要量は,6.0〜8.0mg/kgとされており,われわれの検討では,臨床例において円滑な気管挿管が可能となるプロポフォールの必要量は,6.5±1.4mg/kgであった.一方,気管挿管を行う場合,猫(あるいは小型犬)ではこれよりも高用量が必要な場合が多く,臨床例での必要量は,10.2±2.8mg/kgであった.ただしこれらの投与量はあくまでもガイドラインとして捉えるべきであり,気管挿管に必要な投与量は,個体によって比較的大きく異なる.実際の投与にあたっては,予定投与量の約1/4〜1/3量ずつをそれぞれ15〜30秒程度かけながら,気管内挿管が可能となるまで投与するとよい.挿管可能となるまでの変化は,チオペンタールなどとよく似ており,迅速,円滑に麻酔状態が得られる.ただし,バルビツレイトに比べて覚醒が早いので,バルビツレイトを用いた場合よりも早めに維持麻酔に十分移行させたほうがよい.ちなみに健康なビーグル犬を用いた検討では,プロポフォール単独とチオペンタール単独投与時の覚醒時間は,それぞれ15.9±2.3および32.6±21.1分であった.
b)麻酔前投薬の効果と影響:麻酔前投薬を用いることによって,麻酔導入を円滑・安全にし,かつ動物に与えるストレスを軽減することができる.麻酔前投薬としては,アセプロマジン,ジアゼパム,ミダゾラム,キシラジン,メデトミジン,ブトルファノールなどの各種鎮静薬,鎮痛薬が用いられるが,これらの薬剤を用いた場合にはプロポフォールの必要量が1/4から1/2程度減少するため,麻酔が深くなりすぎないように注意する必要がある.われわれが健康なビーグル犬を用いて行った実験では,円滑な気管挿管が可能となるプロポフォールの必要量は,メデトミジン20μg/kg+ミダゾラム0.3mg/
kg前投与後では2.7±0.7mg/kg,アセプロマジン0.05mg/kg+ブトルファノール0.2mg/kg前投与後では,3.8±0.6mg/kg,そしてミダゾラム0.1mg/kg+ブトルファノール0.2mg/kg前投与後では,4.9±0.8mg/kgと,麻酔前投薬無しの場合に比べ60〜25%程度減少した.
c)プロポフォールとバルビツレイトとの比較:プロポフォールと超短時間型バルビツレイトを比較して,プロポフォールが優れている点は,[1] 覚醒が早い,[2] 視覚犬(ボルゾイ,アフガンハウンド,グレーハウンド,サルーキなど)においてもバルビツレイトのような覚醒遅延が無く,安全に使用可能である,[3] 肝不全や腎不全がある場合にも比較的安全に使用することができる,[4] 蓄積作用が少なく,追加投与ができる,[5] 持続投与によって維持麻酔として用いることができる,[6] 投与直後の頻脈,血圧上昇が少ない,ことなどがあげられる.一方プロポフォールの問題点としては,[1] 投与後の無呼吸がより生じやすい,[2] 細菌が繁殖しやすい製剤であり,その取り扱いには注意が必要である.
d)プロポフォールの中枢神経系に対する作用:プロポフォールは,バルビツレイトと同様脳保護作用を持つが,その作用機序はバルビツレイトとはやや異なっている.しかし,いずれにしても臨床的には脳血流量,脳代謝量とも同様に減少し,結果として頭蓋内圧が低下するため頭蓋内圧上昇例では吸入麻酔薬に比べ安全である.またプロポフォールは,吸入麻酔薬と異なり,脳の自己調節能を保ちやすいという特長もある.
e)プロポフォールの循環器系への影響:プロポフォールは,心筋に対して抑制作用を示し,血管拡張作用も持つ.このためヒトで麻酔導入量のプロポフォールは,平均動脈圧を25〜40%低下させ,心拍出量も減少させる.犬でも導入量のプロポフォールの投与により動脈圧が約30%低下したが,心拍数が軽度増加したため心拍出量は変化が無かった.プロポフォールによる血管拡張は,交感神経系の抑制に加え,血管平滑筋のカルシウム動態に直接作用して引き起こされる.プロポフォールは,圧反射機能を抑制するため,血圧低下に対する心拍数上昇が生じにくい.犬においてプロポフォールを持続投与すると,平均動脈圧は投与前値に比べ30〜40%低い値を維持したが,ボーラス投与時と異なって心拍数の上昇は認められず同様に低下した.一方プロポフォールの持続投与時には,投与開始100〜120分後以降から動脈圧が徐々に回復する傾向があった.プロポフォールの持続投与に亜酸化窒素やオピオイドを併用すると,心拍出量の減少が認められることが報告されている.
このような変化は,循環器系に問題のない動物であれば,十分に許容範囲であるが,脱水のある動物,あるいは心不全の程度が強い動物では血管拡張作用と心筋抑制作用が強調され,強い血圧低下をみることがあるため注意が必要である.
f)プロポフォールの呼吸器系への影響:プロポフォールを投与すると,比較的強い呼吸抑制が見られ無呼吸となりやすい.これは投与速度が速い時,および高用量を投与した時に顕著である.このためプロポフォールを投与する場合は,動物の状態を見ながら,15〜30秒ごとに1/4〜1/3量ずつ,全体として60〜90秒程度で投与する方法が推奨される.無呼吸は通常30〜60秒程度で解消されるが,まれに120秒程度持続する例もある.無呼吸はオピオイドの併用で延長する可能性があるが,併用によりプロポフォール投与量が減少するため,見かけ上はあまり変化しない.呼吸数と分時換気量は,導入後しばらくは減少したままである.維持麻酔中も一回換気量および呼吸数は減少し,CO2上昇および低酸素血症に対する呼吸反応も抑制される.気管拡張作用を示すがハロタンほど強力ではない.
2)吸入麻酔薬を用いた麻酔導入
麻酔導入は,吸入麻酔薬を吸入させることによって行うこともできる.吸入麻酔薬としては,セボフルランあるいはイソフルランが用いられる.人においては,イソフルランは強い気道刺激性を示し,発咳,息こらえなどのために麻酔の導入がうまく行かないことが知られているが,犬や猫においてはイソフルランでも麻酔を導入することが可能である.吸入麻酔薬を吸入させる方法としては,マスクを用いた方法と導入箱を用いた方法がある.
a)マスクを用いた麻酔導入:マスクを用いて麻酔を導入する場合は,動物の口にマスクをぴったりと当て,低い濃度から徐々に麻酔薬濃度を上げて,麻酔をかける緩徐導入法か,最初から最高濃度の麻酔薬を吸入させる急速導入法で行う.緩徐導入では,動物が暴れてしまいうまく行かないことが多い.急速導入でも最初に暴れることが多いが,短時間(通常3〜5分間)で導入できるため成功しやすい.前投薬を用いて鎮静しておけば,円滑に導入することが可能である.
b)導入箱を用いた吸入麻酔薬による麻酔導入:小さくて保定しにくい動物あるいは保定が困難な動物(齧歯類,鳥,猫,子犬など)では,導入箱(表3)を用いることもできる.野良猫,エキゾチックアニマルなどで有用性が高い.透明な箱に動物を入れ,蓋をし,ここに高濃度の吸入麻酔薬を送り込む.動物の状態を細かく観察することが難しいので,動物の意識が消失したら取り出し,その後しばらくマスクで麻酔を続け,完全に麻酔を導入するとよい.
導入箱を用いた麻酔導入法の長所としては,装置の費用が安い,呼吸抵抗が小さい,再呼吸が最小であることなどがあげられるが,その反面欠点として,麻酔薬の無駄が多い,麻酔濃度の調節が難しい,余剰ガスの排出が難しく作業する人も吸引してしまう,麻酔薬の気化が室温に依存することなどがあげられる. |
|
![]()