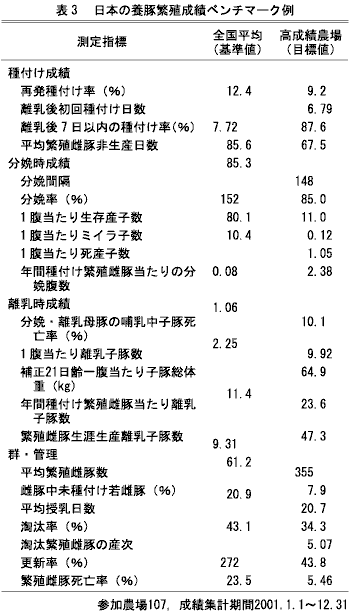4 生産システムをデザインする
現在ある農場の群健康管理だけでなく,生産システムを創る,または再構成することも獣医師の大切な仕事である.そういう仕事をシステムデザインと呼ぶ.
まず養豚生産の簡単な説明をしておく.養豚は繁殖部門と肥育部門に分かれる.繁殖部門には,種付け期・妊娠期・分娩授乳期がある.授乳が終わり離乳された母豚は,順次種付けされる種付け期となる.この3つの期間を平均6回ぐらい繰り返す.分娩を経験していない豚を若雌豚と呼び,初産以降を母豚と呼ぶ.両方あわせて繁殖雌豚と呼ぶ.
肥育部門では,離乳された子豚は,体重または日齢で区別された離乳期から子豚期と肥育豚期の3期で豚舎を移動させられ,約110kgで出荷される.米国では,肥育部門は離乳期と子豚・肥育豚期の2期が普通である.
以下北米で獣医師が中心になって創られたシステムデザインの実例を挙げる.
実例1,繁殖雌豚14,400頭での生産[19].
このシステムは,3,600頭の繁殖雌豚に種付け・妊娠・分娩させる繁殖サイトを4つ,そして4つの離乳子豚豚舎サイト,16の肥育豚舎サイトの計24のサイトからなるマルチサイトシステム(図2と表2参照)である.サイトとは場所のことである.それぞれのサイトは0.64km2 の広さを持っている.他の違う種類のサイトとは4kmの距離を保ち,同じ種類のサイトでも,肥育サイトでは1.2km,繁殖サイトでは1.5km,離乳サイトでは0.8kmの距離を保つように建設されている.
4つの繁殖サイトでは,1週間に計800頭の繁殖雌豚を種付けする計画生産が実施されている.80%の分娩率で1週間に640頭の分娩があるように計画されている.ここでは1週間を単位とするグループ生産(表2参照)が行われている.
1繁殖サイトには3,600頭の繁殖雌豚が飼育され,1週160分娩で4週分である640の分娩豚房がある.それらは40豚房ごとに16の分娩室(4週分)にわけられている.平均3週離乳で,1週間の分娩室の空白期間をもち,分娩室ごとにオールイン・オールアウトができる.
1繁殖サイトでは1週間に160頭の授乳母豚から,1,400頭の子豚が離乳され,離乳子豚は離乳舎サイトに移動される.1離乳舎サイトは8豚舎からなっている.週ごとに1離乳サイトに離乳子豚が収容されると,同時に他の離乳サイトの一つは,肥育舎へ移動される.離乳子豚は50から55日間,離乳サイトにおかれ,そのあと肥育舎サイトに移動される.ここでもオールイン・オールアウトがなされている.
肥育サイトにおける肥育舎は,離乳舎に対応して,8豚舎からなっている.離乳舎の同じ部屋にいた豚は,肥育舎でも同じ部屋に移動される.肥育豚は肥育舎で15週間収容され出荷される.
全繁殖雌豚は個体でコンピュータ管理し,繁殖成績を記録・分析している.離乳舎・肥育舎ともに豚を入れる時と出す時に,群の体重測定をしている.飼料の運搬量はサイトへの持込時に豚のグループごとに測定して肥育成績を定期的に記録・分析している[8].
実例2,巨大ファームのバイオセキュリティ[6]
米国の養豚生産者は大規模になり,そこから多数の農場を保有し母豚総数1万頭を超えるメガファームと呼ばれる巨大生産会社が出現してきた.米国巨大生産会社の一つ(以下B社)のバイオセキュリティ(表2参照)について紹介する.B社は母豚132,000頭を保有し,年間240万頭の肉豚を生産している.B社にとってポーク生産はサイエンスと管理の集中的プロセスであり,現代育種学,授精技術そして生産システムと管理の情報と知識が必須であるとしている.
B社のバイオセキュリティシステムの概要
- 農場を人里はなれた場所に建設する.
- 豚舎は機械換気法で,野鳥が入らないようにされ,周囲フェンスと鍵付きドアがある.豚舎はねずみ類が近づきにくいような構造を持っている.
- 全畜舎に厳しい出入り制限をつける.例をあげると,従業員でも自分の仕事場以外の部署に行くときは豚のいない場所での24時間の待機時間を義務づけている.
- 種豚をハイヘルス状態に保つ.健康で病気抵抗性を持つ母豚の選抜と種付け群としてのピッグフロー(表2参照)を良くする.ハイヘルスとは,生産上大きな問題となる疾病がない,または制御されている状態である[4].
- 各部門でのオールイン・オールアウトによる清潔さの維持
- 生産指標の定期的測定と記録・分析を行う
- 飼料とトラックも定期的に検査され移動は常に記録・分析されている.運搬時にはトラックは水洗・乾燥・消毒される
もし病気が発見されれば,その動物群への影響を軽減し,かつ他の施設への拡散を防ぐために治療がなされる.
B社はこのバイオセキュリティの実践で病気発生のリスクを下げ,施設の分散により病気伝播のリスクを下げることで,病気の発生と拡散による経済的影響を下げている.
実例3,繁殖雌豚の産歴別飼育[14]
カナダのC社が実行している雌豚の産歴による分離飼育システムは,初種付け前の若雌豚と初産の母豚は,2産以上の経産豚とは違う生産管理が必要ということで作られたシステムである.
このシステムをデザインした理由は以下である.
- 若雌豚に十分な馴致期間を与える.養豚界ではPRRSという厄介な病気があるからである.そのため若雌豚は隔離・馴致が必須といわれている.
- 若雌豚の育成を専門化できる
- 若雌豚への発情発見は特に注意深くできる
- 若雌豚への12時間間隔での種付けを専門化できる
- 初産豚のための特別な配慮ができる
C社は繁殖雌豚12,000頭のために,以下の豚舎群を用意している.
(1)若雌豚(産歴0)を育てる豚舎群.この豚舎で,若雌豚は体重25kgから,馴致を始めて,農場に存在する病気に暴露している.135日齢までは身体のたん白質を最大限に増やすような飼料を与えている.
(2)若雌豚に種付けする豚舎群.若雌豚を平均185日齢または体重125kgでこの豚舎に移動する.精管を切除した雄豚で,1日2回刺激する.初発情が発見され次第,種付け舎に移動する.次の発情で種付けし,背脂肪厚と体重を測定・記録し,次の豚舎に移動する.
(3)若雌豚の妊娠舎.ここで妊娠80日齢まで飼育する.
(4)若雌豚が分娩するまでの妊娠舎と分娩豚舎(産歴1となる).妊娠95日から飼料を1kg増やす.適切な時期に分娩舎に移動する.
(5)離乳後種付けされる豚舎.産歴1で種付けされた雌豚を妊娠期中期(50から70日)に(6)の豚舎に移動する.
(6)産歴2以降の雌豚ための豚舎.(5)で種付けされた母豚及びそれ以後の母豚を飼育する.
さらに産歴1の母豚と2以降の母豚から生まれた子豚は違った肥育豚舎で育てられる.産歴1の母豚から生まれた子豚は,母乳からの移行抗体が少ないと考えられているからである.
|
![]()