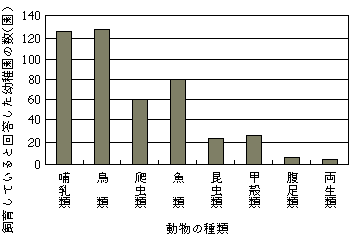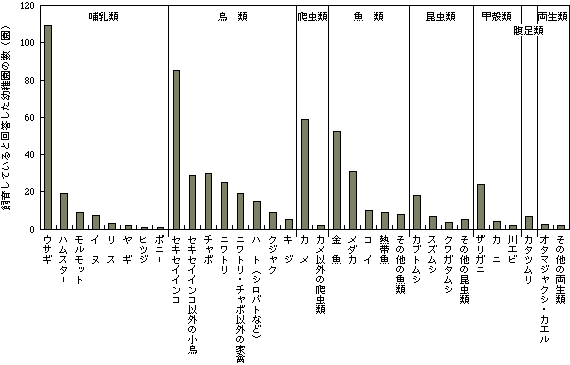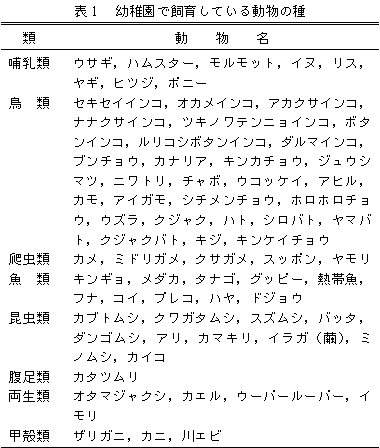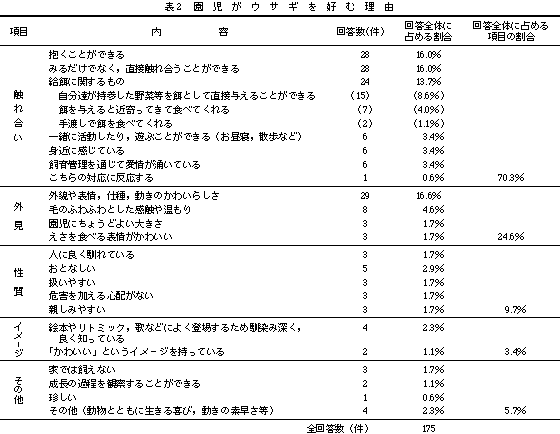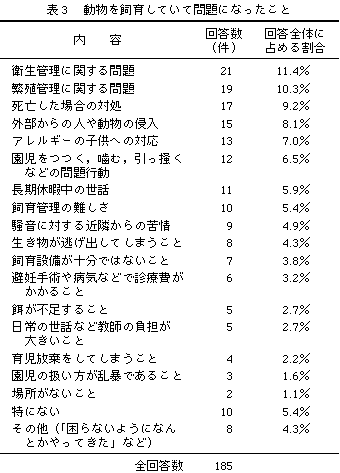| 《1》 |
動物の世話
飼育している動物の世話は,47.6%が「教諭が主として行うが園児にも手伝わせている」,30.7%が「園児が主として行うが教諭が補助する」とし,合わせるとほぼ8割の幼稚園が園児を動物の世話に関わらせていたが,その半数が当番制で,残りは希望制をとっていた.また,園児や教諭以外に,「園バスの運転手さん」「ボランティア」「園長」などが世話をしているところもあった. |
| 《2》 |
動物飼育にかかる負担
「経済的に負担ではない」「労力的に負担ではない」はともに7割を占めたが,3園の幼稚園は「労力的に非常に負担である」と回答した.3園中2園は,園児数がかなり多く,その内の1園は,235匹(羽)(哺乳類15匹,鳥類220羽)も動物を飼育しており,労力的に負担であることは明らかであった. |
| 《3》 |
動物飼育上の問題点
動物を飼育していて何らかの問題があると回答した幼稚園は,95%にものぼった.また,問題を複数抱えている園がほとんどであった(表3).その主なものは「衛生管理に関する問題」(21園)と「繁殖管理に関する問題」(19園)であった.「衛生管理に関する問題」では,人と動物由来感染症に関する知識に乏しいため,「動物からの病原菌の感染」を漠然と危惧する幼稚園が多く,「園の動物に触れないように言い渡している保護者もいる」などの声も聞かれた.「繁殖管理に関する問題」では,飼育数のコントロールに関するものが多く,「増え過ぎて,場所や餌などが幼稚園で飼える許容量を超えている」といった回答もあり,雄雌をむやみに同居させたり,雌雄の判別もせずに無計画に繁殖させている例がほとんどであった.また,生まれた子畜をそのまま親兄弟と同居させておいたために,「近親交配で子畜が奇形になり,早く死んでしまう」といった問題も発生していた.
一方,飼育している動物が病気になった場合,診察してもらうかかりつけの獣医師さんがいないと回答した幼稚園が68%にものぼった.また,動物の飼育方法について専門的な助言を受ける人がいないと回答した幼稚園も半数近くあった.助言を受ける人がいると回答した幼稚園は,その相手として「(園長を含めた)飼育経験者や動物を飼っている知人」「動物園」「ペットショップ」「動物愛護センター」などをあげていた. |
| 《4》 |
動物を飼育することの教育的効果
「園内で動物を飼育することの教育的効果」に「非常に満足」「やや満足」を合わせて,83%の幼稚園が満足していると回答している.満足しているとしてあげられた主な理由は,「思いやりや責任感,やさしさなどの心の教育」(74園),「死生観を伝えることができる」(48園),「生き物との触れ合いの場を提供することができる」(28園),「生き物と接することで園児の心が癒され,園生活に自然に溶け込める」(19園),「理科的な知識の教育」(16園)などであった(複数回答).Levinson[6]も,動物を育てることは子供の感性,自尊心,自制心,自立心を養う手助けをすると報告している.幼児にとって,他者の活動に参加すること,他者に受け入れられること,ほめられること(陽性強化措置)は,自尊心を養うためにきわめて重要な要素である.幼い頃から動物の世話や育成を大人(教諭や保護者)と一緒に行い(参加),その過程で年相応の作業を任され(受け入れ),それを成し遂げたことをほめてもらう(強化)ことによって,子供は自分にも能力があるという自信をもつことができる.また,Paul[9]は,飼い主に全面的に依存しているペットなどの動物に,幼いうちから接することで,物言わぬ動物の気持ちや欲求を読み取る訓練をすることになり,大人になった時に他者の気持ちを汲むことができる心が育つのではないかと示唆している.さらに,Poresky
and Hendrix[10]は,3〜6歳の子供を対象とした調査で,ペットを飼育している子供は,飼育していない子供よりも,他者への感情移入の度合いが高くなることを報告している.もちろん,動物を飼育するだけで誰でも他者に対する共感が育つようになるのではなく,子供がどれだけその動物に愛着を持っているのかが鍵となる[11].先のLevinson[6]は,動物を飼育することによる情緒的な支えは,子供の精神的発達にとって大きな役割を果たしているとしている.Bachman[1]は,人間よりもむしろペットに悩みごとを相談する子供もいることを指摘している.動物は,親や先生のように,自分を評価したり非難したりすることがなく,無条件に愛してくれると感じる子供もいるようである[2,
3]. |
| 《5》 |
飼育動物の死
「飼育していた動物が死んだ時に園児に知らせるか」という質問には,89%(150園)の幼稚園が,園児に対して何らかの説明を行うと回答したが,5%(8園)の幼稚園は,「特に説明しない,死骸を園児には見せないようにして処置する」と答えている.Nagy[8]は,子供の前から死を隠すべきではないと主張している.自然な死に触れておくことで,死に対する子供の恐怖を減少させることができるからである.園児に対する説明としては,「死亡したという事実や死亡した理由を伝える.園児の疑問に答える」という回答が最も多く(68園),次いで「生命や死について考えさせるよい機会と捉え,寿命があることや,生命を大切にすることなどを園児に話す」(48園)があげられた.「浄土に行く」と説明した幼稚園は7園であったが,いずれも仏教系の幼稚園であった.しかし,「天国に行く」と説明した幼稚園が必ずしも宗教的背景を持っているわけではなかった. |
| 《6》 |
園児の動物に対する態度
「過去の園児と比較して,最近の園児の生き物に対する態度が変化した」と回答した幼稚園が,約2割あった.その中には,「住宅環境の変化から自宅で生き物を飼う幼児がほとんどおらず,入園までに生き物に触れた経験のない子供が多い.生き物に対して好奇心一杯に関わる姿は昔も今も変わっていないが,今の子供達は接し方が分からないためか抱き方や触り方が乱暴である」「おもちゃのように動物を扱う」「自分本位で接しがちである」「何でもない昆虫,たとえばアリやセミを異常に怖がり,泣き出す子供もいる」「昔の園児ならば見向きもしない様な虫を異常に珍しがったり(ナメクジを)可愛がったりする」「ネコやイヌ,虫が身近な存在ではなくなり,特別な生き物として見ているように感じられる」「動物にまったく無関心な子供が増えた」「動物に餌をあげたり世話をしたいと希望する子供の数が減った」「触ることを拒む」「清潔さに敏感すぎる」「幼稚園に小動物や植物を持ってこなくなった」「知識の上ではよく知っており情報も豊富だが,実際の生き物,たとえばカエルなどを与えると『見るのは初めて』『初めてだから触れない』という子供がいる」「命の尊さに関して欠落している部分が見られる」「死んでも『また買ってくればいい』という子供がいる」「セミ採りに行っても自分でセミを採ることも自分でセミを持つこともできない」などの回答があった.その他に,「動物を怖がって世話ができない教諭がいる」という回答もあった.住環境や自然環境の変化が最も大きな影響を与えているのだろうか,教諭や保護者などの大人の動物に対する態度や対応が子供の動物観に影響することを考えると,今後は保護者や教諭を含めた動物教育が必要であると考えられる. |
![]()