| 全国の食肉衛生検査所では,BSE発生以前の課題として,1996年の腸管出血性大腸菌食中毒の多発に対応した食肉の病原微生物汚染防止対策としてのと畜場の施設・設備および維持管理の向上を目的とした,新衛生基準(いわゆる14年度対応)施行のため,全国的なと畜場の統合・整備と新たな検査体制整備の真っ最中であった.これにあわせて,以下のBSE緊急対応を実施した.BSE国内発生から約5カ月経過し(2月中旬),すでに,かなりの課題は解決されたが,懸案事項も残されている. |
| |
1.BSE発生から検査体制の整備
| |
(1) |
検査開始のための環境整備
検査所においては,短期間での緊急検査体制の整備にあたって,高額な機器整備,専用検査室の確保等予算措置,検査員の確保・検査技術研修等の対応に追われた.また,一方,と畜場における特定危険部位(以下「SRM」という.)の除去,と畜・解体方法の変更に伴う対応等,さまざまな問題に直面することとなった.さらに,肉骨粉の製造・販売・使用・輸入禁止の措置およびSRMの焼却により,と畜場由来廃棄物のレンダリングによるリサイクルが完全にストップし,廃棄物の出口が塞がれたため,食肉処理に支障をきたした.このことは,10月18日の全頭検査を前に解決しておかなければならない重要なことであった.このレンダリングについては,私も参加した農水省の「BSE対策検討会」の席上,関係委員とともに状況を報告し,暫定的にと畜場廃棄物をいったん肉骨粉にしてから焼却する「中間加工品」の処理として,既存のレンダリング施設の活用・協力が得られ,さらには,SRMの焼却についても,全国の市町村関係者等の努力により目途がたち,わずか1カ月の間に解決の光が見えた. |
| |
(2) |
ELISA検査とキットの緊急輸入
全国一斉検査開始に向け,厚労省の努力により,検査キットの緊急輸入と「全額国庫補助」による全国の検査機関配付がなされた.
これにより,すべての牛において,全国の食肉衛生検査所で,ELISA法によるBSEスクリーニング検査が実施されている. |
| |
(3) |
検査員の確保
陽性と判定された検体は,帯広畜産大学で確認検査が実施され,厚労省BSE検査に係わる専門家会議で確定診断が実施されるシステムが構築された(後日,横浜・神戸検疫所,国立感染症研究所に確認検査の機関が拡大).
また,農水省サイドでも独立行政法人動物衛生研究所において確認検査が行なわれ「BSEに関する技術検討会」で確定診断が実施されるという同様のシステムが構築されている. |
|
| |
2.BSEスクリーニング検査の開始と対応
| |
(1) |
新たに付加された検査業務
食肉処理されるすべての牛に対する出生歴・飼育歴等の確認,臨床診断等生体検査の強化(図1).
個体識別,保管・管理,SRMの除去,検査員・従業員等の感染防御対策等が付加された(図2).
全頭数スクリーニング検査開始により,2例のBSE患畜が発見され,『BSE全頭検査』制度が機能している証しと評価される一方で,各所の対応状況は,日々の検査頭数と再検査の頻度にもよるが,毎日が緊張の連続で,時間外検査に及ぶことも多い(図3). |
| |
(2) |
BSE検査一元化の必要性
食肉は生鮮食品であり,と畜検査は迅速・的確が基本とされている.
BSEスクリーニング検査は,再検査を要しない場合4〜5時間で結果を出せるが,陽性になった場合,国の機関で確認検査を実施するため,検体の輸送等に相当な時間を要している.
今後は,BSEに係る一連の検査を全国の食肉衛生検査所で実施できるよう努力する必要がある.
そのためには,食品衛生法と同様,と畜検査のGLP(精度管理)の導入,国の機関から自治体検査員への技術指導,効率的検査法の開発等が待たれる. |
 |
| 図1 生体検査の強化:複数検査員対応状況 |
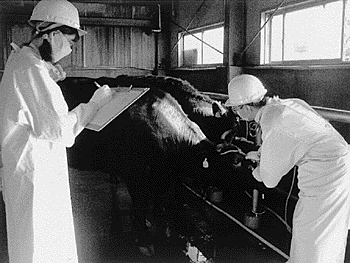 |
| 図2 BSEスクリーニング検査と感染防卸 |
|
|
| |
3.と畜・解体方法の改善
| |
SRMの除去が義務づけられているが,歴史的にと畜・解体に必要不可欠とされてきたピッシング(脳・脊髄の破壊による神経麻痺:不動化)や背割の際の脊髄による枝肉等の汚染問題が指摘され,その対応策が課題となっている. |
|
| |
4.背割と脊髄除去問題に関する全食検協の取り組み
| |
より安全な食肉処理方法の確保のため,脊髄の破壊および除去方法等について,厚労省の厚生科学特別研究事業の一環として,分担研究を実施している.
予備調査として,全食検協加入機関を通じ,脊髄除去方法等の現状を把握した.
| |
(1) |
脊髄破壊方法の調査結果
スタンニング(打撃)後,大半のと畜場はワイヤー使用(80%)であったが,静置(14%),脊髄切断(6%)法など,ピッシング廃止の模索例も試みられている(図4). |
| |
(2) |
背割方法の調査結果
背割については,従来法どおりの背割後脊髄除去を行っていると畜場は正中線背割法が75%,非正中線背割法が12%であった.また,吸引法(7%)または押出法(3%)などにより,背割前の脊髄除去を実施している機関やBSEスクリーニング検査後に背割を実施している機関があり,脊髄除去に係る各機関の模索実態を把握できた(図5). |
| |
(3) |
より安全(適正)な脊髄除去方法の検討
予備調査結果に基づき,試行または導入中の複数の方法について,関係者の協力のもと,実験的データを蓄積し比較検討した.その結果は,BSEに関する研究班会議でも検討・検証され,背割前の脊髄除去に関して,機器導入の指導および導入に係わる国庫補助について通知されたところである(1月31日付け,食監発第0131001号). |
|
|
| |
5.と体全部の一時保管義務と保管施設の確保
| |
スクリーニング検査および確認検査の結果が判明するまでの間,食肉処理されるすべての牛のと体全部(枝肉・内臓・SRM・不可食部位)を一時保管する必要がある.しかし保管施設の確保が難しく,従来の施設では食肉処理が制約されつつあり,冷蔵施設などの保管施設の充実が求められていることから,厚労省および農水省において補助の制度が設けられている.
また,保管中の病原微生物の汚染,増殖の防止のための指導にも対処しているところである. |
|
| |
6.SRMの焼却施設の確保
| |
暫定的に,焼却施設のあると畜場では場内焼却,それ以外の施設では清掃工場等を活用してきたが,廃棄物の処理および清掃に関する法律の改正により,SRMが産業廃棄物に指定されたことから,一般廃棄物としての焼却が不可能となる本年10月以降,牛の頭部を含むSRMの焼却は膨大な量となり,受益者負担にも限界があることから,国家的対応が強く望まれている.
具体的には,除角・下顎の除去等によるSRMの減量化,公的・広域的処理施設の建設,と畜場内焼却施設を含む民間処理施設への公的補助,さらには,焼却灰のセメント化等資源化も検討されている. |
|
| |
7.BSE陽性牛発生時の対応
| |
BES陽性牛となった「と体のすべて」は,法に基づいて焼却処分されるが,場内に焼却炉が併設されていると畜場は少数であり,さらに,感染性廃棄物としての処理費用は高額となる.SRMと同様,公的・広域的処理施設の建設が望まれる. |
|
| |
8.レンダリング処理施設の安全確保と循環型社会
| |
と畜場由来廃棄物が,BSE発生に伴い,肉骨粉等の製造・販売・輸入の全面禁止となったため(ただし,後日,牛由来以外の蒸製骨粉の肥飼料化等は一部条件付きで解除),その処理自体が支障を来している.
早川[2]は,畜産リサイクルのカギは「肉骨粉対策」であると明言している.
農水省のBSE対策検討会でも議論されているが,安全な循環型社会の構築には,以下の条件整備が必要である. |
| |
(1) |
牛のレンダリング原料は,全頭数検査開始後のBSE検査合格材料のみを使用する. |
| |
(2) |
畜種別分別処理(収集・加工・製造)を確立する(と畜場・レンダリング施設等の分別処理機能の確保). |
| |
(3) |
OIE(国際獣疫事務局)処理基準(133℃・3気圧・20分間)を厳守する. |
| |
(4) |
全工程の公的監視・検証システム(マニフェスト方式等)を構築する. |
|
| |
9.廃用牛対策および病畜検査のあり方
| |
BSE患畜3頭が,いずれも高齢の乳廃牛であったことから,生産,処理,流通関係者の思惑も影響し,大量の廃用牛の処理が停滞している.
一方,安全な食肉の生産には,「処理される家畜は健康である」ことが大前提である.食品工場であると畜場に病畜を搬入することは消費者の視点から見直すべき時期かも知れない.EUでは,病畜専用の処理場が存在し,特殊用途に利用されていることも踏まえ[3]抜本的な施策の展開が望まれる(図6). |
|
| |
10.検査結果の公表
| |
都道府県においては,スクリーニング検査陽性の段階で公表する場合と確定した段階で公表する場合に別れている. |
|
| |
11.トレーサビリティの導入と安全情報の提供
| |
家畜の履歴管理等のため,農水省による「BSEとフードシステム・アプローチ」「トレーサビリティ」がスタートし,ようやくFarm to Tableの管理システムの構築が認識されつつある.このシステムが完全に機能すれば,国産牛肉の安全と安心は担保される.特に,最近大手スーパーで導入された,消費者による「店頭での購入牛肉の履歴検索システム」と長野県で導入された「長野県牛肉生産情報表示販売システム」は消費者の視点で高く評価される.
食肉衛生検査所においても,市場側の要望に対し,検査合格枝肉等の「BSEを含む検査済証明の発行,枝肉への検印(合格印)に加え,処理年月日・個体識別・処理場名等の表示を全国一様ではないが実践しつつある.
法的根拠の有無にかかわらず,市場経済原理が優先されつつあるが,家畜生産サイド,食肉処理施設および行政の対応策の程度と情報提供の質が,安全・安心の指標になったことを,強く認識しなければならない. |
|
| |
12.BSE感染源の究明・再発防止対策
| |
輸入肉骨粉と代用乳等が感染源として疑われており,感染源の特定が望まれる.また,飼育されているすべての牛(廃用牛・へい死牛を含む)についても順次BSE検査を実施し,感染実態を明らかにするとともに,感染源のレンダリング利用を完全に防止する必要がある. |
|
| |
13.厚労省への要望書の提出
| |
これまでに述べた課題等の早期解決のため,全国の食肉衛生検査所の意見・要望を集約し,厚労省あて,牛海綿状脳症(BSE)検査に係わる緊急要望書も提出させていただき,施策の展開に反映されつつある. |
|
|