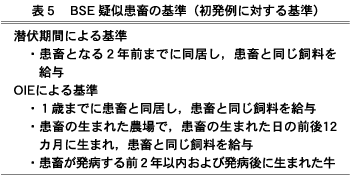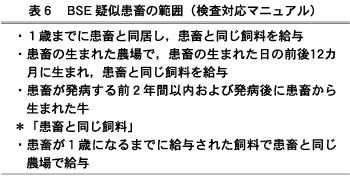![]()
| 患畜等の届出義務 | |
| BSEに関する技術検討会およびBSE防疫委員会が開催され,当該牛がBSEに感染している疑いが強く示唆されたことから,国との協議のうえ,9月13日BSE疑似患畜発生を県報告示した. 生前診断できないとされるBSEについても,家畜伝染病予防法に基づき,当該家畜を診断しまたは死体を検案した獣医師が患畜の届け出を行うこととされている. しかし,都道府県では確定診断するための検査は行っておらず,診断に過誤が生じた場合には,届け出た獣医師の責任も問われる可能性があり,届出には確定検査の結果等を十分に踏まえて対応することが必要と考える. |
|
| 化製処理と汚染肉骨粉の焼却 | |
| 9月14日,農林水産省は,当該牛が化製処理され肉骨粉等に加工されていたことを発表した.これは10日の記者会見で「当該牛はすべて廃棄され,食用に供されていない」と発表し,「焼却処分か」という問に対して「食用に供していないことから焼却したはず」としたことを訂正したものである. その後の調査で,当該牛を処理した茨城県にあるレンダリング場は7月28日から9月13日までの間に210トンの肉骨粉を製造し,大半は徳島県に出荷され,その一部は配合飼料原料とされたが,配合飼料を含めてすべて倉庫に保管されていることが判明した. 当該牛が処理される8月5日以前に製造された肉骨粉はBSEと無関係だが,明確に区分できないことから全量を家畜伝染病予防法に基づく汚染物品として指定した. 農林水産省および徳島県との協議の結果,肉骨粉102トンおよび配合飼料102トンは千葉県内の焼却場で処理することとなった. 焼却には10月23日から11月6日の14日間を要し,「異常プリオンの不活化は800℃以上で完全に灰になれば良い」とされており,この条件を満たす950〜1,200℃で処理された. また,茨城県にあるレンダリング場に保管されていた残りの肉骨粉76トンについても同様に千葉県で焼却された. |
|
| BSEに係る疑似患畜の範囲 | |
| 初発事例では,BSE疑似患畜の判断は表5に示すように潜伏期間による基準と国際獣疫事務局(OIE)の基準により行われた. 当該農場においては飼養牛46頭のうち,子牛2頭を除き,44頭が疑似患畜に該当するとされた. この基準が今後も適応されると,導入牛がBSE感染牛とされた場合であっても,飼養牛のほとんどが疑似患畜とされ病性鑑定を行うことになり,その措置に対し生産者は大変不安を感じていた. しかし,表6に示すようにBSE検査対応マニュアルで規定された疑似患畜の範囲(OIE基準)では,生後1年を超える初産妊娠牛等を導入した場合,導入牛が患畜となっても「患畜と同じ飼料」とは患畜が生後1年までに与えられた飼料を想定していることから,他の同居牛は疑似患畜とはならない.つまり,農場でBSEの感染原因となるような飼料の給与がなければ,経営を圧迫するような防疫措置は行われない. |
|
|
|
|
|
| BSE疑似患畜等の病性鑑定 | |
| 9月29日,白井市および関宿町の疑似患畜および関連牛合計47頭の病性鑑定を実施した. 飼養牛の処分に際しては,畜主の心情に配慮し,一気に農場から牛を搬出することを前提とした. 一時繋留場所を確保し,順次検査すること等を検討したが,BSEは牛同士の接触感染や空気感染を起こさないことはわかっていても,風評被害の問題から実現できなかった. そのため,約100名の人員を確保し,1日で作業を終了することとした.29日午前7時に当該農場の牛の積み出しを開始し,2カ所の施設で病性鑑定のための採材を行い,と体については焼却までの間,保管するための冷蔵施設へ搬入した.すべての作業が終了したのは翌朝午前5時30分であった. 結果として,人海戦術と夜を徹しての作業により,全頭の病理解剖を終了したが,今後,大規模な農場での発生を想定すると同様の対応は困難である. また,BSEの疑似患畜は焼却処分とされているが,本県の家保が保有する焼却施設では,処理能力は最大でも1日4頭前後にすぎない. そのため,検査により陰性が確認された牛体について,近隣県にある国有施設での焼却を依頼することとしたが,風評を懸念するため受け入れに難色を示す近隣県もみられた. 家畜衛生として大きな課題である豚コレラ撲滅や口蹄疫の発生を想定し,これまで県外レンダリング施設の利用を前提として協議を進めてきたが,今回の事例をもとに,都県間の協力体制を再構築することや高能力な焼却炉の整備が必要である. しかし,都県での対応では規模に限度があり,BSE等家畜伝染病発生時の病性鑑定等の防疫措置に対応可能な国有施設の整備が望まれる. |
|