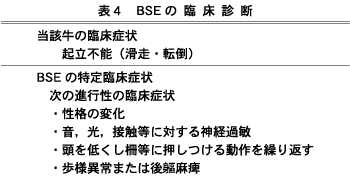| 当該牛の臨床症状とBSEの特定臨床症状 | |
| わが国で最初のBSE感染牛は,県内の酪農家で起立不能のため廃用となった牛がサーベイランスの対象とされたことにより確認された. 7月19日,当該牛が滑って起立困難となったという通報を受け,家畜農業共済組合連合会(以下農業共済連)の獣医師が診療した.しかし,診療時にはすでに自力で立ち上がっており,当日の加療は行っていない.その後,8月5日に再度起立不能となり予後不良と診断され,8月6日に食肉処理場に出荷された. 当該牛のBSE感染が確認されてから,「滑走・転倒・起立不能という臨床症状から,BSE感染を疑えたのでは」という指摘をたびたび受けた. それは,「今回の症例のように中枢神経異常を示す牛」や,あたかもBSEを疑うような「異常な牛」という表現がしばしば使用されていたことからも伺える. これはBSEの症例として牛が滑走・転倒する映像が繰り返し報道された影響も少なくないと考えられる. しかし,農場においては病気となった牛は,症状が重篤になれば当然立てなくなるし,たとえば今回の農場のようにフリーストール牛舎で飼養されている場合には,発情時のマウンティング等により,俗にいう「股開き」となり,起立不能となる牛は少なくない. 千葉県内だけでも,農業共済組合の廃用事故統計や食肉処理場への病畜搬入頭数からも,年間1,500〜2,000頭は起立不能となる牛が発生していると推測される. BSE検査対応マニュアルに特定臨床症状として,起立不能ではなく,表4に示した症状とされたことは,今後,BSE感染牛の的確な摘発に繋がるものと考えられる. |
|
|
|
| BSE検査の経過 | |
| 食肉処理場で8月6日に採材された延髄について,病理材料は9日に中央家畜保健衛生所佐倉に,凍結生材料は13日に動物衛生研究所に搬入された. 「プリオニクステストが陰性なのに,どうして病理検査を実施したのか」という質問を受ける. これは,BSEサーベイランス要領に都道府県が病理組織学的検査を行うことと規定されており,それに基づき千葉県中央家畜保健衛生所が実施したものである. 24日,病理標本の観察で他の検体と異なる空胞がみられたとの連絡を中央家畜保健衛生所より受け,その後の対応を農林水産省と協議した. この時には,日本のBSE汚染の可能性がきわめて低いとされていたこと,サーベイランスが清浄性の確認ために実施していたことから,BSEの感染は疑っていなかった. 農林水産省との協議の結果,念のため9月6日に当該牛の病理標本を動物衛生研究所に送付した. 7日夜,農林水産省からBSEの再検査を実施している旨通報があり,万一に備え関係する家畜保健衛生所に緊急対応が可能な体制をとった. 翌日から,徒労に終わることを願っていた,信じていたという方が正しいと思うが,万一の発生に備えた防疫体制の検討を開始した. 9月10日に免疫組織化学的検査が陽性となったことから,ただちに北部家畜保健衛生所が当該農場への立ち入り調査を実施した. 「BSEの疑いがある」と知らされ,畜主は言葉で表現できないような動揺を示し,聞き取り調査は困難をきわめ,正確で詳細な情報を得るために多くの時間を要した. 調査項目は多岐に渡り,その情報はマスコミを通じて公表されるということから,短期間に,詳細に,正確な情報を把握する必要があった.そのためには,多くの調査員を確保し,対応に当たる必要があったと反省される. |
|
| 発生に係る本県の対応 | |
| 農林水産省からの連絡を受け,千葉県におけるBSEの防疫対策,畜産物の生産・流通・消費対策等を講じ,畜産物の安全性確保に努めるため,農林水産部長を本部長とする千葉県牛海綿状脳症防疫対策本部をただちに設置し対応にあたった. また,庁内各部署の連携を図るために「庁内調整連絡会議」および畜産農家への正確な情報提供・収集のために県内畜産関係団体で構成する「千葉県防疫対策会議」を設置した. さらに,当該牛がBSEの患畜とされた9月22日には知事を本部長とする対策本部を設置し,本部組織体制の強化を図るため,副知事を事務局長とし,総務広報班,防疫指導班,食品安全対策班,流通指導班で構成する千葉県牛海綿状脳症対策本部事務局を設置した. このように,家畜伝染病の一つであるBSEであるが,全庁あげての対応が必要とされ,現在も関係部署との横断的な取り組みが続いている. また,BSE確認に伴う業務量増加に迅速に対応するためおよび県内牛飼養農家に対する全戸・全頭立入検査の実施等,緊急防疫対応を円滑に行うため,畜産課および家畜保健衛生所へ畜産関係機関から兼務職員の派遣および異動・新規採用による人員確保を行なった. |
|
| 当該牛の経歴の特定とその問題点 | |
| 9月11日には当該牛が北海道からの導入牛であることが判明したが,この特定には大きな問題が生じた. これまで,伝染病が発生した場合には疫学関連情報を短期間に収集し,関連農場等の防疫対応を迅速に図ることが重要とされており,そのように対応もされてきた. しかし,BSEについては感染牛の生産農場として特定された場合,関連する飼養牛は疑似患畜となり病性鑑定の対象とされるため,当該農場の経営を左右するとともに,その地域の畜産業に甚大な風評被害を及ぼすことを十分考慮しなくてはならない. そのため,感染牛の経歴特定では絶対に過ちは許されず,証書等との照合による確認が必須条件となる. 今回の事例においては,当該牛がすでに処分されていたことおよび導入牛であったことが特定する上で課題となった. 特定は診療カルテと血統登録書の名号および生年月日の照合により行った. これまでの伝染病であればこれで十分であり,病性鑑定として実施していれば血統登録書と照合し,特定は容易である. しかし,残された材料は頭部だけであり,耳標の有無なども明確にはできなかった. また,導入元とされた北海道からは明確な根拠が求められるとともに,そのため受けた被害に対して責任問題が生じる可能性があり,後日,事実確認のため,農林水産省と県により現地立ち入り調査が行われた. これを救ってくれたのが1枚のスケッチである. このスケッチは,農業共済連の獣医師により,当該牛が導入されたときに描かれたものであり,耳標も分娩月日の順番で装着していたことが判明し,当該牛を特定する根拠となった. また,念のため種雄牛とのDNA鑑定を実施し「親子関係に矛盾は認められない」という結果を得ている. 今回は血統登録証明書を持つ乳用牛であったことから特定できたが,現状では乳用種肥育牛や交雑種肥育牛等では生まれた農場まで遡り特定することは困難と考えられる. 今後,BSEに関する牛の特定には,家畜防疫の概念を超えた影響があることを念頭に置き,このような事態に十分配慮した慎重な対応が必要である. |
|
| 疫学関連遡及調査の困難性 | |
| 疫学関連調査は,本病の潜伏期間が2〜8年とされることから,当該牛が導入された平成10年に遡った調査を実施した. 当該農場は以前一腹搾りの経営を行っており,産歴や授精に関する記録が必要でなかったことから,飼養管理記録は十分とはいえず,牛の移動に関する遡り調査は非常に難航した. また,何度も同じことを繰り返し質問するなど強硬な調査となったことから,畜主は被害者(犯罪者)意識を持つようになったと,平静を取り戻してから当時の様子を話されている. そのような状況下で進められた給与飼料の調査も畜主の記憶だけでは不十分であり,販売元の調査から新たな飼料が判明したこともあった. また,すべての調査結果について書類上の裏付けが必要とされたこと,たとえば牛の販売証明,と畜証明,飼料の購入伝票等について,過去数年に遡り揃えることに膨大な労力を要した. BSEを疑う牛が確認された衝撃や社会の過剰反応,すべての飼養牛の病性鑑定のための処分,マスコミの対応などにより,精神的苦痛と混乱に置かれた畜主との信頼関係を如何に保つかということは非常に重要であり,常に意識においた対応が必要であると改めて認識された. 今回の発生を契機に,英国を始めEUではすでに行われているトレーサビリティシステムである「家畜個体識別システム緊急整備事業」の実施を早め,本年から推進されることは生産段階における個体能力の把握とともに,家畜防疫における疫学調査に大変役立つものと期待される. |