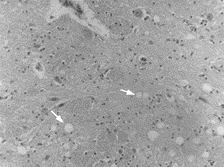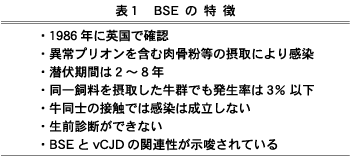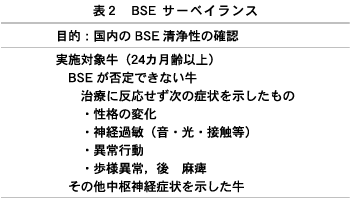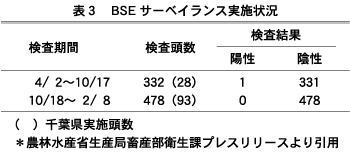資 料
牛海綿状脳症(BSE)の発生と防疫対応の課題
伊藤 健(千葉県農林水産部畜産課衛生班)| は じ め に | ||||||||||||
| 牛海綿状脳症(BSE)は,1986年に英国で初めて確認され,これまで18万頭以上の感染牛が処分されている.BSE感染牛は現在までに,アイルランド,ポルトガル,スイス,フランス,ドイツなどEU諸国を中心に日本を含めた20カ国・地域で確認されている(2002.1.31現在 OIE資料). 日本でBSEが初めて確認されたのは1枚の病理標本(図1)からであった. 今回のBSEの発生により,その特性からこれまでの家畜防疫措置では十分に対応できない問題がみられた. |
||||||||||||
|
||||||||||||
| BSEの特徴 | ||||||||||||
これまでいわれているBSEの特徴を表1に示した.
英国におけるBSE発生に対する消費者の反応は報道されていたものの,日本での発生が牛肉消費に与えた影響は想像を超えるものであった.また,発生後はBSEに対する行政対応の問題が大きく取りあげられ,一時は直面する問題を解決することよりも重要視されたことも,これまでの家畜伝染病の発生においてはなかったことである. これらの特徴を踏まえて,発生の経過と問題点について述べてみたい. |
||||||||||||
|
||||||||||||
| BSEサーベイランス | ||||||||||||
| BSEのサーベイランスは平成8年度以降,臨床検査を主体とし,BSEを疑う牛や病性鑑定のために搬入された死亡牛の病理組織学的検査が行われてきた. 平成13年3月の「BSEに関する技術検討会」において,EU諸国でのBSE発生増加を背景に,日本においてもサーベイランスの検査法を充実させ検査頭数を増やすことが必要とされ,同年4月から開始された. 表2に示したように,サーベイランスの目的は国内のBSE清浄性の確認であり,対象牛はBSEが否定できない牛およびその他中枢神経症状を示した牛とされたが,本県ではこのような症状を示す牛は確認されなかった. 全国的にも中枢神経症状から検査対象とされる牛は少なく,サーベイランスが進捗しないことから,国は5月,神経症状に起立不能や日射病等も幅広に含め,できるだけ早期に目標の300頭を検査することとした. これを受け本県ではサーベイランス対象に起立不能牛を加え,県衛生指導課と協議のもと,県内食肉処理場に病畜として搬入され全部廃棄とされた牛を対象として,食肉衛生検査所と連携のもと推進した. サーベイランスは平成13年10月17日までに332頭,BSE検査マニュアルに基づく同年10月18日から平成14年2月8日までに478頭の810頭に実施され,確認された感染牛は本県の1頭だけである. また,本県では4月以降で全国の検査頭数の約1割,検査対応マニュアルに基づくサーベイランスでは肉骨粉等給与牛を中心に約2割と積極的な取り組みを進めている. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||