(2)患者の血清診断 患者血清の日本脳炎IgG-ELISA抗体は有意に上昇したが、日本脳炎の診断に決定的なIgM-ELISA抗体は陰性であった(表3).そこで他のフラビウイルスの感染を疑いより特異性の高い中和試験を用い抗体価を測定した.日本脳炎に対しては急性期、回復期ともに低い抗体価にとどまったが、ロシア春夏脳炎には急性期ですでに640倍と高く、回復期では2,560倍と有意に上昇した.これらの成績から本症例はダニ媒介脳炎ウイルスの感染によることが血清学的に診断された.さらに、原因ウイルスは強毒型のロシア春夏脳炎ウイルスまたはそれに類似したウイルスによると推定された[6、9]. 1995年には当地区において犬を歩哨動物として疫学調査を実施した(表4).患者発生農家の隣接農家で犬10頭を放し飼いにし4月22日から毎週1回採血し中和抗体の測定とウイルス分離に供した.4月22日では全例中和抗体10倍以下の陰性であったが、5月4日には2頭が陽転し、5月27日には5頭が抗体陽性となった.犬の血液につき哺乳マウスの脳内接種法でウイルス分離を試みたところ、3頭からウイルスが分離された[9]. |
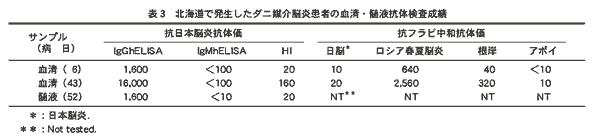 |
|
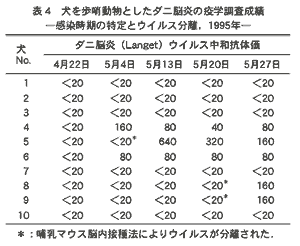 |
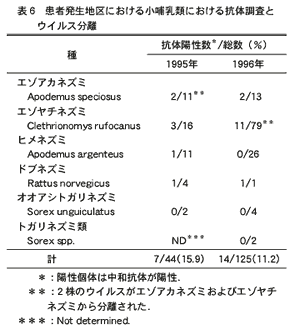 |
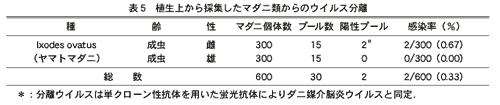 |
|