感染防御抗原の遺伝子感染防御抗原が同定され,その遺伝子構造が明らかにされた病原体は多い.鶏の病原体を例に示そう(表1).感染防御抗原の遺伝子の構造が明らかであれば,次世代ワクチンで予防できる可能性がある.しかし,細菌や寄生虫の多くは感染防御抗原が不明なために,まず遺伝子ライブラリーからその遺伝子を検索・単離し構造を決めなければならない.またウイルスは構造が単純なために候補遺伝子を推定することは容易だが,高い免疫誘導までには挿入遺伝子についての試行錯誤が必要である.2つの遺伝子を例にそのことを考えてみたい.IBDVの感染防御抗原はVP2である.この蛋白をアジュバントとともに鶏に接種すれば免疫を誘導できる.ところが,ヘルペスウイルスベクターあるいはポックスウイルスベクターにVP2を発現させただけでは発病は阻止できても病変は防げない.免疫誘導が不十分なのである.そこで,(1)本来細胞内に蓄積するVP2を細胞表面 にトラップさせる,(2)細胞外に分泌させる,(3)第二のウイルス粒子構造蛋白VP3とともに同時発現させる(VP2/VP3),(4)蛋白翻訳コドンをウイルス型から鶏型に変換するなどが検討されたが,ワクチン効果 を高めることはできなかった.類似のことはオーエスキー病ウイルスでもいえる.病原体が同じヘルペスウイルス科に属すマレック病では,感染防御抗原(糖蛋白gB)をポックスウイルスベクターで発現させれば腫瘍を防ぐ有効なワクチンができる.しかし,オーエスキー病ウイルスのgBをウイルスベクターで発現させても防御効果 は低い.このように,高い効果を持つワクチン開発には挿入遺伝子についての検討が欠かせない. 一方,組み換え生ワクチンの効果は使用するウイルスベクターの特性に大きく依存するため,ウイルスベクターの改良は最も重要な研究課題である.また,感染症ごとに防御に必要な免疫の種類やレベルが異なることは,各感染症ごとに防御免疫の分析とその免疫の選択的誘導法の開発が必要なことを意味している. 以下の項では組み換え生ワクチンの中でも研究が最も進んでいる鶏のウイルスベクターワクチンを中心に,世界における家畜用組み換え生ワクチンの開発の現状をかいつまんで紹介しよう.
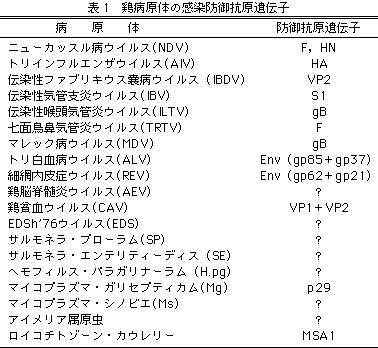
|