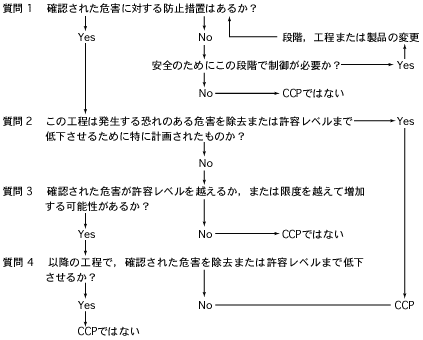| 以上の手順で作成された危害リストの発生要因の項をみることにより,その危害をHACCPシステムすなわちCCPとして管理すべきか,または一般的衛生管理プログラムで管理すべきかが判断でき,防止措置欄に示された具体的な数値は管理基準を決定するための根拠になる.したがって,危害分析はHACCPシステムの導入においても最も重要な手順であり,十分かつ適切な危害分析が衛生管理の適否のカギになる[5]. 3)衛生管理計画(HACCPプラン)の作成 ガイドラインの手順7〜12,すなわち原則2〜7に従ってCCPを設定し,設定されたCCPについて,制御対象となる危害,発生要因,防止措置,管理基準,モニタリング方法,改善措置,検証方法,記録文書名を一覧表にしたHACCPプランを完成させる.プランは,食品の種類,製造加工工程,施設ごとに作成する. (1) フローダイヤグラムに沿ってCCPを設定[手順7:原則2] 確認された危害が,いずれの工程で制御できるか,すなわちいずれの工程がCCPになるかを判断する.CCPとは「食品の安全性に関わる危害の発生の防止,除去または許容レベルにまで低下させることのできる管理対象となる場所,工程または措置」と定義付けられており[1],そのための連続的または相当な頻度のモニタリングを必要とする.まず確認された危害が一般的衛生管理プログラムで解決できないことを確認し,次いで食品の取り扱いに直接関係し,その管理に不備があった場合に最終製品の安全性が確保されない恐れが生じる場合にのみCCPと設定する.その判断は,図2に示した4つの質問からなる判断手順を適用すると容易である.
|