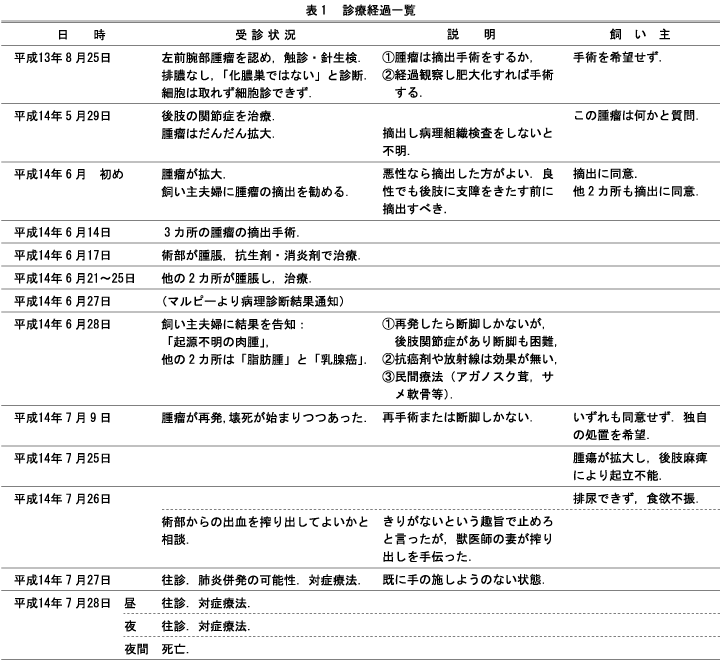![]()
|
判例に学ぶ〜愛犬の手術とインフォームド・コンセント
岩上悦子†,勝又純俊,押田茂實(日本大学大学院医学研究科) 1 は じ め に 1 は じ め に平成17年12月のペットフード工業会ニュースによると,平成17年度全国犬猫飼育率調査の結果,犬の飼育頭数は1,306万8千頭(前年度:1,245万7千頭),猫は1,209万7千頭(同:1,163万6千頭)であった.動物は家族の一員として室内で飼育されるケースが増え,9割以上の飼い主がペットの健康に配慮している(同調査より)ことから,わずかな異変でも早期発見・早期対応がなされ,その寿命が延び,高齢化に伴う疾病も増えている[5].家庭で飼育する動物に対する愛情が深い一方で,不幸にも動物を亡くした際の飼い主の悲しみは大きく,最期に動物病院で診療を受けていた場合には,その思いの矛先が獣医師に向き,損害賠償請求訴訟にまで発展することもある.われわれが渉猟した獣医療訴訟判例は16件であるが(平成18年10月現在),最近臨床獣医師にとって重大な意味を持つと思われる民事判決が機関誌に掲載されたので報告する[2]. 愛犬の手術がインフォームド・コンセントなしで行われた後,愛犬が死亡し精神的損害を受けたとして,石川県の夫婦が動物病院に約350万円の損害賠償金などを求めた訴訟である.この訴訟の控訴審判決が,平成17年5月30日に名古屋高裁金沢支部であった.この判決では,請求を棄却して飼い主側(原告)敗訴とした一審の金沢地裁小松支部判決(平成15年11月20日)を変更し,病院側に42万円の支払いを命じた.この判決はマスコミに取り上げられ(共同通信:平成17年5月30日付,読売新聞:同31日付),関心のある臨床医も多いと思われるのでその概略を紹介する.なお,この判決文は裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp/)より入手が可能である. |
| 2 事案の概要と診療経過 名古屋高裁金沢支部の判決によると,診療経過の概略は以下のとおりである(表1).原告らは患犬(ゴールデン・レトリーバー,雌,平成元年2月9日生)の飼い主夫婦であり,被告は平成11年3月ころから原告らがかかりつけとしているC病院を経営している獣医師Aと,同病院で診療補助をしているAの妻Bである. 獣医師Aは平成13年8月25日,飼い主が本件犬を連れて来院した際,左前腕部に本件腫瘤があるのを認めた.触診と針生検を実施したところ,膿等の液体が出てくることがなかったことから,「化膿巣ではない」と診断した.この針生検ではほとんど細胞が取れず,腫瘤の悪性・良性の別は判断できなかったが,針パンチ生検をするには全身麻酔をかける必要があり,そうであれば腫瘤を全部摘出した方がよいとAは考えていたため,これを実施しなかった.また,悪性・良性のいずれであってもその治療方法としては手術により腫瘤を摘出するしかないと考えていたため,その旨を飼い主に説明した上,《1》直ちに手術を希望するのであれば手術する,《2》直ちに手術を希望しないのであれば経過観察するほかないが,腫瘤が肥大化するのであれば,手術をした方がよい旨を伝えた.これに対し飼い主らは,以前この犬に行った腫瘤の手術の予後が思わしくなく,すでに相当の老犬であったことから,よほどのことがないかぎり手術は受けさせたくないと考え手術を希望しなかった.その後も,本件犬は後肢の関節症治療等のため何回かC病院に来院しており,平成14年5月29日に来院した際,次第に大きくなっていた腫瘤が何であるかの質問を飼い主らから受けたが,この時もAは,腫瘤を摘出した上で病理組織検査をしなければわからない旨説明しただけであった. 6月初めころ,腫瘤が大きくなってきたことからAはその摘出手術を勧めた.その際,腫瘤が悪性のものであれば摘出した方がよく,良性のものであったとしても,次第に大きくなってきているので,後肢の悪い本件犬の歩行に支障をきたす前に摘出した方がよい旨を説明した.さらに飼い主夫妻同席の上で再度,同様の説明をして腫瘤の摘出手術を勧めたところ,飼い主らは本件腫瘤の摘出手術に同意し,他2カ所にあった別の腫瘤の摘出手術についても合わせて同意した. そこでAは6月14日に前記3カ所の腫瘤摘出手術を行った.本件腫瘤の摘出に際しては,その部位ではこれを根こそぎ取ることが不可能であったため,他の機能を損なわない範囲で最大限の切除を行った.もともと本件腫瘤が悪性のものか良性のものかにかかわらず,同一範囲について切除するとの治療方針をAは有しており,実際に行った切除範囲もその治療方針に沿ったものであった. 6月27日,3カ所の腫瘤の病理組織検査を依頼したマルピー・ライフテック株式会社臨床検査センターによる病理組織診断は次のとおりであった.「本件腫瘤は,起原不明の肉腫である.(中略)標本上では腫瘍細胞が脈管へ浸潤する像は認められなかったが,標本の断端部にも腫瘍細胞がみられた.(中略)脈行性の遠隔転移よりは局所の破壊浸潤性増殖に対する注意が必要である.再発した場合には早期に広範囲な再切除を行うことが重要である」.また他の2カ所にあった腫瘤は「脂肪腫と乳腺癌」であった. そこでAは,翌28日に飼い主らに対し前記病理組織検査の結果を伝えた上,《1》本件腫瘤が悪性の腫瘍であるため再発の可能性が高く,再発した場合は断脚するしかないが,本件犬には後肢に関節症があるため断脚も難しいかもしれない旨説明し,また,《2》他の治療方法として抗がん剤投与や放射線治療はあるが,前者はまず効果がなく,後者もやはり効果がないと思う旨説明した.他方,他に治療方法がないことから,気休めかもしれないと告げた上,アガリクス茸やサメ軟骨等の民間療法がある旨説明した. その後,術部の治療のほか,後肢の関節症の治療も継続して行っていたところ,7月9日以降,術部が腫脹して腫瘤が再発し,壊死が始まったことから,その治療方法としては再手術または断脚しかないと考え,その旨飼い主らに説明した.ところが飼い主らは,再手術,断脚のいずれにも同意することはなく,Aに対し「術部に対する独自の処置を行っても大丈夫か」と質問し,「人間に使っても大丈夫なものなら多分大丈夫だと思うが,自己責任でやるように」とAが回答したこともあって,以後,術部の処置は飼い主らが独自に行うようになり,Aが術部に対する治療を行うことはなかった. 以降の経過は次のとおりであった.7月25日,腫瘍が大きくなり,後肢麻痺により起立不能となった.翌26日には排尿できず,食欲もあまりない状態となった.そこで飼い主らは犬を連れてC病院を受診し,術部からの出血により腫瘍が小さくなったような気がしたことから,このまま悪い血が出て腫れが引いてくれないかと思い,絞り出してもよいものかを診療補助をしているAの妻Bに尋ねた.これに協力しようとしたBは,Aからきりがないという趣旨で止めろと言われたもののそれ以上の反対がなかったこともあって,飼い主に協力して術部を絞り出した. Aは翌27日,28日の昼ころ及び同日夜間の3回,飼い主らの依頼によりそれぞれ往診したが,犬は肺炎を併発した可能性があり,死期も迫っているため,症状緩和のための対症療法を行うことしかできず,すでに手の施しようのない状態であった.そして,本件犬は7月28日夜間,13歳5カ月で死亡した. このようなC病院の診療に対し飼い主らは,獣医師らには説明義務違反があり,また,獣医師の資格を有しない妻Bが治療方針の決定に主導的な役割を果たしたとして,債務不履行または不法行為に基づき,治療費18万余円,抗がん剤等購入費11万余円,慰謝料300万円,弁護士費用20万円,合計350万余円の損害賠償金の連帯支払を求めた.一審の金沢地裁小松支部は,獣医師らに説明義務違反はなかったとして飼い主らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする飼い主らが治療義務違反を新たに主張し本件控訴を提起した. |