![]()
| 4 センターの特色 本センターの目的は,「食の安全と安心」を「Farm to Table」に象徴される農場から食卓まで一貫して教育し研究を行うところにある.特に,その中にあって産業動物臨床をセンター内に部門として組み込み,今までのような生産者への貢献に止まらず流通と消費にまで視点を広げて,産業動物臨床が動物の疾病制御を行うこととしたところに大きな特色を本センターは有する.毎日食べている「食」が,健康にとって安全であるためには「食」の生産現場から口に入る(食卓)までの過程が病原微生物学的あるいは物理化学的に厳密に監視されていることが必要である.その過程を大きく分けると以下の三つの分野, 一つは,安全な飼料が供給され,快適な環境のもとで家畜を生産する畜産分野, 二つは,家畜を常に健康に維持する臨床分野, 三つは,食品が加工され食卓に上がるまでを監視する公衆衛生分野 であり,いままではそれぞれが専門に分化されてあった.そのような専門分化の姿は,大学の教育研究分野だけでなく,行政分野においても,さらには社会一般の常識においても分野別に独立して行われることが当然と考えられ,またそれが最も効率的であるとされてきていた.しかし,それぞれの分野が高度に専門分化され,かつ社会構造が複雑になってくるにつれて各専門分野は孤立化を深め,社会で生じた諸問題を各分野のみで解決できることが極端に少なくなってきた.そのような専門分野の孤立化によって発生した典型例がBSEといえる.BSEは,生体の廃棄物である骨を同一種動物の牛に供給したために発生した病気であり,臨床分野との連携のないままに単に生産性を追い求めることによって発生した典型例である.この一つの事例からでもわかるように,一つの分野だけでは問題が解決できなくなってきている状況にあった.その反省点に立って,本センターは,図にみられるような畜産物の家畜・家禽の生産農場から,乳・肉・卵が食品として最後の食卓に上がるまでの一連の過程のすべてを管理できる教育と研究システムであり,これが本センターの特色である.ただ,これを実現するには簡単なことではなく,相当の期間を要すると考える.特にそれを実現するには,異なった分野にたずさわっている人達が交流し,異なった専門分野を理解し合い,おたがいに連携を図っていく意識改革から始まると考える. |
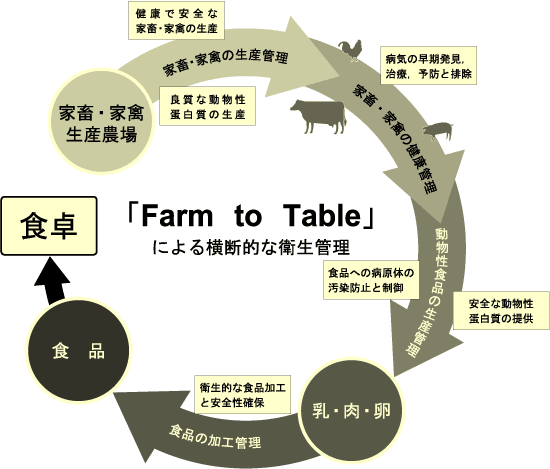
図 動物医学食品安全教育研究センターの特色
| 5 センターの組織 本センターは,その組織を4部門とした.「動物生産科学部門」(畜産)は家畜の生産に関する教育研究を主体に,「食料生産動物医学部門」(臨床)は動物の病気の予防や診断治療に関することを主体に,そして「食品安全科学部門」(公衆衛生)は畜産物の安全管理に関することを主体に,さらにそれらを調整する中心的な役割として,「企画調整部門」は研究プロジェクトや教育プログラムの企画を主体に,分野横断的な教育研究を推進することとした.現在は,各部門ごとに動物科学講座と獣医学科の教員が中心となって各部門7〜9名が兼任してセンターを運営している. |
| 6 これからの産業動物獣医師の役割 本センターを活用しながら,新しい産業動物獣医師をめざして今後の活動を考えるとき,その任務としては以下の4つがあげられる. 第1番目は,“生産者への支援”である.これは動物の疾病の治療や診断予防を通じて,生産者をバックアップするものであり,今までもなされてきたものであり,今後も産業動物獣医師の根幹をなすものである. 第2番目は,消費者の視点に立った“安全な畜産物供給への支援”である.現在問題とされているポジティブリスト制を取り上げても,産業動物獣医師は本センターを通じて今まで以上に他分野との連携を図って,生産された畜産物をチェックし安全な畜産物を供給して行かねばならない. 第3番目は,“動物福祉への配慮”である.動物福祉については日本ではまだ緒についたばかりではあるが,この問題はヨーロッパでは産業動物(食料生産動物)ではあってもその適正な飼養環境が確保されていなければ,動物が飼えないとする法律が制定されてきている.この問題は,動物側に立った適切な飼養環境を獣医師自らが,たとえ生産者と対立することがあっても指導して行く必要がある. 第4番目は,“地域環境への貢献”があげられる.それは,糞尿処理問題を基本として大型化した畜産形態は常に周囲の環境を汚染する可能性が考えられる.そのために産業動物獣医師はその問題について常に指導性を発揮できる力を持つことである.現在,日本においても糞尿処理への対策は少しずつ講じられつつあるが,生産者と直接接している臨床獣医師や家畜保健衛生所獣医師にその適切な指導が求められてきている.以上,これからの産業動物獣医師は上記の仕事が遂行でき指導性を発揮できることが,生産者はもちろんのこと消費者からも強く求められてくるものと考えられる. |
| 7 お わ り に 本センターは,産業動物獣医師が上記の仕事を遂行するための支援機関として設立されたものであり,学生に対する教育機関であるととともに卒業後の研修センターとしての機能も兼ねたものである.そこでは,臨床獣医師あるいは家畜保健衛生所や食肉検査所の獣医師が短期間あるいは長期間派遣され,そこでそれぞれの教育プログラムに従って研修を受けるとともに教育に対しても一部携わってもらうような組織として構築する,新しい教育研究システムである.本センターで一定の研修を修了した者は,その成果をセンター内スタッフや獣医師会との合同の協議によって評価し,受講証書や認定証書を交付する.そのような制度が長年,実施されて実績を重ねて行くことによって社会からの制度の認知がなされてくるものと確信する.その背景には,生産者は技術と指導性が高い獣医師を自らが選択する時代が来ると予想されるからであり,同時に消費者からは畜産物の安全性を一貫して指導できる獣医師への期待が今まで以上に高まることが想定されるからである. これからの産業動物獣医師は日々の診療あるいは予防業務で培った広い知識と人間性をもって地域のリーダーとして,力を発揮して行くことがますます求められてくる時代となってきた.「食」に関わる獣医師を支援する本センターのような組織が,地域特性を活かして他大学にも設置されることを願っている. |
| 参 考 図 書 | |||
|
| † 連絡責任者: | 内藤善久 (岩手大学農学部附属動物医学食品安全教育研究センター) 〒020-8550 盛岡市上田3-18-8 TEL 019-621-6103 FAX 019-621-6107 |