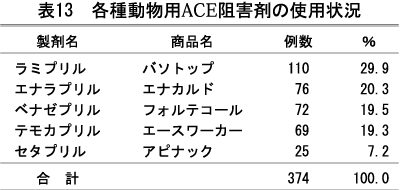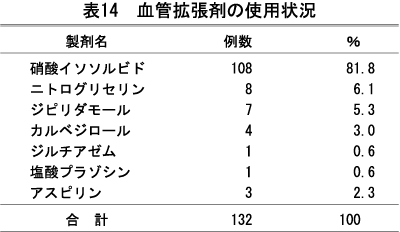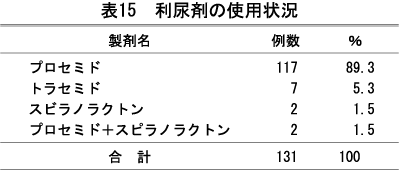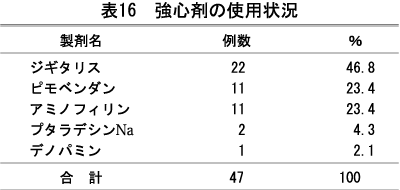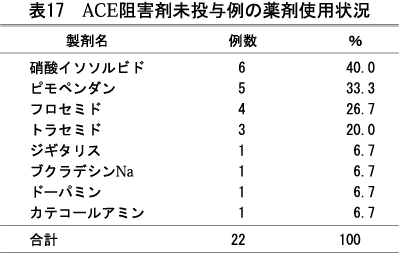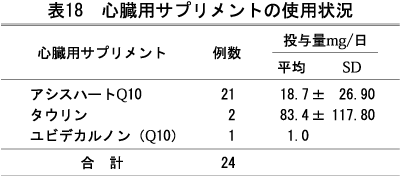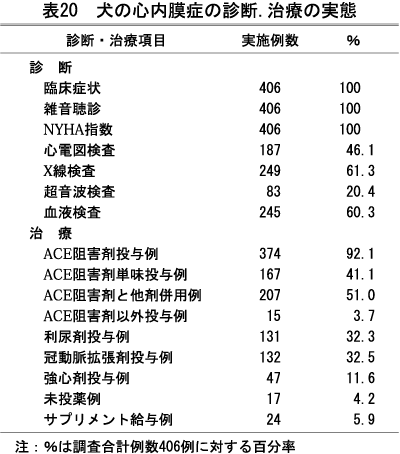![]()
|
| 10 ACE阻害剤使用の実態(表13) 各種ACE阻害剤の使用状況は,表13に示した.374例中で最も多用されていたのがラミプリルで29.9%であった.ついで,エナラプリル,ベナゼプリル,テモカプリルが20.3%,19.5%及び19.3%でほぼ同等であった.そして,最後に市場に出たセタプリルが最も少なく7.2%であった.
|
|||
11 血管拡張剤使用の実態(表14) 血管拡張剤の使用状況は,表14に示した. 血管拡張剤を使用した132例中108例(81.8%)が硝酸イソソルビトであった.その次は,ニトログリセリンとジピリダモールであった.
|
|||
12 利尿剤使用の実態(表15) 利尿剤の使用状況は,表15に示した. 心内膜症の心不全から二次的に起こる肺水腫コントロールのため,利尿剤は多用される.最も多く使用されているのは,プロセミドに次いでトラセミドで,この両者は作用機序が同じループ系利尿剤なので,両者をあわせると94.6%に利尿剤が併用されていた.
|
|||
13 強心剤使用の実態(表16) 強心剤の使用状況は,表16に示した. 強心剤としては,古くから使用されているジギタリス(ジゴキシン)が22例,ピモベンダンとアミノフィリンが11例使用されていた.
|
|||
14 ACE阻害剤未使用例の他剤使用状況(表17) 他剤使用状況は,表17に示した. 例数的には多くないが,ACE阻害剤を使用せず,冠動脈拡張剤(硝酸イソソルビド),心不全治療剤(ピモペンダン),利尿剤(フロセミド,トラセミド)などが少数例に使用されていた.
|
|||
15 心臓用サプリメント使用の実態(表18) 動物用サプリメントも非常に多くなってきたが,心臓用サプリメントはまだ非常に少なく,使用されている多くはアシスハートQ10で,これは心臓エキス,タウリン,ユビデカルノン(Q10)の複合剤であるためと思われる.
|
|||
16 治療剤による心不全改善状態(表19) 心不全の改善状態は,表19に示した. 収集した406例から,判定不能39例と死亡例29例を除いた338例の改善度から改善率を算出すると83.3%となり,ACE阻害剤の有効率と報告されている数値とほぼ同率のものであった. すなわち,心内膜症に関して現在の小動物医療では,投与例の約8割に治療による何らかの改善効果がみられた. |
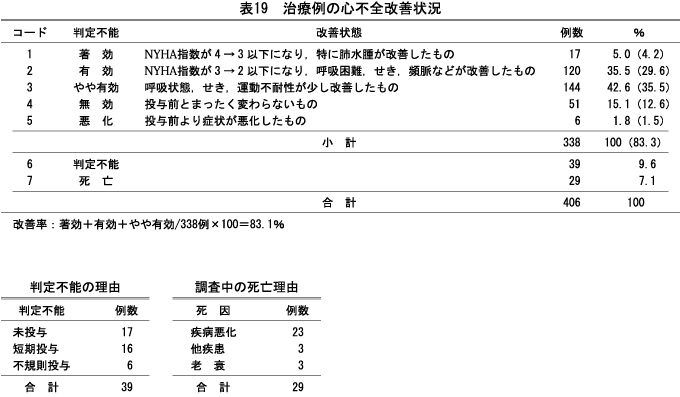
IV 総 括
以上の調査結果から,現時点の心内膜症の診断・治療に関しては,かなり適確な医療が行われていると判定された.
|