![]()
|
牛海綿状脳症の新しい知見を求めて
古好秀男 † (岡山県農林漁業担い手育成財団 ・ 岡山県獣医師会会員)
|
| 2 家畜法定伝染病防圧の経験からの検証 先ず,1967年から1974年にかけて遭遇した炭疽の事例では,120頭の黒毛和牛の繁殖肥育一貫経営牧場で,7日前に死亡していた5頭の牛を掘削機械を使って穴を掘り3mの深さに埋め,8日目に2頭が続発して死亡したことから畜主が不審に思い家畜保健衛生所に届け出があった. 畜主からの稟告を聞いた時点で炭疽を疑い,死亡牛の天然口出血,脾臓肥大,血液凝固不全,莢膜染色等について病性鑑定を実施したが,当時,牛の炭疽を診断した経験者がいないため,炭疽と診断を下すとなると脾臓肥大陽性,莢膜染色陽性だけでは不安であった. 一方,採材した病性鑑定材料を用いてのアスコリー反応,パールテスト,マウス感染試験等の検査結果を待っていたのでは,手遅れになることから,脾臓肥大陽性と莢膜染色陽性を頼りに,炭疽の疑陽性患畜発生として防疫対策本部を設置して,畜主や地域の畜産農家と関係者に理解を求め,防疫班を組織して,周辺農家の牛の検温を行い体温上昇傾向のある牛には抗生物質を投与し,健康な牛には炭疽弱毒ワクチンを接種し不眠不休で防圧に徹した.4日目に最終病性鑑定結果で炭疽と診断されたので,畜主が埋却していた5頭の牛を掘り出し4日間かけて焼却した苦い経験がある.また,乳牛の事例では,畜主から前日に2頭死亡し,また今日1頭が死亡したと家畜保健衛生所に届け出があった.電話で畜主からの状況を聞いているうちに,以前の経験から炭疽の疑いがあると直感し,現場で脾臓肥大陽性,莢膜染色陽性の最小限の検査確認を済ませた内容から,同時に前日と当日の生乳を集配送しているタンクローリー及び乳業メーカーの貯留タンクの合乳が一般に出回っていないことを確認したうえで生乳の取り扱いを規制した.病性鑑定の判定結果までに3日間かかり,また,炭疽と診断されていない段階で,畜主,集配送タンクローリー,乳業メーカーとの話し合いは難航し,もし炭疽でなかったらどの様な責任を取るのかと厳しく詰め寄られ,緊迫感は相当なものであった. 検査の結果,炭疽と診断されたが,毅然とした態度で的確な判断の元に早期対応をしたことが,防圧に繋がったと考える. また,酪大で2000年から2004年の5年間にジャージー種の搾乳牛にヨーネ病が大量発生して66頭の殺処分を行った経験がある. 大量発生の原因について検証してみると,当初,1995年から1997年の3年間には,年間3頭から4頭程度の疑似患畜の発生があった.家畜保健衛生所に依頼して4カ月ごとに自衛検査による再検査を実施して経過観察をしていた.その結果,年間2頭程度のヨーネ病の陽性牛を殺処分した.その後,酪大の校長として2000年にふたたび赴任して驚いたことに1998年,1999年の2年間,ヨーネ病が多発状態となり,一年間に平均13頭もの陽性牛が続発した.最初は死亡していた牛を校内の牧場地に埋却したが,2000年から死亡牛は,総て焼却処分に切り替えるとともに,本格的な防圧に勤めた.エライザー法,糞便検査,抗体検査のいずれかの反応があった総ての牛を殺処分の対象として決断して以来,5年間で66頭の大量発生となった.疑似患畜をどうにかして陰性に転じないものかと,緩慢に思う弱気な考え方と発生の少ない段階で厳しい防圧対応に踏み切らなかった事が,3年後に大量発生となって被害を大きくしたものと思われる.家畜法定伝染病の防圧対応の私の経験から,解明途中のBSEの問題点の解明に向けて検証してみたい. |
| 3 20カ月令と21カ月令の判断の境 世界のBSEの検査基準は,日本が21カ月令以上,EUが30カ月令以上,米国がリスク牛の一部が対象とされている.日本で2006年7月の現在までに27頭を検出している.BSEについては,未解明な部分があまりにも多い.英国では,1996年までに70万頭のBSE陽性牛を食用に提供されたのではないかと推測されているにも関わらず,感染者が157人と少ない発症であること,BSEの感染実験で15頭中1頭しか感染症状がなかったこと,日本でも同じ牛舎で同じ飼料を給餌していたにも拘わらず発症は1頭のみで2頭以上の続発を見ていないこと,肉骨粉由来の給餌が原因であるといわれながらも,国内で2003年の初発から3年が経過して,ようやく2006年2月9日に国内で22頭目にBSEと診断された5歳7カ月令の牛が生後71日目(3カ月)から9カ月令頃までの約6カ月の間に牛由来の肉骨粉のミートボールミールや血粉などの原料で作った飼料を子牛の段階で給餌していたことが感染源であると初めて確認したことは,感染経路の実態解明に大きく前進したと思われる.通常,牛の体内のどの部位に正常プリオン蛋白質が存在しているのか神経細胞との関係を含めて未解明であること等,「種の壁」を含め同種の感染の中でも説明のつかない未解明の部分が多い中で,科学的研究の新しい決定的な知見の発表が立ち遅れていることもあって,防圧に伴う的確な対応が進んでいないことは確かである.日本では20カ月令未満の牛は,BSEは検査対象外として食用に提供されることに同意しているが,現在,BSEに対する検査能力は21カ月令が最短月令である.このことから仮に20カ月令未満のBSEの陽性牛がいたとしても,検査能力が確立されていない現実では検出をすることができないことを認識をしなければならない. 牛が肉骨粉を介して異常プリオン蛋白質を摂取した時点から,その牛は,BSEの異常プリオン蛋白質の保有畜であることはもちろんのこと,異常プリオン蛋白質の増殖蓄積期間であり発症するまでは潜伏期として不顕性感染していることは確かで,事実上疑似患畜となっているにも関わらず20カ月令未満の牛では,牛体内の異常プリオン蛋白質の増殖蓄積量では検査をする月令に到達していないからといって,科学的な根拠もないままにその牛を健康畜と判断して食用に提供することは極めて危険であると考える. さらに検証をするならば,BSEに感染して体内の正常プリオン蛋白質が異常プリオン蛋白質に自発的に変換され増殖蓄積していて,何時検査をしても陽性反応がでる状態で20カ月と30日を経過しており,あと1日で21カ月令になる牛がいたとしても,その牛が21カ月令未満であるために1日の違いで検査対象から除外されて健康畜として無検査で食用に提供されることは,到底許される話ではない.畜産農家によっても飼料給餌の種類や月令に合わせて農家が一律に同じ飼料を給餌することはないので異常プリオン蛋白質が何時どのようにして飼料に混入して給餌したか判らない状態であるため,月令を基準に判定することは正確な判断とはいえない. むしろ,何時感染しどれだけの月日が経過し正常プリオン蛋白質が異常プリオン蛋白質に自発的に変換されて蓄積しているかが問題であるので,現在検査機関に検査能力がある21カ月令以上の牛を食用対象牛として厳格に全頭検査を行いBSEの陰性牛のみ食用に提供する考え方が基本で有るべきではないのか. そもそも20カ月令からいきなり21カ月令に成長することはできない.正確に表現するならば生後21カ月令を基準にして,21カ月令未満ならびに21カ月令以上と表現をしなければならない.試験研究機関で感染実験を行う場合,異常プリオン蛋白質を投与した月令がはっきり判明しているが,一般的な畜産農家においては約60%以上を購入飼料に頼っている実態からして,知らない間に異常プリオン蛋白質が飼料に混入して牛が食べたのか判らないのが現実で,感染後何カ月令と計算して表現できる状態ではない.日本では,英国に一日(一泊)以上滞在した経歴のある人からは血液を介して変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に感染する恐れがあるとの指摘から献血ができないことにされている. BSEは生後1年以内に感染するといわれている. EUのBSEのマウス感染実験では,異常プリオン蛋白質を投与して感染後6カ月目で回腸遠位部に感染性が見られている.子牛では10カ月目に扁桃で病理学的に感染が確認されていることからして,月令よりむしろ感染時点からの異常プリオン蛋白質の蓄積状態が問題である.牛の体内では現行の21カ月令といわず感染後の早い時期から異常プリオン蛋白質の自発的変換を繰り返し増殖蓄積が進行していることを想定し最も重要視して検討しなければならない.特に生後間もない子牛に対する人口哺乳による感染とBSEの陽性牛の肉骨粉が混入した飼料給餌によって育成牛,成牛が感染した場合との感染月令での異常プリオン蛋白質の増殖速度について,感染実験研究を積み重ねBSEの病原体感染被害のメカニズムの全容が解明されなければならない. |
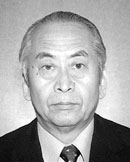 1 は じ め に
1 は じ め に