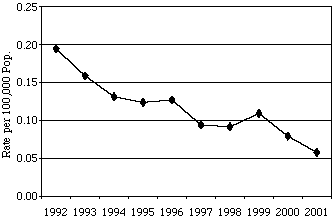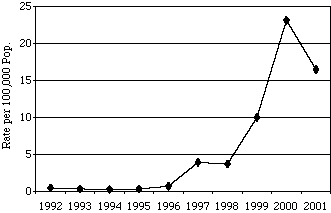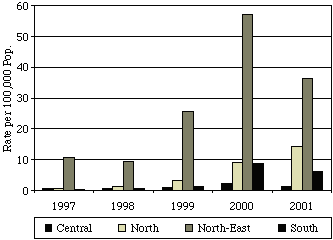![]()
|
タイ国における人と動物の共通感染症
―狂犬病,レプトスピラ症,つつが虫病など―
| 1 は じ め に タイ国(以下タイ)は東南アジアでも日本人に最もなじみのある国のひとつで,海外旅行された方の多くは一度は訪問しているのではないだろうか.タイは東南アジアでも経済発展の著しい国で,首都バンコクは600万をこえる人口を有し,高層ビルと近代的な設備や装飾にあふれている大都会である.高架鉄道は数年前から開通し,最近では走行距離が短いものの地下鉄も開通している.この国も他のアジア諸国と同様に1997年に経済危機に見舞われたが,数年間で回復したとされている.こうした状況の中で,現タイ首相は「わが国は被援助国から脱却し,これからは援助国となる」と述べている.しかし,国内での経済格差は著しく,バンコク市内でも地域によって住・生活環境は極端な差があり,雨のたびに洪水になる地域も多い.また,少なくなったとはいえ掘っ立て小屋のような住居も散在し,浮浪者も多い.バンコクと地方の格差はさらに大きく,バンコクでいわゆる貧民層といわれる地域の生活環境が地域での平均層の生活環境でないかとも思われるところも少なくない. ところで,日本からタイを訪れるに人々の多くは,これまでバンコクやタイの京都といわれるチェンマイあるいは外国人が多く集まるプーケットなどいわゆる観光地へでかけることが中心であった.こうした観光地は旅行者の受け入れ体制も整っており,下痢症などが問題になるものの食品管理も有る程度なされている比較的安全な施設を利用することができる.しかし,最近では自然志向やグルメブームということで,冒険的な旅行が増え,通常の観光では行かない奥地や辺境へ長期にでかけたり,土地の住民でも用心するようなイカモノ食いをする傾向が増えている.日本国内ではどんな地方へ行ってもそれなりに衛生設備が整っており生活環境も地方と都会で極端な違いはない.しかし,タイの僻地はバンコクのような都会とは施設・設備がまったく異なるため,思わぬ感染症に罹患することも想定される. タイには狂犬病をはじめ日本で克服されたような感染症も多い.さらに熱帯病であるマラリアやデング熱のような感染症もある.タイ保健省は感染症などの患者発生状況を年報の形で報告しているが,それをみると,不明熱などを含め感染症が推定される患者数は年間約200万名である.最も多いのが急性下痢症で患者数は約100万名となっているが,大多数が臨床診断による報告であり,起因病原体が特定されているものは少ない.そのため,デング熱,マラリア,狂犬病,レプトスピラ病のように診断法が確立され,それに基づいて報告される疾患とともに,年間20万から30万名の不明熱患者が報告されている. 筆者は国立感染症研究所退官後,国際協力事業団(現国際協力機構,JICA)タイ国立衛生研究所プロジェクトの専門家として2000年8月から3年半あまりタイに滞在したが,その間に入手した資料などを基にタイにおける人と動物の共通感染症(共通感染症),特に狂犬病,レプトスピラ病,つつが虫病を中心にその実態を紹介する(図は上述の年報より入手した). |
||||||
| 2 狂 犬 病 タイでまず驚くのは野犬の多さで,バンコク市内のいたるところに犬が我がもの顔に寝そべっている.地方でも同様で,寺院は犬の安息地なのか特に多い.この国の狂犬病の感染はいわゆる都市型で,犬が感染源となる.猫も狂犬病ウイルスを保有しているが,人の感染源となることは少ないようである.ちなみに猫から検出される狂犬病ウイルスは犬と同じであることから犬―猫間の感染があると推定されている.狂犬病ウイルスは野犬だけではなく飼い犬からも検出されている.後にも述べるが,検査対象とされた犬で狂犬病ウイルス陽性となる例の半数近くは飼い犬である. タイの狂犬病患者は十数年前までは年間200名以上であったといわれているが,漸次減少し1998年には57名となっている.1999年には68名とやや増加したものの,2000年は50名,2001年には37名と引き続き減少傾向にある.図1に最近10年間の人口10万人当たりの患者数の推移をしめした.一方,犬に咬まれた後のワクチンや免疫グロブリン接種,すなわち暴露後免疫の件数は年間20万ともいわれていることから,患者数の減少は暴露後の処置が効を奏しているものと考えられている.事実,狂犬病発生地域で行われた調査で,狂犬病ウイルスが確認された犬に暴露後ワクチンあるいは免疫グロブリン接種された188名には死亡例がなかったが,死亡した2名ではワクチン接種も免疫グロブリン接種もされていなかったことが明らかにされている.ところで,先にも述べたように2001年の狂犬病患者は37名であるが,バンコクが最も多い(8名).しかし,人口10万人に対する比率からみると,ミャンマーやカンボジア国境付近,南部など地方で多く発生する傾向にある. 犬における狂犬病ウイルス保有についてタイ赤十字が中心になって調査が行われているが,それによると1994年から1999年の間に検査対象となった犬の平均39%がウイルス陽性である.また,その多くは1年以下の幼犬で,しかもほとんどワクチンの接種をうけていないことが明らかにされている.同様な実態はその後も続いており,前述の2001年の保健省患者年報でも,検査対象となった犬のおよそ32%は狂犬病ウイルス陽性であることが明らかにされている. ところで,滞在中にバンコク市内の公園で1匹の犬が50名以上の人を咬んだという新聞報道があったが,おそらく発症した犬によるものと思われる.こうした状況の中で政府は飼い犬へのワクチン接種のキャンペーンを行うとともに,野犬の対策に努力しているようであるが,避妊手術や予防注射接種をするのも数が膨大であるため費用がかかることや,野犬の捕獲に対する動物愛護者からのクレームなどでなかなか進まないようである.もっとも,APECが開催された際には,政府は事前にバンコク市内の犬を一斉に捕獲し,一箇所に集めたため,野犬の数は激減し,市内には地域住民から飼い犬とみられるように首輪をされた犬だけが残っていた.しかし,その後野犬はまた増えつつある. このように,狂犬病ウイルス陽性の犬はバンコク市内ではもちろんのこと,地方によっては検査例の半数以上に及ぶことから,犬には近づかないこと,犬に引っ掻かれたり,噛まれた場合はたとえ飼い犬であってもワクチン接種証明がないかぎり病院で速やかに処置を受ける事が重要である. |
||||||
|
||||||
| 3 レプトスピラ症 レプトスピラ症患者はタイでもっとも注目されている疾患の一つである.本病は1942年に初めて報告されているが,1988年から1995年まで年間の患者数は100〜200名程度で注目されるほどの疾患ではなかった.しかし1996年には400名近くに達し,1997年には一挙に2,300名を超える発生となった.翌1998年はやや減少したものの,1999年にはおよそ6,000名となり,さらに2000年には患者発生数が14,000名を超えた.2001年は患者数が8,600名とやや減少したが,洪水の多かった南部地方ではこの年に逆に患者が増加している.最近10年間のレプトスピラ患者数を図2に示したが,ここ数年間の患者発生は驚異的である.また,死亡者も1995年までは年間数名程度であったが,2000年には360名に達している.2001年は患者発生の減少により死亡者も135名と減少しているが,レプトスピラ症は依然として重要な疾患である.患者の発生はほぼ全国でみられるが,図3に示すように70%近くは北東部地方に集中している.なお,患者は圧倒的に男性が多く,職業別では農業従事者が8割近くを占めている.患者の発生は雨季に増加するが,7〜10月に集中する.この時期は米の収穫期であることから,田に入る機会が多くなる.そのため,穀物を食べに来た野ネズミなどの感染動物の尿あるいは尿に汚染された水に接触する機会が増えることによると思われる.感染源動物として前に述べたように野ネズミが最も疑われているが,豚,牛,犬などからも病原体が検出されている.バッファロー,豚,羊,犬も抗体を保有している.特にバッファローは水田の耕作に使われることから感染源として重要と考えられている.一方,感染動物の尿で汚染された水は洪水とともに広がることから,洪水が発生するとレプトスピラの汚染地域は拡大する.したがって,川や池などの水はもちろんでのこと,洪水にも十分な注意が必要である.ご存じのように2000年にマレーシアで行われたエコスポーツに参加した世界各地の選手が感染したが,日本からの参加者も感染している.日本ではレプトスピラ症は少なくなっているが,タイのみならず東南アジアでは注意しなければならない疾患である. ところで,本症の予防にはワクチンが有効であるが,流行している血清型と一致しないと効果がない.レプトスピラには多数の血清型があり,地域によって流行する血清型は異なるとされる.日本ではワクチンが作られているが国内で流行している血清型に対するもので,タイにはまだワクチンはない.帰国前に日本のワクチンでどれだけカバーできるか調査する予定であったが,日本からのワクチンの入手が間に合わず,実行できなかった.タイでは裸足で川や池に入る場合はレプトスピラ感染に注意しなければならない.
|