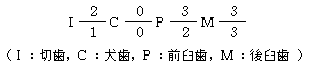![]()
|
エキゾチックアニマルの生物学(V|||)
― ウサギの診療の基礎(2)―
| (前号からのつづき) ウサギ(アナウサギ)Oryctolagus cuniculus は,ウサギ目Lagomorphaに属し,動物の系統分類上,食肉目Carnivoraに属する犬や猫とは目(order)のレベルで異なっている[2, 7].そのため,ウサギの診療に際しては,犬あるいは猫に対するのとは異なる対応が必要なことが多い[8].今回は,ウサギの診療の基礎として,麻酔法と鎮痛法について略述し,さらに代表的な疾病について簡単に述べることにする. |
|||
| 8 麻 酔 法 ウサギに麻酔を施すにあたっては,基本的な方法は犬,猫の場合と同様である[3].ただし,ウサギ用の麻酔薬あるいは鎮静薬等の製剤が開発されているわけではないため,用いる製剤は犬用や猫用の製剤や人体薬とならざるをえない[8].したがって,ウサギの麻酔では,使用する製剤がすべて効能外の使用となることを常に念頭におき,犬,猫の場合以上に細心の注意を払うべきである. (1)麻酔前投薬 ウサギはストレス状態に陥りやすく,それにともなって,麻酔薬投与に際して副作用が認められることが少なくない.こうした麻酔薬の副作用の発現をできるかぎり減少させるため,麻酔前投薬を行うことが望ましい. 麻酔前投薬には,塩酸キシラジンや塩酸メデトミジンなどを使用する.塩酸キシラジンはキシラジンとして5mg/kg,塩酸メデトミジンはメデトミジンとして0.1〜0.5mg/kgの用量をそれぞれ筋肉内に注射する.また,塩酸ケタミンを麻酔前投薬として用いることもあり,この場合にはケタミンとして25〜50mg/kgの筋肉内注射が行われている. なお,ウサギに対しては,唾液や気道における分泌を抑制するための投薬は特に必要ないが,徐脈が認められるような場合には,コリン作働性効果遮断薬(副交感神経遮断薬)を投与することがある.ただし,ウサギの個体によってはアトロピンを分解する酵素を高活性で有しているといわれ,コリン作働性効果遮断薬として硫酸アトロピンを投与しても無効なことがあるとされている.仮にこうした酵素を有している個体であっても,1mg/kgを超えるような高用量の投与を行えば,効果を得ることはできるが,その際にも追加投薬が必要であり,副作用発現の危険性は否定できない.臨床上,それぞれのウサギについてアトロピン分解活性を示す酵素の存在を確認することは不可能に近いため,アトロピンを投与する際には0.05mg/kg程度の用量の投与を行い,経過を観察するのがよいだろう.あるいは,こうした問題を回避するために,アトロピンの代わりにグリコピレート0.01〜0.1mg/kgを投与することもある[9]. (2)注射による麻酔 ウサギに対して単一の麻酔薬を比較的高用量で投与すると,副作用が発現し,麻酔事故が発生する危険性が高まると考えられている[1].そのため,2種以上の複数の薬物を組み合わせて投与し,それぞれの薬物の投与量を減少させることが好ましいといえる. 麻酔薬の組み合わせとしては種々の方法があるが,たとえば,塩酸メデトミジンをメデトミジンとして0.25mg/kgの用量で前投薬し,5分ほど経過した後に塩酸ケタミンをケタミンとして15mg/kgの用量で投与する.あるいはこの2種の薬物を混合し,1回の投薬を行ってもよい. なお,注射による麻酔を行う場合であっても,マスクを装着するか,気管チューブを挿入するなどして気道を確保し,酸素吸入を行うことが望ましい. (3)吸入による麻酔 吸入麻酔薬としてはイソフルランまたはセボフルランを用いるのがよい.ただし,これらの麻酔薬を導入に使用すると,ウサギが無呼吸を起こすことがあるため,観察を十分に行うべきである. |
|||
| 9 鎮 痛 法 ウサギに疼痛をともなう処置を施す際には,鎮痛薬を投与することが望まれる. 鎮痛薬としては,非麻酔性鎮痛薬(オピオイド)に属する酒石酸ブトルファノールや塩酸ブプレノルフィン,あるいはプロピオン酸に属するケトプロフェンを使用する.投薬量はおおよその目安ではあるが,酒石酸ブトルファノールはブトルファノールとして0.1〜0.5mg/kg,塩酸ブプレノルフィンはブプレノルフィンとして0.05〜0.1mg/kg,ケトプロフェンは3mg/kg程度とし,いずれも筋肉内に注射する. |
|||
| 10 歯 牙 疾 患 (1)ウサギの歯の特徴 ウサギは,以下の歯式に示される数の歯を有する.
また,ウサギ類では,上顎の左右2本の切歯は横列せず,一方(I2)がもう一方(I1,大切歯)の後方に位置している.このような歯の特徴によってウサギ類は系統分類上,独立した目とされており,また,これがウサギ目のことを重歯目Duplidentataという理由でもある[5, 6]. (2)切歯の過剰伸長 ウサギの歯牙疾患としては,切歯(大切歯)などに過剰な伸長をみることが多い.齧歯目Rodentiaの動物と同様に,ウサギの歯も,その生涯にわたって伸長を続ける常生歯である.特に切歯は,1年間におよそ10cmも伸びるといわれている.ただし,上顎の切歯と下顎の切歯は相互に噛み合う位置にあり,したがって,正常な状態では,上下の切歯は摩滅し,過剰に伸長することはない.しかし,何らかの理由で上顎と下顎の噛み合わせが不良になると,切歯が摩滅せず,過長となることがある(図1). 切歯の過剰伸長が生ずる原因としては,種々の要因が考えられる.先天的な原因としては,遺伝的な噛み合わせの不良がある.特にある種の小型品種では,遺伝的に下顎が前方に突出しており,これにより不正咬合が生じるといわれている.また,著者は最近,ある特定のブリーダーによって生産されたジャパニーズ・ホワイトのウサギに高率に切歯の過剰伸長を認めており,遺伝的な要因の存在を想定している. 切歯が過剰に伸長すると,ウサギは採食や飲水を十分に行えなくなり,体重の減少や脱水を起こす.また,夜間に排泄される盲腸糞を摂取することもできなくなる.さらに流涎を示したり,グルーミングを良好に行えなくなることもある. 切歯の過剰伸長の場合,診断は,その外貌から容易に行うことが可能である.ただし,歯根等の状態を確認するためにも,X線検査を行うことが推奨される. 治療には,過長となっている部分を切断する.この際,カッター等で歯を切断すると,歯が縦方向に割れたりするため,歯科用のバーを用いるとよい(図2,3).歯髄は通常,正常な歯の長さの1/2程度までの部分に存在しているため,過長部分には存在しないはずである.したがって,この部分を切断しても歯髄が露出することはないと考えられる. しかし,こうした治療を行っても,歯が過剰に伸長する原因が改善されないかぎり,ふたたび過長となることは避けられない.このようなウサギについては,定期的な検査を行い,必要に応じて過長部分の切断を繰り返す必要がある.そのため,飼い主の負担の軽減を考え,抜歯を行う場合もある[5]. 抜歯後は,給与飼料の形状を再考し,細切して与えるなどの配慮が必要である.ウサギが十分に摂食しているか観察するとともに,高頻度に体重を測定するとよい.また,ウサギは切歯を用いてグルーミングを行っているため,切歯の抜歯後は,飼い主がブラッシングなどを丁寧に行う必要が生じる. (3)臼歯の過剰伸長 切歯に比べると頻度はやや低いようであるが,臼歯にも過剰伸長が発生する.これについても,遺伝的,後天的な種々の原因があると考えられている. 症状としては,採食量の低下とそれにともなう体重の減少,流涎などが認められる. 臼歯の過剰伸長は,切歯の場合と異なり,外観から容易に観察することはできない.診断に際しては,鎮静または麻酔処置を施したうえで,強制的に開口して歯を観察する.また,X線検査も有用な診断法である.切歯の過剰伸長が認められたウサギは,臼歯も過剰に伸長していることが多々あるため,切歯だけに限らず,臼歯まで十分に観察すべきである. 治療は,過長部分の切断を行う[5]. |
|||
|
|||
|