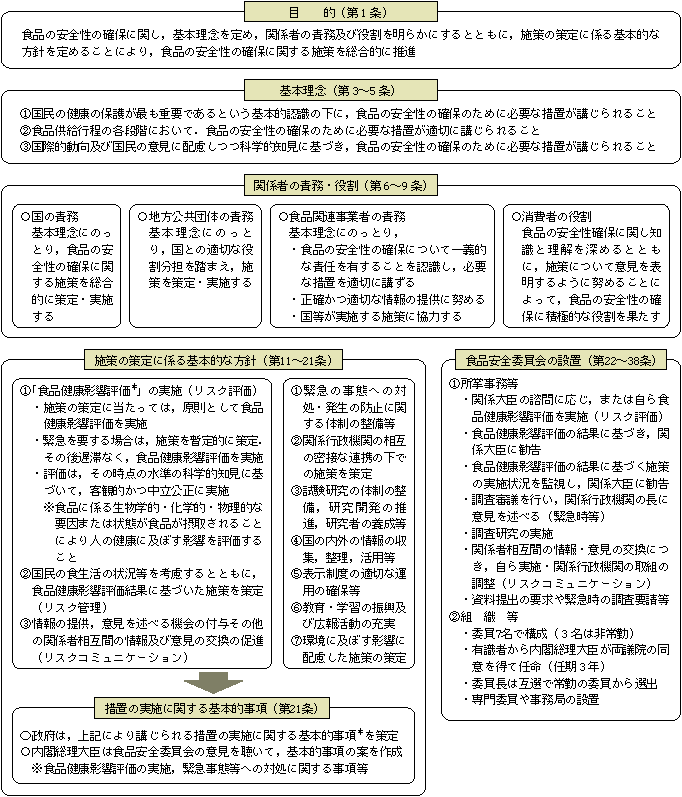![]()
|
食品安全と獣医師
杉浦勝明†(内閣府食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課長) |
 経済の発展に伴い,国民の食生活は豊かになった.世界各国から多種多様な食品が入手可能となり,世界中の食を享受できるようになった.一方,食品の生産から消費までの過程(フードチェーン)は,複雑化した.こうした中,牛海綿状脳症(BSE)の問題,輸入野菜での残留農薬の問題,国内における無登録農薬の使用等,食にかかわる事件,事故が相次ぎ,食の安全に対する不安や不信感が高まった.また,低い食料自給率や世界中からの食材の調達,新たな技術(遺伝子組換え,クローン等)の開発等,国民の食生活を取りまく状況は大きく変化している. 経済の発展に伴い,国民の食生活は豊かになった.世界各国から多種多様な食品が入手可能となり,世界中の食を享受できるようになった.一方,食品の生産から消費までの過程(フードチェーン)は,複雑化した.こうした中,牛海綿状脳症(BSE)の問題,輸入野菜での残留農薬の問題,国内における無登録農薬の使用等,食にかかわる事件,事故が相次ぎ,食の安全に対する不安や不信感が高まった.また,低い食料自給率や世界中からの食材の調達,新たな技術(遺伝子組換え,クローン等)の開発等,国民の食生活を取りまく状況は大きく変化している.一方,家畜衛生分野においては,豚コレラ等の急性感染症の防圧に伴い生産に慢性的に影響を与えるいわゆる生産疾病が顕在化するとともに,フードチェーンを通じた食品安全の確保との観点から,生産段階での食中毒菌の汚染防止,人と動物の共通感染症の防疫といった分野の比重が増している. こうした情勢に的確に対応するために,平成15年7月,国民の健康の保護が最も重要であるとの基本的認識の下,関係者の責務・役割,施策の策定にかかる基本的な方針,食品安全委員会の設置等を定めた食品安全基本法が制定されるとともに,食品衛生法等の関連法が改正された. ここでは,こうした近年の国民の食の安全への関心の高まりを背景とする新たな食品安全行政の展開の動きとその中で獣医師が果たすべき役割について論じてみたい. |
| 1 食品安全基本法の概要(図) 本法の目的は,「食品の安全性の確保に関し,基本理念を定め,関係者の責務及び役割を明らかにするとともに,施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより,食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進する(第1条)」ことである.基本理念として,第3〜5条に[1]国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に,食品の安全性確保のために必要な措置が講じられていること,[2]食品供給行程の各段階において,食品の安全性確保のために必要な措置が適切に講じられていること(フードチェーンを通じたリスク管理),[3]国際的動向及び国民の意見に配慮しつつ科学的知見に基づき,食品の安全性確保のために必要な措置が講じられることが謳われている. 関係者の責務・役割は,第6〜9条に明記されている.国の責務は,「食品の安全性確保に関する施策を総合的に策定・実施する」とされ,地方公共団体の責務は,「国との適切な役割分担を踏まえ,施策を策定・実施する」とされている.食品関係事業者の責務は,「食品の安全性確保について一義的な責任を有することを認識し,必要な措置を適切に講ずるとともに,正確かつ適切な情報の提供に努め,国等が実施する施策に協力する」とされている.消費者の役割は,「食品の安全性確保に関し知識と理解を深めるとともに,施策について意見を表明するように努めることによって,食品の安全性確保に積極的な役割を果たす」とされた. 施策の策定に係る基本的な方針は,第11〜21条に明記されている.「食品健康影響評価(リスク評価)」の実施を原則とすることが謳われており,国民の食生活の状況等を考慮するとともに,食品健康影響評価結果に基づいた施策を策定(リスク管理)することが規定されている.情報の提供,意見を述べる機会,その他の関係者相互間の情報及び意見交換(リスクコミュニケーション)も必須とされている. さらに,[1]緊急の事態への対処・発生の防止に関する体制の整備等,[2]関係行政機関の相互の密接な連携の下での施策の策定,[3]試験研究の体制の整備,研究開発の推進,研究者の養成等,[4]国の内外の情報の収集,整理,活用等,[5]表示制度の適切な運用の確保等,[6]教育・学習の振興及び広報活動の充実,[7]環境に及ぼす影響に配慮した施策の策定も規定されるとともに,食品安全委員会の設置について規定されている. |
図 食品安全基本法(平成15年法律第48号)の概要