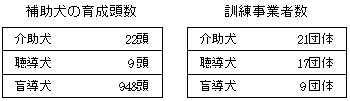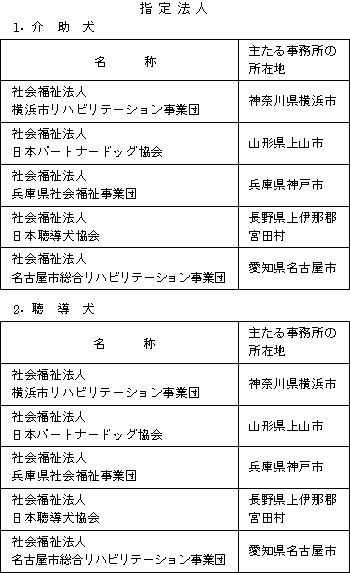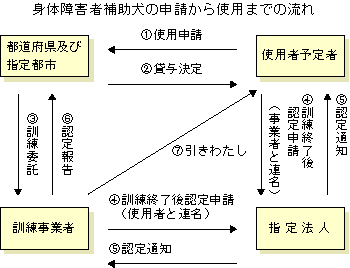![]()
|
身体障害者補助犬制度の概要
| 竹垣 守†(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部社会参加推進室長補佐) |
| 身体障害者の自立と社会参加を促進するための身体障害者補助犬法が昨年(平成15年10月)全面施行され,本法に基づき身体障害者補助犬の同伴の受入れを義務付けられる施設等について,法施行時の「国,地方公共団体,独立行政法人,特殊法人,公共交通機関等」に加え,「不特定かつ多数の者が利用する施設」についても適用がされたところである.全面施行後ようやく1年を経過したところであり,引き続きその周知を進めていくことが必要である現状をも踏まえ,以下身体障害者補助犬制度の概要を記述する. |
| 1.身体障害者補助犬法の制定について 身体障害者補助犬法における,身体障害者補助犬とは,身体障害者の日常生活を支援するものであり,「盲導犬」,「介助犬」,「聴導犬」を総称するものである. 本法が制定される以前においては,約50年の歴史をもつ盲導犬については,広く国民に知られていたところであるが,介助犬,聴導犬については実働頭数がきわめて少数であることや,すでに道路交通法に規定されていた盲導犬と異なり法的位置づけが何らなく,周知もされていなかったことから,公共的施設や公共交通機関においても円滑な受け入れがされていないという状況にあった. こうした状況を踏まえて,身体障害者補助犬を訓練する事業者及び使用者の各々の義務等を明らかにし,良質な身体障害者補助犬の育成・普及を行うとともに,身体障害者補助犬を同伴する場合の施設等利用の円滑化を図り,身体障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とした本法律が制定された. 法律においては,訓練事業者に対し,身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択すること,必要に応じ医療を提供する者や獣医師との連携を確保することにより身体障害者の状況に応じた訓練を行うことなどの育成上の義務を規定するとともに,身体障害者補助犬の使用者に対しては,使用にかかる適格性,身体障害者補助犬の行動の管理,衛生の確保等について規定を行っている.こうした一方で,国等が管理する施設,公共交通機関,不特定かつ多数の者が利用する施設に対しては,身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない旨が規定されている. |
| 2.身体障害者補助犬の機能と役割について 「身体障害者補助犬」とは,前述のとおり,盲導犬,介助犬及び聴導犬を総称するものであり,盲導犬については,周知のとおり,視覚障害者の歩行誘導を行うものであるが,介助犬については,身体障害者補助犬法において「肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために,物の拾い上げ及び運搬,着脱衣の補助,体位の変更,起立及び歩行の際の支持,扉の開閉,スイッチの操作,緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって,第16条第1項の認定を受けているもの」,聴導犬については,「聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために,ブザー音,電話の呼出音,その者を呼ぶ声,危険を意味する音等を聞き分け,その者に必要な情報を伝え,及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって,第16条第1項の認定を受けているもの」とされている. また,介助犬に関する具体的役割としては,厚生労働省の「介助犬に関する検討会報告書」にも記されるように,「手の代わりとなり,不可能だった動作が可能になる」,「書類など落としたものを拾ってくれるので,仕事の効率があがる」,「積極的に外出するようになり,行動範囲が広がる」,「頼むことに気兼ねがいらない」,「介助されるのではなく,自分でしている感覚をもつことができる」,「安らぎを与えてくれるので,心に余裕が生まれ,生活設計をする動機付けになる」など,直接的には,肢体不自由者の日常生活動作を介助することであり,そのことによって,肢体不自由者の自立や社会参加を促進し,生活の質の向上が図られるという効果が期待できるとされている. また,この他にも飼い主としての役割意識や責任感の向上,交流範囲の拡大などという効果,対人関係における潤滑油的効果をもたらす役割等も考えられるが,これらはペットと共通するものであることから,介助犬としての役割とは区別して考えられるべきとされている. |
| 3.身体障害者補助犬の訓練及び認定 身体障害者補助犬の訓練事業については,社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業として位置付けられており,訓練基準等については,身体障害者補助犬法施行規則(厚生労働省令)により規定されている. また,その詳細については,厚生労働省の「介助犬の訓練基準に関する検討会」,「聴導犬の訓練基準に関する検討会」等により報告されており,各訓練(基礎訓練・介助動作訓練(盲導犬については歩行誘導訓練,聴導犬については聴導動作訓練)・合同訓練)を行うことにより,使用者の指示に従い,確実・適切に各種動作を行うことができる良質な身体障害者補助犬を育成する体制の整備を図っている. さらに,この訓練を終了した犬が法律に規定される身体障害者補助犬となるためには,訓練事業者は,厚生労働大臣が指定する補助犬の認定を行うための「指定法人」に対し認定申請を行い,当該指定法人に設置される,医師,獣医師,社会福祉士等により構成された審査委員会を経て認定を受けることが必要となっている.この認定を受けた結果,法第12条に定める表示を行うことができ,法による身体障害者補助犬となる. なお,指定法人の認定を受けるまでの,経過的な措置(法附則第3条)として,平成16年9月30日までの間にかぎり,厚生労働大臣に届け出を行い証明書の交付を受けた犬について介助犬,聴導犬と表示することができる取扱いがなされていたところである.(盲導犬については,身体障害者補助犬法制定以前にすでに道路交通法による認定制度が存在したこと等も勘案し,経過措置(法附則第2条)により,当分の間,本法による指定法人の認定を要せず,従来どおり国家公安委員会が指定した法人(各盲導犬協会)が認定したものとされている.) |