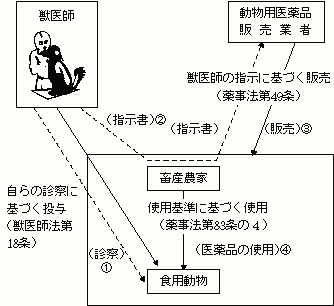| [1] |
Acar J:獣医畜産新報,54,752-755(2001) |
| [2] |
Acar J, Rostel B : Rev Sci Tech Off Epizoot, 20, 797-810 (2001) |
| [3] |
Anthony F, Acar J, Franklin A, Gupta R, Nicholls T, Tamura Y, Thompson S, Threlfall
EJ, Vose D, van Vuuren M, White DG : Rev Sci Tech Off Int Epizoot, 20, 829-839 (2001) |
| [4] |
Bengtsson B ed: SVARM 2002, Swedish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring,
National Veterinary Institute, Uppsala (2002) |
| [5] |
Bezoen A, van Haren JC, Hanekamp JC : Human health and antibiotics growth promoters
(AGP) : Reassessing the risk, Heiderberg Appeal Nederland Foundation, Amsterdam (1998) |
| [6] |
Committee on drug use in food animals : The use of drugs in food animals: Benefits
and risks, National Academy Press, Washington DC (1998) |
| [7] |
Emborg HD, Heuer OE ed : DANMAP 2002-Use of antimicrobial agents and occurrence of
antimicrobial resistance in bacteria from food animals, foods and human in Denmark, Statens Serum Institute,
Danish Veterinary and Food Administration, Danish Medicines Agency and Danish Veterinary Institute, Copenhagen
(2002) |
| [8] |
Kaatz GW, Barriere SL, Schaberg DR, Fekety R : J Antimicrob Chemother, 20, 753-775
(1987) |
| [9] |
Kijima-Tanaka M, Ishihara K, Morioka A, Kojima A, Ohzono T, Ogikubo K, Takahashi T,
Tamura Y : J Antimicrob Chemther, 51, 447-451 (2003) |
| [10] |
小嶋二三夫:飼料検査,478,1-8(2003) |
| [11] |
中島祥吉:薬が効かない―ヒトと感染症のたたかい―,63h86,丸善,東京(2000) |
| [12] |
Nicholls T, Acar J, Anthony A, Franklin A, Gupta R, Tamura Y, Thompson S, Threlfall
EJ, Vose D, van Vuuren M, White DG, Wegener HC, Costarrica ML : Rev Sci Tech Off Int Epizoot, 20, 841-847
(2001) |
| [13] |
日本植物防疫協会:農薬要覧2001,88-89(2001) |
| [14] |
農林水産省動物医薬品検査所:動物医薬品検査所最近10年のあゆみ,13-17(1996) |
| [15] |
高橋敏雄,守岡綾子,石原加奈子,木島まゆみ,小島
明美,大園智子,船橋かおり,田村 豊:獣医畜産新報,54,733-738(2001) |
| [16] |
田村 豊:動薬検年報,39,1-13(2002) |
| [17] |
The joint expert advisory committee on antibiotics resistance : The use of antibiotics
in food producing animals : Antibiotic-resistant bacteria in animals and humans, Commonwealth Department
of Health and Aged Care and Commonwealth Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia,
Canberra (2003) |
| [18] |
World Health Organization: WHO Global Principles for the Containment of Antimicrobial
Resistance in Animals Intended for Food, Report of a WHO consultation, Geneva (2000) |
| [19] |
八木澤守正:抗菌薬使用の現状調査,平成11年度厚生省科学研究補助金分担報告書,47-59(1999) |
| [20] |
Yamamoto K, Kijima M, Yoshimura H, Takahashi T : J Vet Med B, 48, 115-126 (2001) |
| [21] |
Yoshimura H, Ishimaru M, Endoh YS, Kojima A : J Vet Med B, 48, 555h560 (2001) |
| [22] |
Yoshimura H, Takagi M, Ishimaru M, Endoh YS : Vet Res Commun, 26, 11-19 (2002) |
![]()