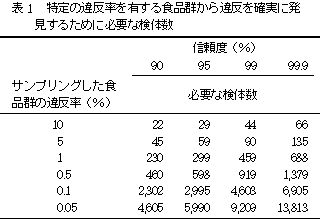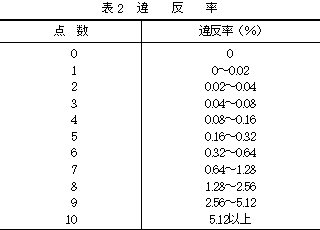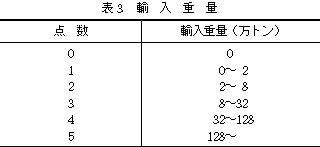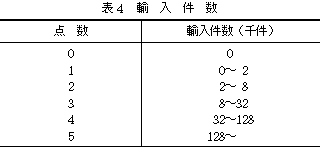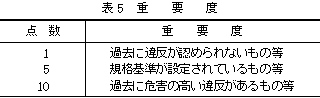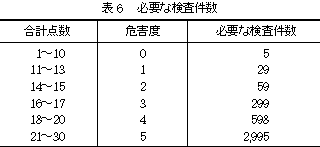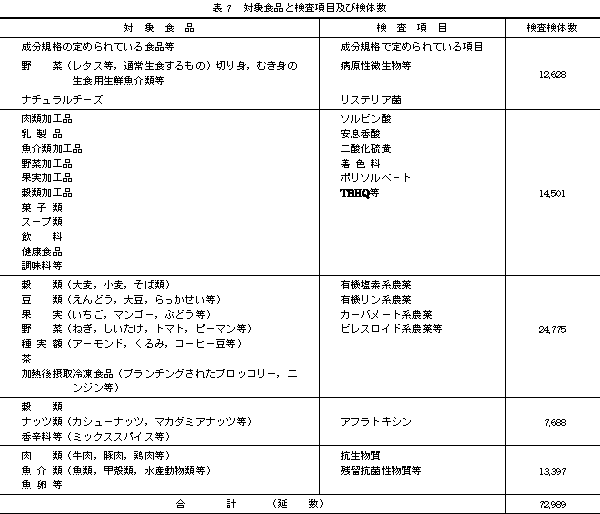| (1) |
統計学的な考え方
食品の安全検査を目的としたモニタリング計画の策定に際し,必要な検査項目に対する検体数は,当該食品群が一定レベル以上の違反率を有する食品群であることを確実に発見するために十分な数でなければならない.この検体数については,統計学的に設定される必要があり,FAO/WHO国際食品規格計画の分析・サンプリング部会において,そのための国際的な考え方が示されている.
たとえば,1%以上の違反率がある食品群から少なくとも1件の違反を95%の信頼度で発見するためには,299件サンプリングする必要がある.ここで留意しなければならないのは,サンプリング数は輸入件数の母数に関わらず設定されるということである.すなわち,1000件の輸入届出がある食品群であっても,100,000件の輸入届出がある食品群でも299件サンプリングして検査を行い,すべてが違反でなければ95%の信頼度でこの食品群の違反率が1%以下であることが統計学的にいえるということである.ちなみに,同じ95%の信頼度で違反率を5%以下であることを証明するためには,59件のサンプリングでよく,違反率が0.1%以下であることを証明するためには2,995件のサンプリングを行わなければならない(表1参照). |
| (2) |
具体的な策定方法
わが国の輸入食品のモニタリング検査計画を策定するにあたっては,対象とする食品群を分類(平成15年度計画では122品目群に分類)した上で,過去の違反率のみでなく,違反になった場合の危害の程度(その違反品を摂食した場合の個々人の健康の危害の程度のみならず,公衆全体に対する影響を推測するため輸入数重量等も考慮する)も勘案したスコアリングを行い必要な検査件数を定めている.
具体的には,食品群ごとに
| [1] |
違反率については,表2のとおり,違反率を0〜10に点数化し,違反率が高いものほど点数を高くし, |
| [2] |
輸入重量については,表3のとおり,輸入重量を0〜5に点数化し,量の多いものほど点数を高くし, |
| [3] |
輸入件数については,表4のとおり,輸入件数を0〜5に点数化し,件数の多いものほど点数を高くし, |
| [4] |
重要度については,表5のとおり,過去に危害の高い違反があるもの等を勘案の上,1,5,10の3段階の点数をつけ,
これらの合計点数により,危害度を設定し,表6のとおり検査すべき検体数を定めている.なお,信頼度は先進諸国が採用している95%としている. |
|
| (3) |
モニタリング検査の実施
平成15年度におけるモニタリング検査は次のとおり計画されている.
| [1] |
対象食品
表7に掲げる食品を対象とし,次に掲げる食品については,食品衛生法違反の蓋然性が高いとして除外した.
| ア. |
食品衛生法第15条第3項に基づく検査が行われている食品 |
| イ. |
事故品 |
| ウ. |
積み戻り品 |
| エ. |
税関職員から食品衛生上の問題があるとして連絡のあった食品 |
| オ. |
初めて本邦に輸入される食品 |
なお,上記にかかわらず,厚生労働大臣の指定検査機関及び輸出国公的検査機関の検査成績書の提出があったものならびに同一食品の継続的輸入として,過去の検査成績書の提出のあるものについても,検査機関の精度管理等の観点から対象としている.さらに,[1]に該当する食品であっても,食品衛生法第15条第3項に基づく検査項目と異なる検査項目についても対象となる. |
| [2] |
試験項目
表7に掲げる食品について,食品,添加物等の規格基準において定められている成分規格等の項目,病原微生物,カビ毒等を試験項目としている. |
| [3] |
検査検体数
4(2)において記載した方法に基づき定められたサンプリング検体数68,489検体に,中国産野菜のように危険情報に基づき集中的に検査を実施する検査強化分4,500検体を加えた72,989検体を全国の検疫所においてサンプリングし年間を通じて検査することとなっている. |
|
| (4) |
モニタリング検査の結果
モニタリング検査において,違反が発見されたものについては,ただちにモニタリング検査率を50%(2件に1件)に引き上げて監視強化し,引き続き,再度違反が発見されるものについては,100%命令検査の対象としている.
なお,輸入食品の違反事例については,すべて厚生労働省のホームページに掲載され,2週間ごとに更新されている.(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html) |
![]()