![]()
|
輸入食品の残留物質検査体制について
| 滝本浩司†(厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課検疫所業務管理室室長補佐) |
| 1.は じ め に BSE問題,無登録農薬問題,食品の偽表示問題等,食の安心・安全を巡る諸問題が次々と発生している.また,わが国は食料を大きく海外に依存している状態が続いており,その依存率はカロリーベースで約60%に達している.輸入食品は,その生産や製造・加工行程が見えにくいことから,輸入食品に対する消費者の不安感は根強いものがあり,水際検査の重要性は益々増大している. そこで本稿では,輸入食品の残留物質検査体制について解説することとする. |
| 2.輸入食品の検査体制 わが国への食品の輸入量は依然増加傾向にあり,平成13年度においては,3,250万トンに達している.これら食品を輸入する場合,食品衛生法に基づき厚生労働大臣への届出が義務づけられており,平成13年度においては160万件を超える届け出がなされている.近年,多様な消費者嗜好に即応するための流通チャンネルが発達し,以前に比べ,輸入がより小口頻回に行われる傾向にあり,輸入届出件数は10年前に比較すると約2.2倍に急増している.(図1) この輸入届出の窓口は全国31の検疫所に配置されており,283名の食品衛生監視員が輸入食品の監視及び指導等を行っているほか,横浜検疫所と神戸検疫所に設置された輸入食品・検疫検査センターにおいて,残留農薬や遺伝子組換え食品など高度な検査を集中して実施している(図2). ひとくちに輸入食品といっても,たびたび食品衛生上問題となる食品もあれば,違反の蓋然性がかぎりなく小さい食品までさまざまである.これら年間160万件を超える輸入食品を効率よく検査し,違反食品の国内流通をくい止めるため,図3のフローチャートに示すように,輸入時においては大きく分けて命令検査とモニタリング検査が実施されている. |
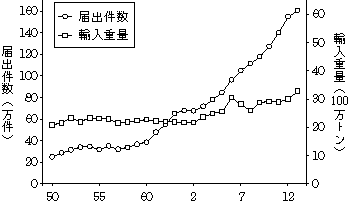 図1 年次別輸入・届出数量の推移 |
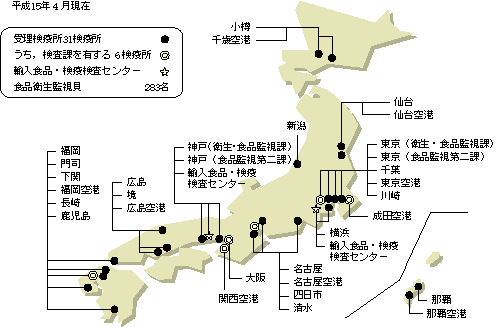 図2 厚生労働省検疫所輸入食品監視窓口一覧 |
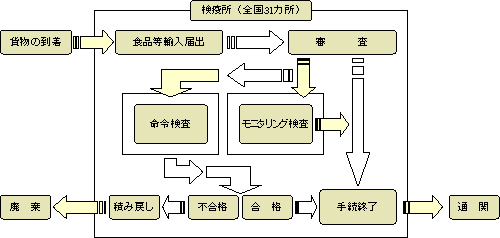 図3 輸入食品等検査手続きの流れ |
| 3.命 令 検 査 食品衛生法第15条第3項注1)に基づき実施される検査であって,厚生労働大臣が輸出国の衛生状態や過去の違反状況などから食品衛生法違反のおそれがあると認められる食品を輸入する者に対し,指定検査機関の検査を受けるべきことを命じるものである. 現在対象となっているのは,落花生のアフラトキシンや特定の国の農産物の残留農薬や畜産物の残留動物用医薬品などであり,通知により指定されている.届け出された食品がこれら命令検査対象食品に該当する場合には,輸入者は,検疫所から発行された検査命令書の内容に従い,指定検査機関に検査命令書の写し及び検査手数料を添えて検査の申請を行う.検査機関は,検査命令書に従い試験品の採取及び検査を行い,検査の結果については検疫所を通じて輸入者に通知され,その結果,法に適合するものであれば輸入者は当該食品を輸入することが可能となる. |
|||
|
|||