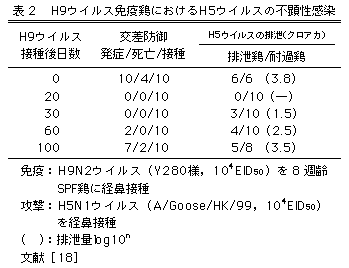| III.H5ウイルスの変異 |
インフルエンザウイルスはRNAウイルスであるために突然変異を起こしやすい.また,異なるウイルスが重感染した場合に,8本の異なる遺伝子断片が入れ代わり,合いの子ウイルスが容易に生まれる(遺伝子交雑).本解説では,H5およびN1遺伝子以外の内部遺伝子が異なるものを別の遺伝子型として区別している.
1997年から2002年までに分離されたH5ウイルスの遺伝子型をGuanらの報告を参考にして図1にまとめた[9].毎年同じ遺伝子型が流行してもおかしくないが,2001年,2002年の分離株の遺伝子型は年々変わっている.新しい遺伝子型が次々と誕生する理由として,汚染元においてH5ウイルス(Gd/96株)が撲滅されずに,徐々に分布域を広めながら未知の水禽類ウイルスと出会い,遺伝子交雑を繰り返しているからと考えられる.その相手方のウイルスは香港では見つかっていない. |
| |
| IV.香港の防疫対策 |
| |
| 1.家禽の生産・流通・販売 |
| |
現在香港には約150戸の養鶏場と40戸のハト農場があり,約140万羽の鶏が飼育され,毎日約2万羽が鶏卸売市場に出荷されている.また,中国本土からは毎日10万羽の鶏と2万羽の陸生家禽類(キジ,烏骨鶏,チャッカー,ハト)が同じ鶏卸売市場に搬入されてくる.一方,水禽類は1998年から肉処理後に流通・販売されるようになった.現在ではすべてが中国本土産で,多くは処理肉で輸入されるが,一部は生鳥で香港の水禽類卸売市場に搬入されて,そこで肉処理され販売される. |
| 2.防疫対策の変遷 |
| |
本病の防疫には,鶏卸売市場に搬入されてくる生鳥の検査と,その流通段階における徹底した衛生対策が必要である.香港では1997年の発生以降,3度にわたり衛生対策が強化されている.具体的な対策は,鶏・ウズラ・水禽類の市場の分離,ウイルス検査の徹底,卸売市場・生鳥マーケットの消毒日の設置,ワクチンの使用であるが,その変遷を年度ごとに紹介する. |
| |
1997年の対策:1997年の発生後に実施された対策は以下のものである.[1]H5ウイルスが水禽類から陸生家禽類に持ちこまれないように,陸生家禽類と水禽類の卸売市場を分離した.[2]中国本土産,香港産ともに,出荷5日前にHI抗体が陰性であることを確認してから出荷する.[3]抗体検査書類の確認は,香港産は鶏卸売市場で,中国本土産は検疫場所と鶏卸売市場で行う.[4]陸生家禽類は中国本土産,香港産ともに1箇所の鶏卸売市場に搬入する.なお,香港での水禽類の生産は1998年を最後になくなった |
| |
2001年の対策:2001年の発生後に次の対策が追加された.[1]香港産の鶏については出荷20日前にもHI抗体検査を行う.[2]中国本土産の陸生家禽類は,検疫場所でも全ロットについて抗体検査を行う.[3]鶏卸売市場と生鳥マーケットで定期的にウイルス検査を行う.[4]ウズラは,2001年をもって香港生産は中止,中国本土産の生ウズラの輸入も中止した.すべて,中国本土で処理された肉の輸入となった.[5]鶏卸売市場は10日毎,生鳥マーケットは30日ごとに,全家禽を処分して消毒する. |
| |
2002年の対策:2002年の発生後に次の対策が追加された.[1]鶏卸売市場に搬入された香港産の鶏および中国本土産の陸生家禽類・水禽類を対象に,抽出ロットについて抗体検査を行う.[2]香港の養鶏場で1年間不活化オイルアジュバントワクチン(H5N2)を試験的に使用して,その評価を行う. |
|
|
| |
| V.ウイルスの進入経路 |
| |
| |
1997年の発生:侵入経路として,養鶏場が密集する新界地区に多数ある池に飛来する野生水禽類と,新鮮な鶏肉を好む香港人のために,毎日大量に中国本土から輸入されてくる生鳥の可能性が考えられる.広東省のガチョウ農場で1996年にH5ウイルス(Gd/96株)の感染があり[27],その地域の農場から水禽類が香港に輸入されていた.また,当時は生鳥マーケットで水禽類が鶏と一緒に飼育されていた.これらのことから,輸入水禽類を介してH5ウイルスが香港に持込まれたと考えられている. |
| |
2001年の発生:香港の養鶏場では発生していないこと,水禽類は生鳥として流通していないことから,これらは汚染源とは考え難い.中国本土産の鶏・ウズラまたは野鳥がウイルスを持ち込んだ可能性がある. |
| |
2002年の発生:養鶏場での発生の1カ月前に生鳥マーケットでウイルスが分離されていたこと,ウズラ・水禽類は生鳥として流通していなかったことから,これらは汚染源とは考え難い.中国本土産の鶏または野鳥を介してウイルスが持ち込まれた可能性がある. |
| |
2003年の発生:公園の水禽類から最初にウイルスが分離されたことから,野鳥の可能性もあるが,中国本土産の輸入鶏が汚染していた報告があることから,その可能性が高い.
これらの発生に共通する進入経路は中国本土産の鶏と野鳥である. |
|
|
| |
| VI.摘発漏れの原因 |
| 香港政府が防疫対策を強化しているにもかかわらず,高病原性鳥インフルエンザが続発する原因として,病原体の侵入を完全には摘発できないことが考えられる. |
| |
| |
H9ウイルスの蔓延:南中国の陸生鳥類で流行しているH9ウイルスには2つのグループがある.哺乳類に親和性のある内部遺伝子を持つものと,親和性の低い内部遺伝子を持つものである.両ウイルスとも香港の生鳥マーケットで分離されている[5-7,
14].後者は,中国本土や香港の養鶏場に広く浸潤しているウイルスで,産業上目立った被害をもたらさないが,鶏群の50%以上がこのウイルスに汚染されている[6]. |
| |
不顕性感染の機構:1997年の発生で,鶏が高病原性のH5ウイルスに感染しても発症しなかった点は予想外であった.この現象は2001年,2002年にもみられた[9].香港の鶏はH9ウイルスに汚染されていたことから[6],その影響が検討された結果,H9ウイルスに免疫となった鶏は,H5ウイルスに感染しても不顕性となることが確認された[18,
19](表2).H9ウイルス感染後100日以内であれば,H5ウイルスに感染しても多くは無症状でウイルス排泄量も少ないが,それ以降は発病率・ウイルス排泄量ともに増加する[18].この交差免疫は中和抗体ではなく,細胞性免疫(細胞障害性のCD8+T細胞)に由来することが確認されている.
これまで,インフルエンザウイルスではHA亜型が異なると交差免疫は成立しないとされてきたが,今回見つかった交差免疫については詳細調べる必要がある. |
| |
搬入量と検査方法:鶏卸売市場に搬入される中国本土産の鶏はトラックで年間約2万台に及ぶ.この中に感染鶏が紛れ込んでいたとしても,H9ウイルスによって不顕性感染になるのであれば,症状の観察や抗体検査で摘発することは難しい.また,生鳥マーケットは香港全体で800カ所ある.感染が不顕性化するのであれば,ウイルス分離以外に有効な検査法はなく,物理的にも時間的にも摘発には限界がある. |
|
|