| 1.は じ め に |
1981年,山階鳥類研究所による新種ヤンバルクイナの発見は国内の鳥類では59年ぶり,先進工業国での鳥類の新種発見は奇跡的といわれるほどの大ニュースとなった(図1).さらに謎に包まれたそのクイナの生態が『飛べない鳥』であったことや姿がきわめて美しく目立つ色彩であったにもかかわらず発見されなかったことから,ヤンバルクイナの和名の由来である山原(ヤンバル:沖縄本島北部地域)の森林がいまだ秘境であることを裏付けると同時に,ヤンバル地域の名を一躍全国区におしあげる立役者となった.また沖縄県内では,海邦国体や民間の広告やキャンペーンのマスコットになるなど,これほど人々に親しまれている野生動物は他にない存在となっている.
ところが,新種ヤンバルクイナの発見からちょうど20年を迎えた2001年,ヤンバルクイナの生息域や生息数が急速に減少していることや,ノネコによる捕食を裏付ける報告などが相次ぎ,ヤンバルクイナの絶滅が現実のものとなる恐れがでてきた. |
 |
| 図1 ヤンバルクイナ |
| 2.ヤンバルクイナの危機的状況 |
ヤンバルクイナの発見当初の1980年代,山階鳥類研究所,環境省,WWFJ(世界自然保護基金日本委員会),地元沖縄の野鳥研究者によって調査が行われた結果,沖縄本島北部地域に限定されているとはいえ,意外にもヤンバルクイナの生息域(国頭村・大宜味村・東村)は広く,生息数も2,000羽前後であることが判明した.観察事例が増えるにつれ,鳴き声による識別も容易になり,生息状況が把握されていくと,『幻の鳥』とよばれていたヤンバルクイナは,容易には絶滅はしないだろうという楽観論さえでるようになっていた.
ところが,その後,沖縄県や環境省,山階鳥類研究所のヤンバルクイナ生息状況調査によって,ヤンバルクイナの生息域と生息数がきわめて急速に減少していることが判明した.1985年から2000年までの15年間で生息域の面積は約25%減少し,生息南限ラインは約10km北上した(図2).
2003年現在,3年前まで確認できていた大宜味村でのヤンバルクイナの生息は確認できなくなっている. |
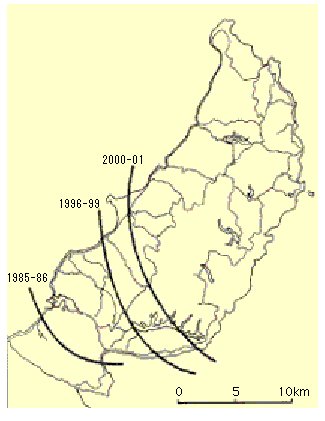 |
| 図2 ヤンバルクイナの生息域南限ラインの推移 |
| 3.ヤンバルクイナを絶滅へ追い詰める原因 |
| (1) |
生息環境の減少と悪化
ヤンバルクイナを絶滅へ追いやる原因は,多くの希少野生動物が危機的状況にあることと同じように生息環境の減少と悪化がひとつの要因としてあげられる.ヤンバルクイナの生息する沖縄本島北部の森林は,ダムの建設に伴う森林の伐採や林業による常緑広葉樹の伐採,大規模林道建設に伴う森林面積の減少,生息域の分断などの環境改変が著しい状況が続いている.特に森林内に延長,整備された林道は後述するマングースやノネコの森林内への進入拡散を容易にしていると考えられている. |
| (2) |
交通事故や側溝による被害
ヤンバルクイナの生息分布域内の人為的な構造物や車両による交通事故の被害は,すでに個体数が著しく減少したヤンバルクイナにとってきわめて甚大な影響をあたえていると考えられる.
特に,林道沿いの側溝は孵化直後のヤンバルクイナのヒナのみならず,両生類や爬虫類などの小動物にとっても這い上がれない絶壁のような状況を作り出している.また,整備拡張された県道や林道では日常走行する車両が増加するとともに,高速での走行が可能となり,道路沿いに生息する地上走行性のヤンバルクイナが交通事故に巻き込まれる確率が高まっており,昨年,1年間で5件の交通事故死が確認されている. |
| (3) |
移入種(ノネコ,マングース)による影響
| [1] |
北上するマングース
1910年,ハブやネズミの駆除を目的として沖縄本島南部地域に導入されたマングースは,現在では沖縄本島北部地域にまで北上し,在来の希少野生動物の脅威となっている.マングースの食性は昆虫類,爬虫類,両生類,鳥類及びその卵であり,このほとんどがヤンバルクイナの食性と重複しており,生態系の中で競合していると考えられている.マングースの北上とともにヤンバルクイナが逃げるように生息域を北上,縮小させていることが沖縄県及び山階鳥類研究所の調査などから明らかとなってきている(図3).これらのことから,沖縄県は2000年からマングースの捕獲事業を開始し,2002年度までに合計2,713個体の捕獲実績をあげている.しかしながら,現時点でのマングースの捕獲事業はマングースの北進を食い止められるかどうかという状況にあり,沖縄県全域からの排除には莫大な予算及び労力を要することは間違いない. |
| [2] |
ヤンバルの森林で待ち受ける猫の脅威
ヤンバル地域での猫による野生動物への影響は15年以上前から指摘されてきた.これは大規模な道路整備や林道の開通に伴い,一般市民がヤンバルの森林奥地へと容易に入り込めるようになったのと同時に,人里はなれた森林内へ猫を捨てやすい状況がうまれたため,急激に野生化した猫(以下ノネコ)が増え,繁殖するようになったためと考えられる.2000年から開始した沖縄県のマングース捕獲事業ではマングース捕獲ワナに延233頭のノネコの捕獲がされ(図4),ヤンバル地域のノネコの多さが浮き彫りになった.その後,2001年8月21日,国頭村内の伊江林道で採取された哺乳類の糞からヤンバルクイナの羽毛が検出され,DNA分析により猫の糞であることが判明した. |
| [3] |
絶滅しやすい飛べないクイナ
飛べないクイナ類は世界で約33種が知られているが,そのうち13種がすでに絶滅し,現存する20種のうち18種はいずれも絶滅の危機にあるといわれている.グアム島に生息していた飛べないクイナであるグアムクイナは1981年には約2,000羽生息していたものが移入種であるナンヨウオオガシラというヘビによる捕食により約5年間で約20羽まで減少し,絶滅回避のためすべての個体が人工増殖の目的で,捕獲された.これにより,野生のグアムクイナは1987年にいなくなった.グアムクイナの例から,現在,1,000羽前後しか生息していないと考えられているヤンバルクイナは,最悪の場合,あと5年から10年で絶滅してしまうのではないかと危惧されている.
ヤンバルクイナの危機的状況の特徴は,生息環境が残っているにもかかわらず,急速にその生息域と生息数が減少しているところにある.これは,移入種による影響が最も大きいことを示唆している. |
|
|
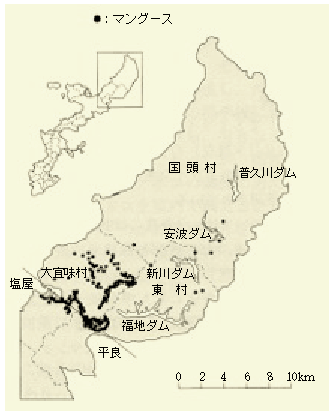 |
図3 マングースの捕獲地点(平成12年10月〜平成14年3月)
(沖縄県自然保護課提供) |
| |
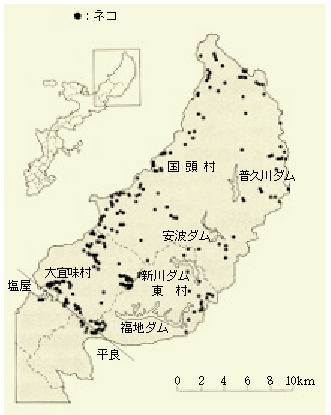 |
図4 ネコの捕獲地点(平成12年10月〜平成14年3月)
(沖縄県自然保護課提供) |
|
![]()
![]()