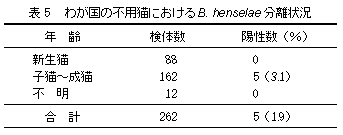![]()
|
| |V.人のBartonella 属菌感染症 | |
| 1.猫ひっかき病 | |
| CSDは現代社会で最も一般的にみられるBartonella 感染症で,その主要な病原体はB. henselae である.B. clarridgeiaeもまれに定型的,非定型的なCSDを起こす[55,
59].定型的なCSDでは,猫から受傷後,3〜10目に受傷部すなわち菌の侵入部位(通常,手指や前腕)に虫さされに似た病変が形成され,丘疹から水疱に,また,一部では化膿や潰瘍に発展する場合もある.これらの初期病変から1,2週間後にリンパ節の腫脹が現れる.リンパ節炎は,一般に一側性で,鼠径部,腋下あるいは頸部リンパ節に多く現れる[55,
64].わが国の130名のCSD患者のうち,リンパ節の腫脹を呈した患者は84.6%で,そのうち33%は頸部,27%が腋窩部,18%が鼠径部のリンパ節であった[71].通常,リンパ節の腫脹は疼痛を伴い,数週から数ヶ月間持続する.多くの症例で,全身感染の徴候,すなわち,発熱,悪寒,倦怠,食欲不振,頭痛等を示すが,一般に良性で,自然に治癒する. CSDの非定型的な症状は5〜10%の割合で発生する.症状としては,パリノー症候群(耳周囲のリンパ節炎,眼球運動障害等),脳炎,骨溶解性の病変,心内膜炎,肉芽腫性肝炎,あるいは血小板減少性の紫斑等が報告されている[14, 58, 60].脳炎はCSDの最も重篤な合併症の一つで,リンパ節炎を発症してから2〜6週後に発症する[14, 29].ほとんどの例で後遺症なしに完全に治癒する. |
| (1)発生状況 | |
| Jacksonら[46]によると,1992年の全米のCSD患者は年間約22,000人で,そのうち約2,000人が入院しており,CSDの年間発生率は0.77〜0.88/100,000人と見積もられている.米国のコネチカット州では,1992〜1993年にかけて246人のCSD患者が報告され,年間発生率は3.7/100,000人となっている[40]. わが国では,1953年に浜口ら[39]によって本症が初めて報告されて以来,症例は散見されている.全国的なCSD患者数に関する統計はないが,神戸市と福岡市の医師に行ったアンケート調査において,医師が経験した人獣共通感染症のうちCSDは外科系医師では1位,内科系医師では2位にランクされている[89].これより,わが国でも相当数のCSD患者が発生しているものと考えられる. 各国のCSD患者のB. henselae 抗体陽性率は健常者のそれに比べて,有意に高い値を示している.わが国でもCSDと診断された患者の39〜50%がB. henselae 抗体陽性であった[52, 88, 96].また,健常者のうち,猫の飼育・受傷歴のないグループの抗体陽性率は2.3%(4/173),猫の飼育歴・受傷歴のあるグループでは12.5%(10/80),CSD患者の同居家族では21.4%(3/14)であることが示されている[88, 96].これらの事実は,猫が本症の重要な感染源であることを示しているものと思われる. |
|
| (2)患者の性,年齢 | |
| CSD患者は,男性に多発する傾向があることが報告されている[14, 46].いっぽう,わが国では全患者の60%以上が女性で,10代と40代の女性に多発する傾向がみられている[95].CSDは小児から老人まで全年齢層に発生するが,成人より子供の割合が高く,15歳以下の症例が45〜50%を占めている[14, 40, 46, 71].わが国は,9歳以下の子供では,女子より男子に多発する傾向がみられる[95].このことは,男子の猫の扱いが乱暴で,引っ掻かれたり,噛まれたりする頻度が高いことを示しているのかもしれない. | |
| (3)発生と季節 | |
| CSDは一年の後半,7月〜12月[14, 95],あるいは秋から冬にかけて多発している[46, 60].この理由として,夏のネコノミの繁殖期にB. henselaeに感染する猫が増加し,その後,寒い時期になると猫は室内にいることが多くなるため,飼い主が猫から受傷する機会が増えるためではないかと考えられている. | |
| (4)猫のB. henselae 抗体保有率 | |
| 猫のB. henselae 抗体保有率は国,地域,あるいは調査対象の猫等によってさまざまである(表3). 米国のコネチカット州では,CSD患者の飼い猫のB. henselae 抗体陽性率は81%で,対照群の猫の38%に比べ有意に高いことが示されている[97].Childsら[18]は,調査した猫の14.7%(87/592)が抗体陽性で,特に,野良猫で44.4%と高いことを示している.カリフォルニア州を中心とした調査では,81%(166/ 205)の猫が抗体陽性で,高い抗体価を示した猫では菌血症を示す率が高いことも示されている[19].動物病院に来院した猫を対象とした調査では,21%(109/578)が抗体陽性であった[10].さらに,米国の猫[47]や日本の猫[63]で,気候が温暖で湿潤な地域では本菌の抗体陽率が高いのに対し,寒冷な地域で低かったことから,本症はノミを含む節足動物の分布と関係している可能性が示されている. その他の国では,オーストリアで33.3%(32/96)[3],フランスで36%(23/64)[22],スイスで8.3%(61/728)[34],オランダで56%[5],ジンバブエで24%,南アフリカ共和国で21%[49],イスラエルで39.5%[4]の猫がそれぞれ抗体陽性であったことが報告されている. わが国では,Uenoら[90]が,調査した猫の15.1%がB. henselae 抗体陽性であったことを報告している.Maruyamaら[62]は,神奈川県および埼玉県では飼育猫の9.1%がB. henselae 抗体陽性であったこと,また,全国の猫では8.8%が抗体陽性であったこと,1〜3歳の若い猫,室外飼育の猫およびノミの寄生のあった猫で有意に高かったことを明らかにした[63]. 米国では野生のピューマ,ボブキャットや動物園で飼育されているヒョウやライオンなどの猫科動物からもB. henselae 抗体が検出されており,その保有率も地域によっては飼い猫と同等の高い値となっている[94].CSDの疫学において,これらの野生猫科動物がどのように関与しているのかは不明であるが,B. henselae は自然界の猫科動物にも広く分布しているものと思われる. |
|
| 人と動物のBartonella 感染症 |
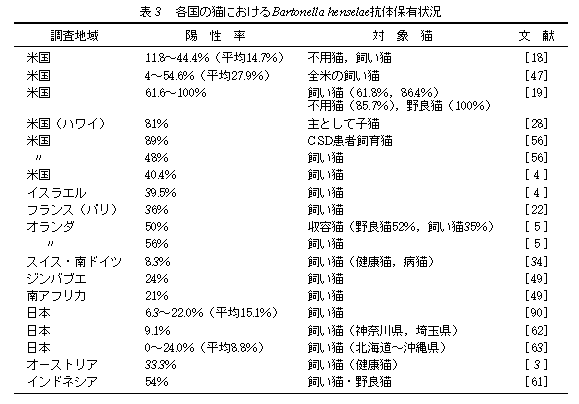 |
| (5)猫のBartonella 保菌率 | |
| Regneryら[75]が1992年に初めて猫のB. henselae菌血症を報告し,CSDおよび細菌性血管腫(Bacillary angiomatosis; BA)の病原巣としての猫の重要性を指摘して以来,世界各国の猫の保菌状況が報告されるようになった(表4). 米国のKoehlerら[54]は,BA患者の所有する7頭の猫の血液から本菌を検出するとともに,グレートサンフランシスコ湾地域のペットおよび収容猫の41%(25/61)が菌血症であることを報告した.Chomelら[19]は,調査した北カリフォルニアの猫の39.5%が菌血症で,特に12カ月齢以下の若い猫とノミの感染を受けている猫において菌血症の割合が高いことを示している.また,ハワイでは72.4%(21/29)[28],ドイツでは13%(13/100)[79],オランダでは22%[5],デンマークでは22.6%(21/93)[20],インドネシアでは64.3%(9/14)[61],タイでは27.6%(76/275)[68],フィリピンでは61.3%(19/31)[21]の猫からBartonellaが分離されている. わが国では,1995年にMaruyamaら[67]により初めて猫からB. henselaeが分離された.その後,Maruyamaら[66]は,全国の690頭の猫について詳細に調査し,その7.2%(50/690)がBartonella属菌を保菌していたこと,3歳以下の猫で保菌率が高いことを明らかにした.保菌率は北海道,宮城県の0%から沖縄県(島尻郡)の20%で,南の地方や都市部の猫で高いことから,わが国の猫のBartonella 保菌率は,抗体陽性率と同様にノミの分布あるいは猫の密度に関係している可能性が考えられる(図1). 猫はB. henselae, B. clarridgeiaeに単独,あるいは両菌種に混合感染している例が各国で報告されている[37, 41, 61, 66, 68]. |
|
| 丸山 総一 壁谷英則 見上 彪 |
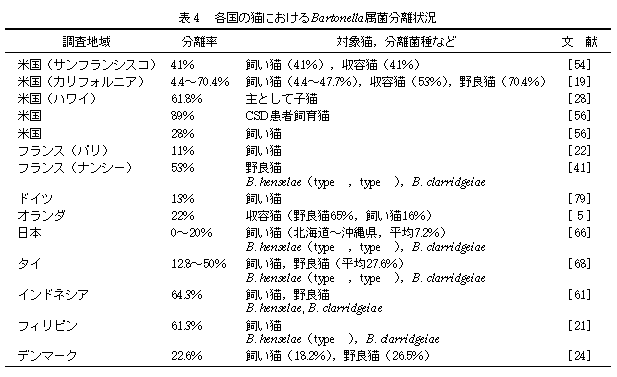 |
| 人と動物のBartonella 感染症 |
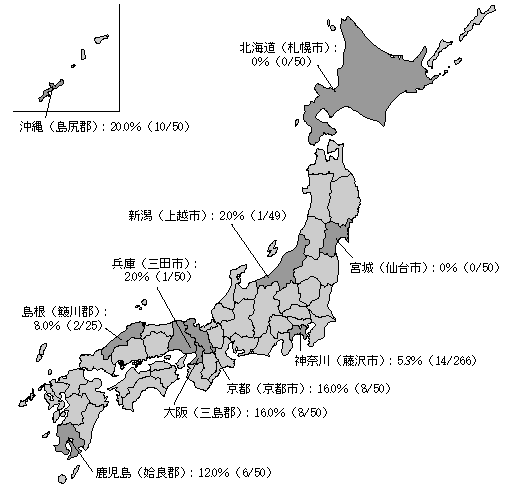 |
| 2.細菌性血管腫 | |
| BAはB. quintana,[57, 82]およびB. henselae によって起こる[1, 2, 84, 93].B. henselaeが原因となるBAの多くは,免疫不全状態の人に発生する.BAは上皮様血管腫症(epitheloid angiomatosis)ともいわれ,血液の充満した嚢腫を特徴とした皮膚の血管増殖性疾患で,臨床的にカポシ肉腫のような紫色や無色の小胞あるいは嚢胞性皮膚病変である[54].実質臓器に嚢腫が波及した場合,細菌性肝臓紫斑病(bacillary peliosis hepatis; BP),脾臓性紫斑病(splenic peliosis)あるいは全身性BAとよばれる. | |
| 3.塹 壕 熱 | |
| 塹壕熱は第一世界大戦中に約100万人の兵士が罹患した5日熱(quintan fever:B. quintanaの名前の由来ともなった),Wolhynia熱としても知られている.潜伏期は15〜25日で,軽度の発熱から重症の者までさまざまな臨床像がみられる.通常,突然の発熱に始まり,しばしば激しい頭痛と足の痛みが一定期間持続する.足の痛みは時に重篤で,特に脛骨に現れる.患者の舌には舌苔が生え,結膜充血,斑状紅斑性丘疹,背部痛,筋肉痛等が生じることがある.慢性患者では貧血を起こすことがある.死亡例はない[69]. | |
| 4.菌 血 症 | |
| Bartonella 属菌による持続的な菌血症は,当初,第一次世界大戦中に流行した塹壕熱の症状として認められた.現在では,B. quintana に感染した都会のホームレスの人達やアルコール中毒患者に多くみられる症状となっている[13, 86].B. henselae による菌血症はHIVh感染者[54],骨髄移植者[2],発熱を呈した免疫健常者[92]で報告されている.さらに,近年,米国で発熱と菌血症を呈した牧夫からB. vinsonii subsp. arupensisが分離されている[91]. | |
| 5.心内膜炎 | |
| B. quintana,B. henselae, B. elizabethae およびB. vinsonii subsp. berkhoffii が細菌性心内膜炎に関与することが知られている.Spackら[85]は,HIVに感染したホモセクシャルの人で,B.
quintana による心内膜炎を初めて報告した.また,英国で,僧帽弁と大動脈弁に心内膜炎を併発したアルコール中毒患者の男性の血液からB. quintana が分離されている[38]. B. henselae の心内膜炎は,猫ひっかき病の非定型的な症状として認められ,特に猫との接触がある心臓弁膜症患者に多くみられる[30, 43, 57]. 1986年に心内膜炎患者の血液から分離された偏好性の菌がB. elizabethaeと命名されたが,本菌による心内膜炎の事例はこの1例が報告されているのみである[25]. B. vinsonii subsp. berkhoffiiも人に心内膜炎を起こす可能性が示されているが,報告された症例では本菌に対する抗体とPCR法でその遺伝子が検出されたのみで,患者の血液からは本菌は分離されていない[77]. 最近の研究では,人の心内膜炎の3%がBartonella の感染による可能性が高いことが報告されている[69].これらの事実から,抗生物質で治療をしていないにもかかわらず,通常の血液検査で菌の培養が陰性の心内膜炎患者を診断する際,Bartonella の感染を疑う必要があるものと思われる. |
|
| 6.その他の疾病 | |
| その他のBartonella属菌が起こす疾病として,B. bacilliformis によるペルーイボ病(Verruga peruana),オロヤ熱,カリオン病などがある.ペルーイボ病は南アメリカのアンデス地方で流行しているリューマチ痛と発熱を伴った皮膚と粘膜に生じる多発性結節性の血管病変である.感染数カ月後に,首,顔,体幹に果物のクランベリーに似た肉芽腫性病変が現れる.さらに,粘膜や内臓表面にも病変が現れる場合がある.組織学的にこれらの結節性病変は,内皮細胞の増殖を伴う血管病変である[69]. オロヤ熱は高熱,敗血症,および溶血性貧血を伴う全身性疾患である.2〜6週間の潜伏期の後,高熱,悪寒,頭痛が現れる.これらの症状が急速に進行した場合,筋肉痛,関節痛,リンパ節炎,情緒不安などを起こす.さらに,髄膜炎,アンギナ,呼吸困難などの循環器症状,発作といった合併症を起こすことがある.これらの症状のほとんどは,B. bacilliformis の赤血球内への侵入と増殖に関連したものである. カリオン病はB. bacilliformis によって起こるペルーイボ病,オロヤ熱などの症候群をいう.ちなみに,本病名はペルーイボ病の研究中に本症で死亡したペルーの医学生Daniel Carionにちなんで付けられたものである. 近年,齧歯類を病原巣とするB. grahamii のDNAが視神経網膜炎を起こした患者の眼房水から検出されたことから,本菌が人に対しても病原性を有することが示唆されている[51].しかしながら,本症例の感染経路は明らかにされていない. |
| V.動物のBartonella 感染症 | ||
| B. henselae に感染した猫は長期間の菌血症を起こすが,通常,臨床症状は示さない[19, 36, 75].猫を実験的にB. henselaeに感染させた場合,2〜3週間で菌血症(菌量:3〜106FU/ml)に達し,2〜3カ月間持続する[19,
36].自然感染した猫では1〜2年もの間,菌血症が持続した例も報告されている[48, 56]. Breitschdwertら[10]は,輸血によりB. henselae を実験的に感染させた二匹の猫に48〜72時間の発熱,一過性の神経機能障害が生じたことを報告している.また,O' Reillyら[72]は,自然感染猫から分離したB. henselae(LSU株),LSU株実験感染猫の血液,ならびにLSU株実験感染猫を吸血させたノミの糞をそれぞれ他の猫に皮内投与したところ,いずれの猫も傾眠,発熱,食欲不振などの臨床症状を示したことから,B. henselae の株によっては猫に病原性を示すものがあると思われる. われわれの研究では幼猫や成猫からはB. henselae は分離されたが,新生猫からは分離されなかったことから,猫では本菌の垂直感染は起こらないものと思われる(表5).
B. clarridgeiae は猫が自然病原巣であるが,猫に対する病原性は確認されていない.Chomelら[24]は,B. clarridgeiae を犬の心内膜炎の病変から分離し,本菌は犬に対しても病原性を有することを明らかにした. 近年,peliosis hepatisを呈した犬の肝臓からB. henselae のDNAが検出され[53],またリンパ節炎,血小板減少症,運動失調,貧血,痩削を呈した犬の血液からB. elizabethaeあるいはB. henselaeのDNAが検出されたことから[70],これらのBartonellaは犬に対しても病原性を有するとともに,犬が猫と同様本菌の病原巣となる可能性が示唆されている. その他のBartonella 属菌の動物に対する病原性は不明である. |
||
| VI.お わ り に | |
| 現代社会において最も多くみられるBartonella 感染症であるCSDのわが国での診断数は,他の人獣共通感染症に比べても多いにもかかわらず[89],届け出の義務がないため,その患者の実態は依然として不明の状態である.近年,“猫ひっかき病”とはいうものの,発症に猫が関与していない事例や犬が関与した事例なども報告されており[50,
87, 95],さらにその病態もさまざまであることが明らかとなってきた.したがって,猫ひっかき病はBartonella 感染症の病態の一つとして位置づけるとともに,その名称についても検討する時期が来ているようにも思われる. 現在,19種3亜種のBartonella 属の菌が報告されているが,いまだ人や動物に対する病原性が不明なものも多い. 今後,新種のBartonella 属菌が発見されてくる可能性もあり,それらの病原性ならびにCSDをはじめとするBartonella 感染症の疫学を明らかにしていく必要があると思われる. 謝辞:本論文に掲載した研究の一部は文部科学省の科学研究費(No. 10660307およびNo. 6604)により行われた. |