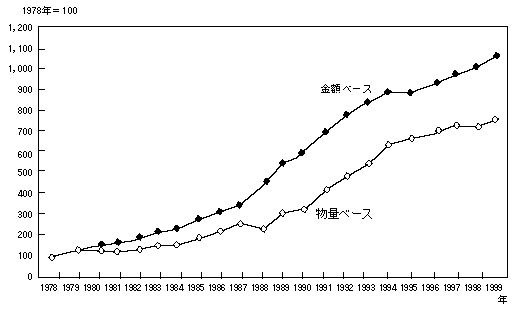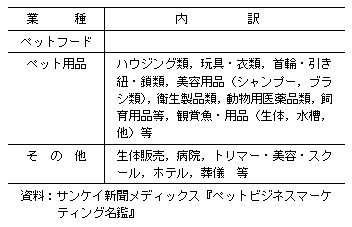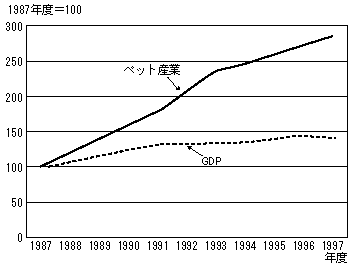近年,日本は核家族化の進展の中,少子高齢化社会が到来し,厚生労働省の『国民生活基礎調査』によると,2000年には1世帯あたり平均世帯人員数は2.76人と,3人を割り込む状況となってきている.「1人世帯」,「1世代世帯」の割合も大きくなり,児童のいる世帯割合は減少傾向にある.そんな家族構造の変化の中,ペットが家族の一員の役割を果たし,家族のつながりを強化するなど,これまでの家庭内での人間との関係が大きく変貌を遂げてきている.
畜犬登録頭数は1990年代より大きく上昇し,調査機関により数値は異なるが,ペット飼育率も上昇傾向にあり,最近では全国レベルで30%後半となっている.また,飼育動物の種類も,世話の手間や費用がかかるにもかかわらず,近年では犬や猫,またそれにとどまらず直接触れあい,コミュニケーションのとることのできる動物を選択する傾向がみられる.
総理府『動物保護(2000年は愛護)に関する世論調査』によると,ペット飼育をしている人で,「気持ちがやわらぐ(まぎれる)から」という飼育理由の回答を時系列でみると,1986年には21.6%,1990年が27.9%であったが,2000年には46.2%と急上昇している.
また,家計で「教養娯楽費」に含まれるペット関連費用は,1990年代の動きをみると,教養娯楽費品目の中ではパソコンに次ぐ急速な伸びを示している.
これら消費者側の変化に対し,供給側であるペット産業,また動物病院はどのような状況にあるのであろうか.本稿では最近の動きをいくつかのデータを用いて示していくこととする. |
1)ペット産業
| |
ペット産業についての市場規模はいくつかの機関により調査されているが,その公表数値にはかなりのばらつきがみられる.ここでは,比較的時系列で推移をみることができるサンケイ新聞メディックス『ペットビジネスマーケティング名鑑』のデータを取り上げて,ペット産業全体を概観していくこととする.この調査結果によると,その市場規模(売上高ベース)は,1987年度が3,310億円であったのが,1997年度には9,440億円となっており,10年間で約3倍近い伸びを示していることがわかる.ペット産業を構成する業種は,「ペットフード」,「ペット用品」,「その他」と大きく3つにわけられている(表1).この3つの業種別シェアは,1997年度には「ペットフード」が37.4%,「ペット用品」が30.4%,「その他」32.2%という数値になっている.この他,ペット産業のカテゴリーには含まれていないが,ペット関連の出版事業,ペット可マンションや住宅関連事業,またペットとともに宿泊できる施設等,近年では次第に浸透してきている業種もある.これらはペットをキーワードとして売上額に貢献している部分があることは明らかであるが,直接どれほどのデータがペット関連に含まれるかは,残念ながら把握することはできない.しかし,ここで1例をあげたように大きく影響を受けている業種は数多くあり,また以前は存在していなかったペットの医療共済制度などの新規商品やサービスの増加を含めると,市場規模は数倍に及ぶものと想定できる.図1では,ペット産業の市場規模を,1987年度から1997年度までの10年間の名目GDP(国内総生産)の推移と比較してみる.1987年度を100とすると,ペット産業は1987年度から1990年度まではバブル景気の影響を受け,各年ベースになおすと20ポイント,GDPは7〜8ポイントずつ伸びていた.しかし,1991年度を契機にしてバブル崩壊後,GDPが1〜2ポイントずつの上昇で伸び悩んでいるのに対し,ペット産業の市場規模はそこから1993年度にかけ各年ベースでは30ポイントずつと急激に伸びており,その後1994年度以降もコンスタントに成長を続けていることが読み取れる.
1997年度の業種別の構成比をさらに表1の細かな業種でみていくと,「ペットフード」が最大のシェアとなっている.次いで,「その他」の中の生体販売,「ペット用品」に含まれる観賞魚・用品が続いている.動物病院はここでは「その他」に含まれ,ペット産業全体の13%のシェアを占めている.ただし,総務庁(現総務省)統計データの「獣医業」収入総額と,この『ペットビジネスマーケティング名鑑』データとを対比し検討すると,動物病院の構成比はより大きな割合となっている可能性がある. |
|
|
![]()