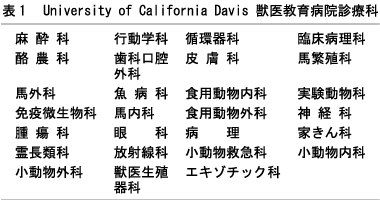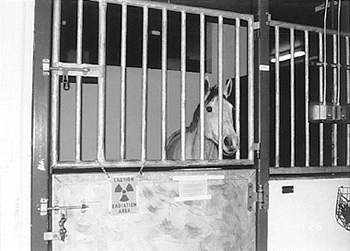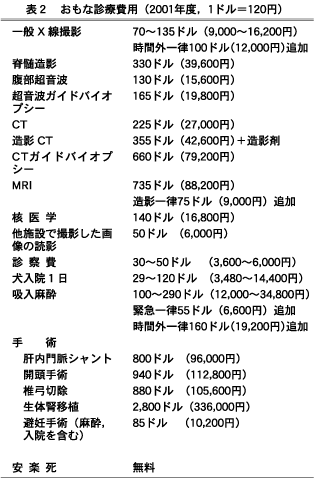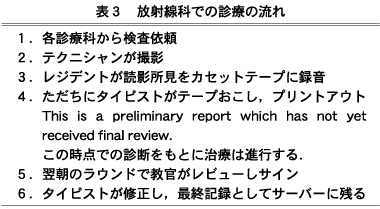資 料
アメリカにおける獣医学教育(文部科学省在外研究員留学報告)
山田一孝(帯広畜産大学畜産学部獣医学科)
| 文部科学省在外研究員として1年間アメリカのUniversity of California, Davis(UC Davis)に留学する機会を得た.アメリカでの1年間は,本来研究に専念するために与えられた時間ではあったが,アメリカの獣医学教育や臨床の現状について垣間みる機会にも恵まれた.研究成果は学術論文で報告することとして,本稿では,私が見たアメリカにおける獣医学教育について紹介したい. |
| University of California, Davis, Veterinary Medical Teaching Hospital(獣医教育病院) | |
| UC Davis獣医教育病院には27の臨床講座(表1)があり,診療業務を担当している.教官約100人(後述するがマンパワー約50%が診療業務に従事),レジデント(有給研修医)約80人,テクニシャンおよび事務職員は約250人,総勢400人以上から構成される病院である. 獣医教育病院案内の冒頭に,「本獣医教育病院は教育と研究を目的としており最高の治療を提供しますが,費用と時間を要します.診療費用は開業医と比較して安くはありません.」と述べられている.年間の診療頭数は犬13,500,猫3,300,馬4,900,エキゾチック1,200,その他(牛,山羊,羊,豚)1,500頭で,2000年度の売り上げは15,917,207ドル(約19億円)である.病院運営費の65%を病院独自の売り上げで賄い,35%についてカリフォルニア州からサポートを受けている.UC Davis獣医学部では,基礎獣医学の教官が約90人,臨床教官が約100人である(帯広畜産大学は基礎教官が18人,家畜病院専任教官を含め臨床が14人).基礎の教官も獣医教育病院から材料の提供を受けるため,獣医教育病院との関わりが深い.このことからも,UC Davisの獣医学部は,基礎,臨床にかかわらず獣医教育病院を中心に物事が進んでいる. カリフォルニア州の面積は日本とほぼ同じで,人口は3,200万人(日本の約1/4)である.カリフォルニア州唯一の獣医学部のあるDavis市の人口は6万人.いわゆる地元とはYolo county(帯広でいう十勝)で,人口は15万人.帯広畜産大学のある帯広市とほぼ同じ規模である.受診動物はYolo countyから約45%,Davis市内からが約30%である.まれに州外からの受診動物もいたが,半分近くは地元の受診動物である.Yolo countyには22の開業医があるが,大学病院における受診動物のほとんどが開業医からの紹介であることからも,開業医と大学が競合することはない.診療はすべて予約制である.そのため暇な日や特に忙しい日がなくコンスタントに忙しい.毎日,平均して小動物75頭,大動物(馬)90頭が入院しており,診療科ごとに入院室を持つ.治療に際しては,まず獣医師から検査および治療費用の見積もりが提示される.血液検査,X線,超音波など検査費用についてクライアントは了解済みなので,積極的に検査ができる点で仕事はやりやすい.費用を理由に積極的な治療を渋るクライアントは大学病院ではご遠慮である. |
|
|
|
| 私が所属した放射線科は,X線,超音波,CT(図1),MRI(図2),核医学検査(図3)による診断を業務としており,教官6人,レジデント5人,テクニシャン9人,タイピスト(口述した読影所見をタイプする人)2人の計22人からなる組織である.放射線科で1日に扱う症例数は小動物X線40頭,小動物超音波20頭,大動物X線10頭,MRI 2頭,CT 3頭,核医学2頭ほどである.日本の大学の多くは獣医放射線学は外科の一部であるが,アメリカでは放射線科の役割が確立している.動物病院の求人広告にも,「放射線専門医求む!」といったものがよく見かけられ,放射線専門医は読影だけで生計をたてることができる. | |
|
|
|
|
|
|
| CTやMRIによる断層画像検査は日常の診療の一貫に組み込まれ,欠かさざる検査手段としての地位を築いている.これら検査により,脳腫瘍のルールアウトや前庭疾患と中枢神経系疾患の類症鑑別に利用されている.検査費用(表2)は日本の病院に比べると高額であり,頭部MRI検査は735ドル(麻酔費用除く)であるが,それでも毎日検査の症例がある.獣医教育病院の診療費用が高いことは,高度獣医療を期待するクライアントのみを対象とする結果でもある.避妊手術が麻酔,入院を含めて85ドルと低価格である理由は,教育目的で教官の監督の下で学生が執刀するためである.日本の大学附属病院と予算システムに違いがあるが,私が強く感じたことは高度獣医療にはコストがかかるということである.これだけのコストをクライアントに分担してもらうことで設備投資,人件費を補うことができ,高水準の獣医療を提供しているのである.税金で運営されている日本の大学附属病院が街の動物病院と価格競争をしていては,獣医学の発展は厳しい. | |
|
|
| 獣医教育病院ではレジデントの貢献が大きい.レジデントは,放射線科では放射線専門医を目指す4年間のプログラム(大学によっては3年)に在籍中の研修医である.初年度は小動物のX線読影と超音波,2年目で大動物の読影と核医学,3年目でMRIとCT,最終学年で画像診断全般を担当する.5人のレジデントは交替で夜間と土日の当番をもつ.さて,放射線の時間外当番とは何をするのであろうか? まさに緊急患者の読影をするのである.また,レジデントは診療ばかりではなくマンパワーの20%の研究テーマも持つ.レジデントは専門医の資格試験にむけよく勉強するし,それにもまして感心することは,ここUC
Davis獣医教育病院では,獣医師免許をもったレジデントを4年間飽きさせないだけの症例数と知識の泉がある.これは,何よりも教官がレジデントに教え続けるだけの勉強をしているということに他ならない. 放射線科の一日は朝8時の「ラウンド」と呼ばれる症例検討会から始まる.ラウンドで前日のレジデントの読影所見が教官のレビューを受けて最終記録となる.複数の教官が検査結果に目を通すことで誤診の可能性が低くなる.レジデントは昼休みもとらず5時まで座ることなく働く.そして夕方5時にパタリと診療を終え速やかに当番へと切り替わる.毎朝のラウンドの他に,週1回読影練習会が開催される.放射線科専門医とレジデントの総勢11人がそれぞれの解釈について議論する場は壮絶である.放射線の専門医でありながら常にブラッシュアップの機会にさらされている. 放射線科での診療の流れを表3に示す. |
|
|
|
| 記録(臨床経過,検査結果,請求額,見積額,支払い状況)はすべてひとつのサーバーで一括管理されており,病院内はもちろんパスワードさえあれば自宅からでもインターネット回線を介して情報をみることができる.記録はクライアントからの要求があればクライアントに手渡す.記録の最後には「かわいいドロシーはとても協力的でした.私たちはドロシーのことが大好きです.もし今後何か問題があったら遠慮なく連絡して下さい」「ラッキーを助けることができなくてとても残念です.今回は私たちを信頼してくれてありがとうございました.」といった文章で締めくくられる. 日本の大学附属家畜病院で学生がこなしている雑用をUC Davis獣医教育病院ではテクニシャンが行う.ここでは学生はお客様で学生のマンパワーは期待されていない.つまり,学生がいないと撮影ができなかったり,学生の授業が終わるのを待って脊髄造影を行うことはない.日本の大学病院の現状ではX線写真現像,血液検査や調剤は学生が,ときには教官が行う.本来であれば学生は勉強に,教官は教官でなければできない仕事に専念するべきである.診療においても役割分担が確立しており,獣医師がテクニシャンの仕事に手を出すことはない.撮影はテクニシャンの仕事,獣医師は読影が仕事である.もうひとつの役割分担として脊髄造影に際して撮影と読影は放射線科で,脊髄腔穿刺は神経科で,麻酔は麻酔科で行う.放射線科医は読影に専念し直接動物を診ることはない.役割分担という考え方が徹底していることは,サッカーよりもアメリカンフットボールが盛んなこの国ならではであろう.プロ野球でいう指名打者制度もアメリカらしい発想である.MRIおよびCTの際も麻酔は麻酔科が担当するため,放射線科の獣医師は麻酔に対して責任を負わず読影に専念できる.医学部をみれば明らかであるが日本の獣医学にも麻酔科医は必要である.動物だから麻酔にマンパワーを必要としない理由はなく,日本の獣医学領域に麻酔の専門医の導入を提案したい. 実に不思議なことにアメリカの犬はおとなしい.従順でよく命令を聞く.X線撮影では「Come On」といって撮影台を叩くと犬は撮影台に飛び乗るし,「Stay」と命令すればじっとしている.信じられないが本当の話である.ほとんどの症例は鎮静を必要とせず,人の力で抑えることもなくサンドバックで保定するだけであった.超音波検査では20分もの間仰臥でおとなしくプローブをあてさせる.講義室のドアには犬立ち入り禁止のサインがある.それでも授業にはいつも犬がいる.犬も吠えることなくおとなしく授業を聞いているのである.多くの家庭で犬か猫が飼われており(人口当たりの犬・猫の飼育数は日本の約5倍),動物に対する思い入れは格別に深いようである.ケーブルテレビにはペットチャンネルたるチャンネルがあり,日本でいう「動物病院24時」のような番組が一日中放映されていた.さらに,アメリカでは獣医師の社会的地位も高く報酬もよい.カリフォルニア州における小動物病院の新卒獣医師の年収の相場は4万ドル(480万円),10年目の勤務獣医師で8万ドル(960万円)とのことである.教育に要した費用とクライアントに対する責任を考えると当然のことであろう.アメリカに来た当初は,「なぜ日本とアメリカの獣医学はこれほど違うのか?」について頭を悩ませたことがあった.クライアントの治療に対する積極性,犬の態度,後述する学生の勉学態度,獣医師の社会的地位,何から何まで違うのである.これは国政によるものばかりではなく,文化的な差によるところも大きい. |
|