乳牛の新しい繁殖管理法と繁殖効率改善の戦略
Novel New Concepts for Reproductive Management and Strategies
to Improve Reproductive Efficiency in Dairy Cattle
WW Thatcher1), F Moreira1), J Santos2) and R Mattos2)
| 1) | Department of Animal Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA |
| 2) | Veterinary Medicine Teaching and Research Center, University of California-Davis, Tulare, CA 93274, USA |
現在の酪農生産システムにおいて牛群の妊娠率を維持することは,大規模化や個体管理の困難な飼育形態に,乾乳および泌乳期の栄養要求に応じた栄養管理の複雑さが加わり,難しい問題となっている.妊娠率低下にはこうした複数の要因が関与しているが,中でも最近の発情発見率の低下は,妊娠率低下の大きな要因となっている.このため,ホルモン処置により排卵時期を制御して,発情発見によらず,定時に人工授精を行う定時人工授精(timed
artificial insemination : TAI)は,妊娠率向上につながる新たな繁殖管理法としてその効果が期待されている.しかし,一方では,TAIの処理に用いられるホルモンの働きや,生殖生理に対する理解不足からその効果を十分に引き出せていない例もみられる. |
|||
現在,泌乳牛の生殖機能調節にはプロスタグランジンF2α(PGF2α)製剤と性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)製剤が広く用いられている.PGF2αは黄体を退行させる働きをもつが,発情後1〜5日目の発育途上にある黄体に対しては無効である.GnRHは脳下垂体から黄体形成ホルモン(LH)および卵胞刺激ホルモン(FSH)を分泌させて,成熟卵胞を排卵させ黄体形成を促す働きと,新たな卵胞の発育を開始させる働きがある. GnRHの投与により新たな主席卵胞を発育させ,その7日後にPGF2αを投与すると発情が誘起される[7].このPGF2α投与後にGnRHを追加投与すると,一定時間後に排卵を誘起できる[11].この処理法は,排卵を同期化し定時人工授精を可能にするOvsynchプログラムとして知られている[10].TAIの受胎率は通常の発情発見による人工授精と同等とされているが[14],現在もこのシステムを至適化する努力が続けられている. 図1は,発情後5日目(月曜日,午後5時)に最初のGnRHを投与してOvsynch処理を開始し,TAIを実施した例の,黄体機能を示すプロジェステロン濃度変化と,典型的な卵胞発育の様子を示したものである.処理開始時の卵巣にはGnRHによるLH分泌に反応して排卵する正常な主席卵胞が存在している.GnRHによるFSH濃度の上昇は,約2日後(発情周期7日目)に卵巣での新たな卵胞群の発育開始を誘起し,やがてこの中から1つの卵胞が選抜され主席卵胞へと発育する.次いで,GnRH投与時に存在していた黄体およびGnRH投与後新たに形成された黄体を退行させるために,発情後12日目(GnRH投与後7日目,月曜日,午後5時)にPGF2αを投与する.新たに選抜された主席卵胞は,黄体退行に伴うプロジェステロン濃度の低下により発育が加速し,PGF2α投与から2日目(水曜日,午後5時)に2回目のGnRHを投与すると,その投与から24〜32時間後に排卵する[11].そこで,GnRH投与から約16時間目(木曜日,午前9時)にTAIを実施すると,精子には受精能を獲得するのに十分な時間が与えられ,排卵時には受精,すなわち妊娠開始に必要な受精能を持つ精子が存在することとなる. |
|||
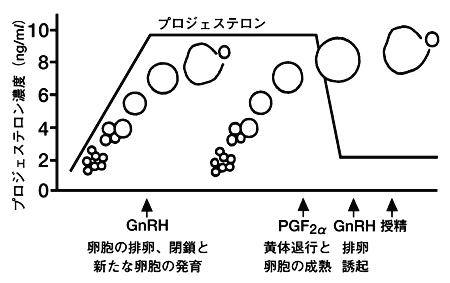
|
|||
| 以上はOvsynch/TAIの理想的なシナリオであり,このプログラムの成功には各処理が正確なタイミングで実施されることが不可欠である.例えば,1回目のGnRHとPGF2αの投与間隔を7日間よりも短くすると,PGF2αはGnRH投与により新たに形成された黄体を確実に退行させることができない.また,2回目のGnRH投与がPGF2α投与から48時間より遅れた場合,多くの牛でGnRH投与前に発情が発現してOvsynchプログラムのスケジュールから逸脱し,受精のタイミングは誤ったものとなる.このように,Ovsynch/TAI実施にあたっては忠実にそのプロトコールに従うことが重要である.作業上の利便性から,GnRH投与時あるいはその24時間後に授精できないかという質問が多く寄せられるが,授精適期はGnRH投与後12〜18時間であり,GnRH投与と同時あるいは投与後24時間目の授精では受胎率は低下する[12]. OvsynchによるTAIの成功は,対象となる牛が正常な発情周期を回帰していることと,処理を開始する発情周期のステージに依存する.Ovsynch処理は発情を回帰していない牛でも発情を誘起し,時に妊娠に至る例もみられるが,対象となる牛群に発情を回帰していない牛がいる場合,牛群の受胎率低下は避けられない.この点については,後でもう一度触れることとする. 図2および3は,Ovsynch処理を開始するのに不適切な発情周期のステージの例を示したものである.図2は,正常な第2ウェーブの主席卵胞が発育している発情周期15日目にOvsynch処理を開始した牛の例である.第2ウエーブの主席卵胞は,処理開始時の卵胞の成熟度によっては排卵するものもみられるが,その多くは排卵するには小さすぎ,GnRHを投与しても排卵に至らず新たな黄体の形成はみられない.また,GnRH投与後2〜4日目には,子宮から分泌されるPGF2αにより黄体退行が誘起される.したがって,GnRH投与後7日目のPGF2α投与時にはすでに黄体は退行しており,中には発情を示すものもある[8].このような牛はOvsynchのスケジュールから外れ,予定よりも早期に排卵が起こるため,Ovsynch/TAIプロトコールに従って授精すると,授精のタイミングは遅すぎ,妊娠は成立しない. |
|||
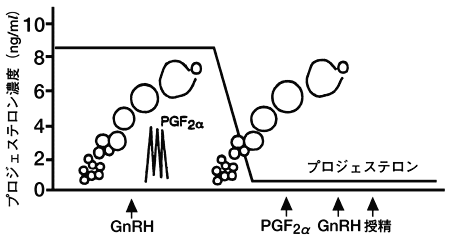
|
|||
| 図3は,黄体形成期(発情後2日目)にOvsynch処理を開始した例である.このシナリオでは,処理開始時の牛はすでに発情を終えて排卵しており,卵巣には新たな主席卵胞の発育がみられる.この時期の卵胞は小さく,GnRHを投与してもその発育は促進されないし,新たな卵胞の発育もみられない[8].この主席卵胞は2回目のGnRH投与時にはドミナントの状態になってすでに5日以上を経過しており,過熟状態にあると考えられる.ドミナントの状態になり5日以上を経過した卵胞を持つ牛[2],あるいはOvsynch処理を黄体形成期に開始した牛では受胎率の低いことが知られている[8].過熟卵胞の卵母細胞は受精能が低く,また,2回目のGnRH投与により排卵しない例もみられる. | |||
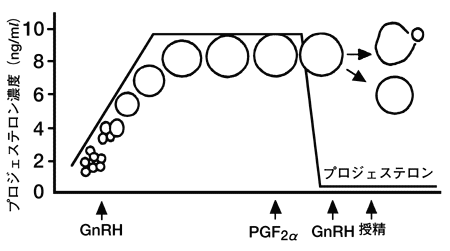
|
|||
| 表1は,Ovsynch処理開始時にすべての牛が正常な発情周期を示し,発情からの日数は均等に分散していると仮定して,Ovsynch/TAIによる妊娠率を試算したものである.便宜上発情周期の長さを20日間とすると,牛群の5%の牛が発情周期のそれぞれの日に分布する.100頭からなる牛群を想定し,それぞれ発情周期初期(黄体形成期,Ovsynch処理開始に不適),発情間期初期,発情間期後期(Ovsynch処理開始に不適)および発情前期にあたる牛の頭数および予想される受胎率を示している.この表から推定される牛群全体の受胎率は36%である. しかし,発情周期は人為的に調節することが可能である.その代表的な方法は,すべての牛にPGF2αを14日間隔で2回投与し発情を同期化する方法である.表2は,この発情同期化法の2回目のPGF2α投与から12日目にGnRHを投与してOvsynch処理を開始した場合に期待される,Ovsynch処理開始時の牛群の各ステージへの分布と受胎率を示したものである.すべての牛が正常な発情周期を示している場合,Ovsynch処理を開始する時点で,90%の牛は処理開始に適したステージ(発情後5〜10日目)にあると期待される.この場合に予想される牛群全体の受胎率は48%に増加する.このような同期化処理の実際の有効性については後に具体的な例をあげて検討する. |
|||
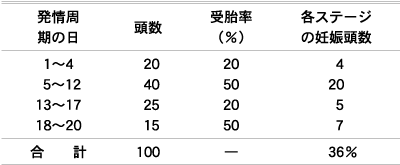 |
|||
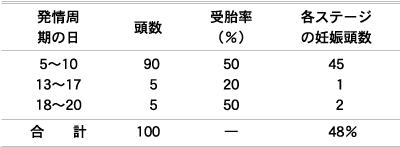
|