資 料
家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制
JVARM実施体制と役割分担 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| JVARM実施体制と役割分担を,抗菌剤使用量の調査と薬剤耐性菌調査に分けて説明する. 抗菌剤使用量の調査の実施体制は,図2のとおりである.まず,農林水産省生産局畜産部衛生課薬事室より各製造および輸入業者あてに報告書の指示が発出される.報告対象期間は,毎年1月1日から12月31日である.業者は,所定の報告書を翌年の2月末までに薬事室に提出し,報告内容について動物医薬品検査所で集計・分析される.最終的に,生産局から正式な報告書「動物用医薬品,医薬部外品,生産(輸入)販売高年報」として毎年出版される.調査項目は,前述した通り平成12年から活性成分の使用量を基本としている. |
||||||||||||||||||||||||||||||
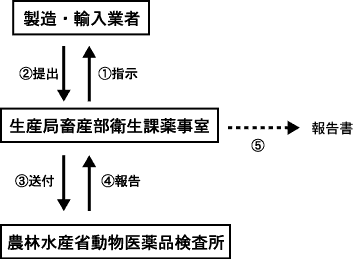 図2 抗菌剤使用量調査の実施体制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 次に,薬剤耐性調査の実施体制について述べたい.全国には187カ所の家畜保健衛生所があり,各都道府県当たり平均4カ所あることになる.このような家畜保健衛生所の絶大な協力により,全国隈なく張り巡らされたJVARMネットワークが構築された.まず,野外流行株であるが,これは家畜保健衛生所が分離・同定したものを,毎年指定した菌種を動物医薬品検査所に送付する.動物医薬品検査所では,MICを測定し,その他の性状検査等を実施する他,分離菌株の保存も行っている.一方,食品媒介性病原細菌と指標細菌については,家畜保健衛生所で対象家畜から糞便を採取し,菌分離・同定を行う(図3).分離菌については,家畜保健衛生所でMICを測定し,疫学情報とともにMIC成績を動物医薬品検査所に送付する.動物医薬品検査所では,送付された成績を集計,分析し,薬剤耐性株を地域ごと,年度ごとに保存している.また,薬剤耐性株については,分子疫学的調査を実施するため遺伝学的性状の解析,薬剤耐性機構の解明等を実施する.さらに,試験法の確立,ブレークポイントの設定,MICの精度管理用参照株の配布,研修会の開催等を行っている.したがって,動物医薬品検査所はJVARMの中央ラボラトリーもしくはリファレンスラボラトリーの機能を有している.なお,抗菌性飼料添加物については,独立行政法人 肥飼料検査所で分析等を実施している.得られた成績は,生産局畜産部衛生課薬事室および飼料課に報告され,必要な場合は何らかの行政措置を講じる場合もある. |
||||||||||||||||||||||||||||||
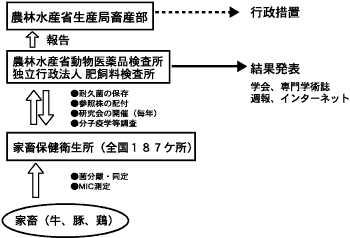 図3 食品媒介性病原細菌と指標細菌の薬剤耐性調査実施体制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| なお,動物医薬品検査所では,検査第二部抗生物質製剤検査室の全スタッフがこの業務を担当する他,さまざまな面で全所を挙げてこの業務をバックアップしている. |
||||||||||||||||||||||||||||||
JVARM品質保証システム |
||||||||||||||||||||||||||||||
| JVARMでは,全国の多くの家畜保健衛生所が実施施設として参加している.したがって,それぞれの技術力の差が成績の精度に反映されるため,試験技術の平準化を行うことが,システムの信頼性の確保に最も重要である[10].そこで,JVARMの品質保証システムとしては,分離株のMIC測定に当たって同時に複数のMIC精度管理参照株について実施することを要求しており,参照株が指定された規格値の範囲にある場合のみ,MICの測定が可能とされている.また,各家畜保健衛生所の試験技術の熟達度を確認するため,MIC値を伏せた菌株を配布し,その成績も求めている(熟達度確認試験).既定MICの範囲から逸脱している場合は,技術上の何らかの問題点があると判断される. また,対象菌種の分離・同定法やMIC測定法の平準化や最新の薬剤耐性菌情報の交換を目的とした研修会を年1回動物医薬品検査所で開催し,モニタリング実施上の問題点を解決している. |
||||||||||||||||||||||||||||||
成績の公表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング成績の内容次第では,早急な対策を講じる必要もあることから,成績がまとまればできるだけ早い時期に公表することを心がけている.公表の方法としては,最も早い時期に生産局畜産部衛生課発行の“家畜衛生週報”に関心の高い食品媒介性病原細菌と指標細菌の調査概要を報告している[6].また,動物医薬品検査所のホームページ(http://www.
nval. go. jp)でも広く情報を公開している.さらに詳細の成績および解析結果は,関連学会,学術誌[7]にも積極的に発表し,国内外の研究者,政府機関,臨床獣医師および製造(輸入)業者等に情報を提供している. |
||||||||||||||||||||||||||||||
お わ り に |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回,わが国初の全国的な家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制の現状について紹介した.すでにご紹介したように,わが国の薬剤耐性モニタリング体制は,OIEガイドライン[2, 3, 10]にほぼ準拠したものである.JVARMについては,第2回OIE薬剤耐性国際会議(2001年,パリ)でも紹介し,世界的にも類を見ない組織的なモニタリング体制と高い評価を受けた.しかし,発足からまだ日も浅く成績の集積がないとともに課題も多く残されている.まず,システムとしてであるが,食用動物由来薬剤耐性菌のヒト医療に及ぼす影響を明らかにするのであれば,食物連鎖を構成するすべてを調査対象とすべきである.OIEガイドライン[2]でも述べられているように,養殖魚,野菜,食品等を如何にこのシステムに組み込むかが今後の課題となろう.さらに,先進のモニタリング体制であるDANMAPやNARMSではすでに構築されているところであるが,薬剤耐性菌対策の一環として実施するのであれば,家畜衛生のみならず食品衛生,医療をも包含したモニタリング体制が必要である.近い将来,JVARMからJARM(Japanese
Antimicrobial Resistance Monitoring System)に発展することを期待したい. 次に,方法論についても言及したい.現在モニタリングに使用されているMIC測定法は,わが国独自の方法である.WHOやOIEの国際会議では,国際間でのモニタリング成績の共有化が議論されており,国際間で比較可能な方法によるモニタリング手法の確立が要求されている.MIC測定法のゴールドスタンダードといわれる寒天平板希釈法においても,諸外国とわが国の標準法に差異があり,早急なMIC測定法の見直しが必要に思われる. 以上述べてきたように,いろいろな点において改良の余地はあるものの,全国を網羅した家畜衛生分野での薬剤耐性モニタリング体制が確立したことは,薬剤耐性菌を制御する対策の第1歩を踏み出したことであり評価できるものと自負している.畜産は,農民の育成と消費者の保護という同調可能なバランスの上に成り立っているが,時としてこの均衡が崩れた時に大きな歪みが生じる.動物用抗菌性物質は,畜産において必要・不可欠の資材である反面,その誤用や過剰使用は薬剤耐性菌の増加につながるものである.この両刃の剣を巧みに操る道標として,JVARMの存在意義があるように思われる. 最後に,OIEは薬剤耐性モニタリングを,「あるポピュレーションとその環境における薬剤耐性の蔓延の変化を検出することを目的にする進行中のプログラム」と定義し,長期間にわたる調査とした.これは,期間限定のサーベイランスとは明らかに異なるものである.したがって,JVARMも末永く調査を継続することにより,わが国の薬剤耐性菌対策の要としてさらに発展することを期待している. 多忙な業務の傍ら,JVARMの意義を理解して絶大なご協力をいただいている全国の家畜保健衛生所の皆様に深甚の謝意を表したい.また,分離された薬剤耐性菌の各種性状解析については,国立感染症研究所と東京都衛生研究所および動物衛生研究所のご指導・ご協力を得ており,この場を借りて感謝申し上げたい. |
||||||||||||||||||||||||||||||
引 用 文 献
|