資 料
家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制
田村 豊 高橋敏雄 守岡綾子 石原加奈子 菊間礼子 農林水産省動物医薬品検査所 (〒185-8511 国分寺市戸倉1-15-1) |
||||||||||
は じ め に |
||||||||||
| 家畜衛生分野における最初の全国的な薬剤耐性調査は,昭和51年度および昭和52年度に農林水産省畜産局が実施した実態調査[5]に遡ることができる.当時,食用動物由来薬剤耐性菌の公衆衛生への影響が盛んに議論されており,抗菌性物質の畜産物への残留や薬剤耐性菌の増加による公衆衛生への影響を配慮した「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和51年施行)が成立した時期であった.そこで,同法に基づく規制前後の薬剤耐性菌の実態を把握することを目的として,薬剤耐性調査が実施されたものであった.その後,数次にわたり全国的な調査が行われたが,いずれも単発的[4,
9]であり継続的な調査は実施されていなかった. 最近,世界保健機関(WHO)は,ヒト医療における薬剤耐性菌問題の原因が食用動物に抗菌性物質を使用することにあるとの観点から,食用動物における抗菌性物質の使用を禁止もしくは制限しようとするキャンペーンを展開している[8].しかし,これらの会議では,ヒト由来薬剤耐性菌の出現と食用動物への抗菌性物質の使用との因果関係の実証に至らなかったが,その一因として食品媒介性病原細菌の薬剤耐性に関する科学的なモニタリング情報の欠如が挙げられた.一方,家畜衛生の専門国際機関である国際獣疫事務局(OIE)は,家畜衛生および公衆衛生上問題となる薬剤耐性菌を制御するための戦略の一つとして,国際的に比較可能な薬剤耐性モニタリングの重要性を指摘した[2]. 現在,家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制としては,欧州連合(EARSS; European Antimicrobial Resistance Surveillance System),WHO(WHONET; WHO Network on Antimicrobial Resistance Monitoring),デンマーク(DANMAP; Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme),米国(NARMS; National Antimicrobial Resistance Monitoring System),スウェーデン(SVARM; Swedish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring)等で機能的に活動していることが知られている. そこで,このような薬剤耐性菌をめぐる国際動向を背景として,わが国では,平成7年度から製造物責任法対応として実施していた家畜病原細菌の薬剤耐性調査に加え,平成11年度から健康動物由来食品媒介性病原細菌および指標細菌の全国的な薬剤耐性調査を開始した.さらに,平成12年度からは,畜産振興総合対策事業に基づき全国の家畜保健衛生所の全面的な支援をうけ,全国的な薬剤耐性ネットワークを構築することができた.そこで今回,わが国の家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング体制の現状について紹介したい. なお,本モニタリング体制は,対外的にJVARM(Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring System)と呼称している. |
||||||||||
JVARMの目的 |
||||||||||
| JVARMの目的としては,以下の項目が挙げられる. | ||||||||||
|
||||||||||
JVARMの概要 |
||||||||||
| JVARM実施内容の概要を図1に示した.図に示されている通り,JVARMは大きく分けて3つの調査から成り立っている. | ||||||||||
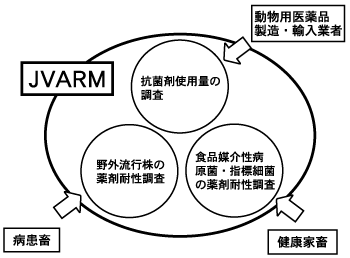 図1 JVARMの概要
|
||||||||||
薬剤耐性調査内容 |
||||||||||
薬剤耐性調査内容の概要を表1に示した.まず,野外流行株の調査であるが,毎年,病性鑑定材料から分離・同定した菌株を寒天平板希釈法により最小発育阻止濃度(MIC)を測定している.一方,食品媒介性病原細菌と指標細菌の調査では,47都道府県を偏りが生じないように4群に区分けし,各都道府県とも肉牛,豚,肉用鶏,採卵鶏の各6経営体(飼料添加物についても実施する場合は8経営体)から,1経営体1サンプルの糞便を採取し,指定された菌種を2株分離する.この時,指示された全国一律の方法に準拠して対象菌種を分離し,同定する.サルモネラ,STECおよびカンピロバクターについては,血清型も調べることとしている.採材に当たっては,本モニタリングの目的がリスク分析の基礎資料を提供することも含まれているため,サンプルの由来農場,規模,採材日,治療用抗菌剤および抗菌性飼料添加物の使用状況等の疫学調査もフォーマットに従ってあわせて実施することになっている.分離された菌株については,操作性,経済性等を勘案して一濃度ディスク拡散法により推定MICを求めている. |
||||||||||
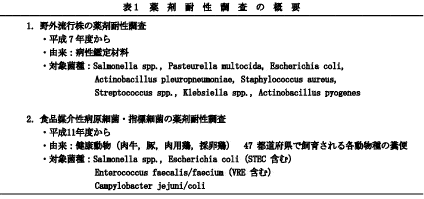 |
||||||||||
| なお,対象となっている抗菌性物質は,Enrofloxacine、Ofloxacin、Ceftioful、Virginiamycin、Ampicillin、Oxytetracycline、Chloramphenicol、Streptomycin、Sulfadimethoxine、Colistin、Nalidixic
acid、Apramycin、Bicozamycin、Cephazorin、Trimethoprim、Cefuroxime、Gentamicin、Kanamycin、Oxolic acid、Erythromycin、Tylosin、Bacitracin、Spectinomyin、Spiramycin、Lincomycin、Vancomycin、Avilamycin、Salinomycin、Nosiheptide、Destomycin-A、Efrotmycin、Olaquindoxの32成分で,動物専用抗菌剤,人体兼用抗菌剤,抗菌性飼料添加物等で重要と思われる成分はすべて網羅されている.これは,過去の調査およびOIEガイドライン[2]に準拠して,菌種ごとに対象抗菌性物質を指定している. |