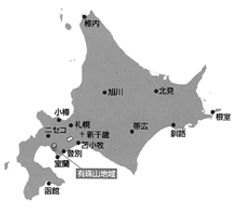紹介
有珠山噴火災害とNOSAI家畜診療所の対応
佐藤時則(北海道農業共済組合連合会・家畜部)1.は じ め に |
|||||||||
| 2.噴火の経過 平成12年3月下旬から火山活動が活発化し,3月29日には最大震度5弱を始めとした火山性地震が急速に増加するなど一段と噴火の危険性が高まったことから,虻田町,壮瞥町,伊達市の3市町の危険地区に対して避難指示が出され,31日までに3市町約12,000人(総人口の2割強)の住民が避難を完了した.29日からは,避難指示地区を通 る国道,道道,そして高速道路が全面通行禁止となり,JRも運転中止し,警察・自衛隊の検問により同地区への立ち入りは事実上禁止された. その直後から火山性地震は一層活発になり,遂に3月31日午後1時10分に噴火が起きた(図2). 以後,西山の西側山麓と金毘羅山に火口群が出現し,大爆発や大火砕流,そして前回噴火時に見舞われた泥流災害の危険性も否定できない不安な状態が続いた(図3). 一方,最新鋭観測機器設置による観測体制整備や火山活動の沈静化の兆しを受け,危険度の低い地区の避難指示解除や時間限定の一時帰宅が順次進められた. 5月23日には,虻田町をはさんで東の伊達市と西の豊浦町を結ぶ国道37号線の昼夜通 行が可能となるなど,避難指示地区が徐々に縮小し,5月末には噴煙を上げる有珠山を背に待望の田植えも始まり,この段階で避難生活を余儀なくされた住民は約3,300人にまで減少した. そして,7月10日には前述の「終息に向かっていると考えられる」との統一見解が出され,7月28日には住居に不適な火口周囲を除き,避難指示が4カ月ぶりに全面 解除され,事実上,最後の避難指示解除となった. 10月に入った今,有珠山の遠望は一見穏やかに見えるが,温泉街の一番近いところからわずか数百mのところに開いた金毘羅山火口からは噴煙が400〜800mほど立ち上がっている.ゴーッという地鳴りとともに,断続的に噴石を放出する小規模な水蒸気爆発があり,その爆風による空気振動(空振)が数秒おきに玄関と窓ガラスをガタガタと震わす.風向きによってはいまだに大量 の降灰もある.このように噴火活動が継続していることから,火口直下の202世帯378人には避難指示が出されたままとなっており,半年間たった今なお,1,500人もの住民が不便な仮設住宅に住んでいる. しかし,火口周囲の地盤沈下が著明となり,徐々にマグマの活動が沈静化してきていることも確かである. |
|||||||||
|
|||||||||
| 3.避難指示地区内の家畜の動向 最大時の避難指示地区内には畜産農家が実45戸(加入38戸),鶏を除く家畜飼養総頭数2,660頭,うち大家畜(牛馬)1,101頭(加入1,069頭)がいた(表1). そのうち実15戸が家畜309頭を連れて避難し,長期間避難先で不自由な飼養管理を続けた.避難移動は,噴火直後の4月1日から開始し,4月7日までに完了した(表2). 農家の中には,「今まで生計を支えてくれた牛を見殺しにできない」,「500頭も乳牛を飼っているので避難場所がない,避難したら誰が搾乳してくれるのか」,「自分の命より馬が大事」などと避難指示に抵抗し残留する人もいたが,ほとんどの農家が説得に応じ,指定された短い時間の間に,JAの用意した家畜輸送車等で家畜を安全な避難場所に緊急搬出した. その後,6月7日には避難農家全戸の避難指示が解除されて帰舎が進み,6月19日現在で避難中なのは,酪農家1戸59頭だけとなった. 同農家は噴火口から1.5kmしか離れていない虻田町の杉上義弘さん(共済加入)で,噴火時は牛舎で牛の世話をしていた.避難指示は出ていたが,1日でも搾乳を休めば牛が乳房炎になるため逃げるわけにはいかなかった. 翌1日朝には牛舎前の道路に断層ができ,牛舎とサイロに亀裂が生じ倒壊する恐れも出てきたため,酪農家仲間の協力で,その日のうちにトラック6台で牛と家族を避難させた.避難先は農協が提供してくれた豊浦町の離農牛舎で,杉上さん一家はその日からその牛舎に住み始め,搾乳を再開した(図4). しかし,噴火と地震のストレスのため,発情が来なかったり,自家製サイレージを持ち出せなかったこともあって乳量 が2〜3割減少したほか,牛舎が狭く過密状態で下痢発熱等の症状を呈する牛が多くみられた.加えて,バーンクリーナーも動かず除糞作業に追われていたが,町内の仲間や近隣酪農家のボランティアなどの支援もあり,やっと,6月23日に全頭帰舎できた. 避難農家のほとんどが,杉上さん同様,牛と家族の移動で手一杯だったため,自家製粗飼料を持ち出せなかったことから,4月1日から農協が窓口となり友愛牧草の受け入れを行なった.その結果 ,4月26日までに道内7団体から118tの牧草ロールの提供があり,避難農家に届けられた.友愛牧草は量 的補充の緊急避難措置として大いに喜ばれたが,事態が長期化するにつれ,自家製粗飼料との栄養組成の違いもあり,一部酪農家では乳量 回復に向けた飼料給与上の苦労もあったようである. また,立ち入り禁止となり,農家だけがが避難したが,避難指示地域内の畜舎に取り残された家畜は,最大時7戸1,921頭(うち豚以外の大家畜140頭)に及んだ. 取り残されたことが直接の原因となった死廃事故は,共済加入家畜での発生はなかったものの,中小家畜(いずれも非加入)で発生し,2戸121頭の哺育豚・肥育豚(100頭は停電で哺育器の暖房が切れたため母豚に寄り添って圧死,21頭は2週間の立ち入り制限のため飼料給与不足で餓死)と鶏1戸1,573羽(停電で自動給水機が停止したことによる脱水等)が報告されている.(胆振家畜保健衛生所調べ) さらに,避難および帰舎の移動ストレスはもちろん,避難しなかった家畜も日々続く噴火の爆風と地震で少なからずストレスを受け,降灰による二次被害(呼吸器病,皮膚病,灰混入の牧草摂取等)も危惧された. しかし,病傷も含め,噴火との直接の因果関係が認められる共済事故は,現在まで発生していない. このように,農作業の遅れやストレスによる減乳などのほか,家畜の避難移動費,避難先牛舎の借上料,飼料代等の経済的損失はあったものの,家畜に対する直接の被害を僅少に抑えていることは特筆に価する. |
|||||||||
 図4 避難移動する乳牛(4月1日、村上氏所有牛) |
|||||||||