| 今 後 の 展 望
以上の記載のように,Q熱の疫学の一端が明らかになってきたが,多くの不明な点が残っている(図2).すなわち,(1)本菌は,自然環境,特にダニ類と野生動物・鳥類の間でどのように維持されているか,その生態学的解明,(2)本菌は,産業動物や伴侶動物などに健康な状態で保菌されているのか,繁殖障害など多様な病態を起こすのか,その病態学的解明,(3)人に多様な病態を示すことが海外で報告されているが,その中で最近注目されているうつ病や不定愁訴などとの関係,あるいは流産やSTDなどの病態学的解明,(4)食品(乳肉・卵製品)や血液製剤などの安全性に関する調査研究,(5)簡易診断技術の開発と普及,(6)医師をはじめ獣医師,国民への啓蒙などがある. 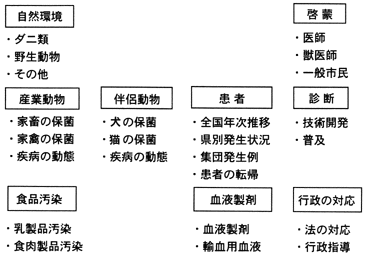 図2 今後の問題 ―疫学と対応― お わ り に 多様な病態を示すQ熱はわが国に広く存在し,まれな疾病でないことが明らかにされてきた.その背景には動物やその製品が深く関与していると推定される.動物のコクシエラ症は,経済的被害の多い他の伝染病の陰に隠され,排菌動物がいるにもかかわらず長い間見落とされている.動物の健康管理,食品の安全管理,環境整備などは獣医師の古くて新しいテーマであるが,臨床医師にも患者の診断・治療以外に感染源解明などの疫学的アプローチを期待したい.O-157のように,対応が後手にまわることなく,法的処置による早急な対応が望まれる.諸外国では市民や危険度の高い職業者を対象に不活化と生ワクチンが開発・実用化されている.最後に研究に協力いただいた多くの先生方に謝意を表する. |