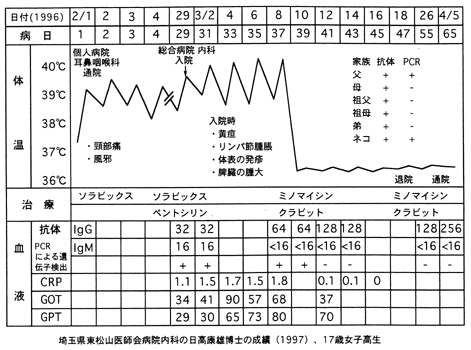| Department of Veterinary Microbiology, Faculty of Agriculture, Gifu University,1-1 Yanagido, Gifu
501-1193, Japan
日獣会誌 52 77〜83(1999)
は じ め に
Q熱(コクシエラ症)はリケッチアの一種であるコクシエラ菌(Coxiella burnetii)によって起こる人獣共通感染症で,1935年に発見された後,1940年代後半までに世界各国で患者が確認された.わが国では1950年代前半に人および家畜に抗体が低率ながら検出された.しかし,患者(患畜)や病原体が確認されず,本症はわが国に存在しないと考えられていた.1988年帰国直後の医学生の症例が報告されたのを契機に研究が開始され,わが国にもQ熱が広く存在することが明らかにされてきた.多くの症例では感染源が特定されていないが,動物が深く関与する症例も報告されてきた.患者は年間に相当数発生していると推定される.
本文ではQ熱の最近の知見と今後の展望について言及したい.なお,本誌やJ. Vet. Med. Sci.など[3-8]の総説も併せて参照されたい.
人 の 症 例
1988年帰国直後に発症した医学生の症例が報告された.これを契機に,著者らは内科および小児科医から依頼される症例を血清学的および病原学的に診断し,多くの症例が集積されてきた.以下に興味ある症例を示す(表1).
症例1:患者は17歳女子,平成8年2月1日より約1カ月間持続する発熱と頸部痛で個人の耳鼻咽喉科に通院.総合病院に入院時,黄疸,リンパ節腫脹,脾腫,体表発疹があり,入院7日目にミノマイシンに著効を示し,Q熱の疑いで埼玉県東松山医師会病院の日高医師から検査を依頼された(図1).IgM抗体は発熱期に16倍,IgG抗体は32倍,128倍,256倍と上昇し,血清からのPCRによる遺伝子検出も陽性を示したことから,Q熱と診断された.家族全員と飼育猫は症状がなく健康であったが,全員が抗体陽性,父親と猫の血清からも遺伝子が検出され,猫が感染源と推定された.もし仮にこの父親が献血すると血液製剤の問題が生ずるであろう.
症例2:患者は6歳男子,平成8年3月14日より高熱と頭痛が12日間持続.その後発語不明瞭と眼球左方偏位になり急性小脳炎と診断され,ミノマイシンに著効を示したことから,Q熱の疑いで秋田大学医学部小児科から検査を依頼された.急性期血清で抗体およびPCR陽性,髄液からC.
burnetiiが分離された[24].動物の飼育歴がなく,感染源は不明であるが,近所に酪農家がある.
症例3:患者は3歳男子,6カ月齢より原因不明の精神運動発達遅延で,平成8年4月より発熱,咳嗽,血症板減少などで1カ月間入・退院を繰り返し,持続性発熱と肺炎になりミノマイシンに著効を示したことからQ熱の疑いで,杏林大学医学部小児科から検査を依頼された.発熱期は抗体,PCRとも陰性であったが,回復期にはIF抗体256倍,PCRも陽性になり,Q熱と診断された.感染源は特定できなかったが,自宅のベランダでハトと遊びその糞を食べていた.
症例4:患者は23歳男子学生,1997年の夏休みにチベットとネパールを旅行,帰国1週間前より発熱と頭痛があり,帰国後都立墨東病院感染科に入院,肝臓機能障害も併発し,マラリア,デング熱,チフス,パラチフスなどが否定され,Q熱の検査を依頼された.入院2日目の血清は抗体価64倍でPCR陽性,入院10日目では抗体価128倍でPCR陽性,入院20日目ではIF抗体価256倍でQ熱と診断された.推定感染源は旅行中に飲んだヤクと他の動物の生乳および生チーズと考えられた.
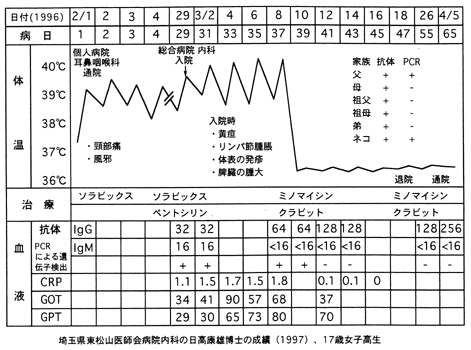
図1 Q熱(コクシエラ症)の熱型および治療経過
|