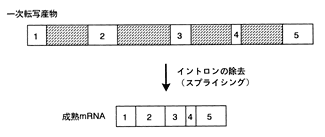| RNAはえらくなかった
さて,DNAを中心にした分子生物学の発展の中で,この小文の主題であるRNAとはどんな位置づけをされてきたのであろうか.RNAは,DNAと同様に遺伝情報となる塩基配列をもち,構造的に1対1でDNAに対応できる分子で,情報の質がDNAと異なるわけではない.ただ化学構造がほんの少し異なることにより,DNAと比べると非常に壊れやすい.遺伝情報を,この壊れやすいRNAにいったん移すというメカニズムは,遺伝情報を微妙に制御するには都合がよいと考えられる.すなわち,不必要になったときすぐに消えてくれることが期待できる.そしてまた必要になったときはDNAをお手本に合成すればよいのである.安定なDNAの上に情報自体はきちっと保持しておき,その情報を発現させたいときには壊れやすいRNAにするのである.蛋白質合成の直接の鋳型となるのはDNAではなく,この壊れやすいRNAであるというメカニズムは,遺伝子発現の調節という観点から,非常に合理的である.いずれにしても,DNAが支配し,その先兵である蛋白質が大活躍する生命の,その間で,すぐに消えてくれることを期待されていたRNAは,重要な役割ではあるものの生命活動という舞台の主役というわけにはいかなかった.おとなしいわき役としてのRNAは,1981年まで続く.寡黙な仕事人,RNAの役割をもう少し詳しく見てみよう.RNAの機能は,メッセンジャー(メッセンジャーRNA,mRNA)であり,アミノ酸の運搬人(転移RNA,tRNA)であり,リボソームの構造を支えるもの(リボソームRNA,rRNA)であった.いずれも,遺伝情報がDNAから蛋白質へ流れるための仲介役にしか過ぎず,能動的な蛋白質と比べれば常に受動的であり,生化学反応の表舞台に立つことはないと考えられていた.すなわち,細胞内の生化学反応を押し進めているものは蛋白質であり,化学反応ということを中心に考えれば,主役はいつも能動的な機能をもつ酵素蛋白質であった.いくつか機能不明のRNAも報告されていたが,蛋白質の圧倒的な機能の多彩さに比べれば,決して主役ではなく,いずれも蛋白質の機能を補助する役割しか期待されていなかった.RNAはえらくなかったのである. RNAの逆襲 RNAのまったく別の一面,ひょっとするとこれが真の姿かもしれないが,RNAの能動的な能力に初めて出合ったのはアメリカ・コロラド大学のThomas Cechである.この話に入るには少し時代をさかのぼる必要がある.
|