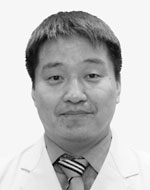![]()
|
大 学 教 育 と 国 際 協 力
― 北海道大学とザンビア大学の教育連携プロジェクトに参加して ―
奥村 正裕†(北海道大学大学院獣医学研究科助教授・北海道獣医師会会員)
| 今の日本では少子化が危惧され,大学入学者が年々減少する事態が続いている.幸い,獣医師を志す若者とそれを受け入れる大学の需給関係であろうか,獣医学部人気は衰えるどころか,入学選抜の激戦化が続いている.しかし,これからの大学を考えるとき,獣医学部においても少子化ということは避けて通れないファクターであることは間違いない. 一般に,教育の一番の魅力はそこに注がれた熱意と努力が次世代の人々に引き継がれ,そして何倍にも増幅されていくことである.一つの教育が将来に大きな足跡として後世に伝えられていくのである.そのことは大学人として働く時,とても大きな責任となり,また,やりがいとなる.しかし,私が未熟者であるからであろうか,それを実感できることは非常に少ないように思う. グローバル化する社会において,教育とは単に“国”という枠組みにとらわれず,人類すべてに貢献すべきものとして考えなければならなくなってきた.教育による知識の伝承は,少子化に苦しむ一国にとどまるべきではなく,さらに大きな枠組みの中でその拡大を続けるべきである.獣医学分野では,動物の病気もまた,国・地域や動物種の違いなどを乗り越え,人類の生命を脅かす非常に危険な家畜伝染病となる.国内の大学で教育された獣医師が,国内,あるいは先進国内にとどまらず全世界的なセンスを持つことの意義は非常に大きくなったといえる. 国際協力には,多くの方式がある.物質的な援助,マンパワー・資金の供与,そして人材育成である.どれも重要な方法であるが,それが成熟し,また,日本に恩恵を返してくれるケースは決して多くないのではないだろうか.今般私は,ザンビア国における獣医学教育の場において,提供した協力が実を結び,その結果我が国に対して恩恵をもたらした一つの例に遭遇したので紹介する. 私は大学卒業後,青年海外協力隊員として2年間ザンビア大学獣医学部において,微力ながら国際協力に身を投じた.経済,社会,政治……すべてに絶望に近い印象を受けた当時から10数年経過し,再び,今度はザンビア大学獣医学部の協力を受け,日本の大学学生の教育を行うことになった. ザンビア大学獣医学部は日本の獣医学教育関係者にとって非常にゆかりの深い施設であり,その獣医学教育の礎は日本の獣医学教育者が作り上げたといっても過言ではない.日本政府による無償資金協力によりザンビア大学に同国初の獣医学部の建物がつくられ,その後13年間以上,国際協力事業団(当時)を通して,国際協力専門家および青年海外協力隊隊員により現地の獣医師養成教育および獣医学大学院教育体制の確立がなされてきた.また,日本の獣医系大学では,ザンビア人教員の養成を目的に,日本政府の国費留学生制度を利用して多くのザンビア大学獣医学部卒業生を大学院生として受け入れてきた.その成果は国際協力関係者に高く評価され,国際協力機構の最も優秀なプロジェクト形式技術協力として表彰された.現在では,一部を除き,教育のほとんどはザンビア人教員により実施されている.プロジェクト形式技術協力が終了した後も,日本人研究者とザンビア大学獣医学部の教員の間の研究交流を継続されている.このようにザンビア大学獣医学部の設立・教育体制構築に関する成果は非常に大きなものである一方,さらに発展的な教育・研究の連携に際して,一般に発展途上国を相手にした技術協力にありがちな“一方通行”の技術協力,資金・設備供与となっていたのは現地の経済環境および社会状況から,避けられないのが実情であった. 私が初めてザンビア大学獣医学部に関わったのが,1990年の7月であった.青年海外協力隊員として,初めての外国生活がザンビアであり,当時,ザンビア大学獣医学部では第二期の卒業生を輩出したばかりであった.ザンビア大学獣医学部設立以前は国内に獣医科大学はなく,日本の約2倍の国土に獣医師はわずか20名足らずで,ザンビアの畜産は,海外留学から帰ったそれらの獣医師と専門学校を卒業した獣医助手の手に委ねられていた.そのため家畜伝染病は頻発し,と畜場では重大な寄生虫病まで見逃されていた.また,と畜場を通らない食肉の流通も当たり前であった.大学には頻繁に(日本でいう)法定伝染病に罹患した動物が運び込まれ,人を咬んだため,処分された狂犬病の疑いのある犬もいた.このような実情にフィールドに出ていた獣医・畜産関係の隊員たちと目前の状況に,時には絶望的な感覚を覚えたものであった. その後,青年海外協力隊の2年間の任期を終えて帰国し,大学院に入り,そして大学教員になった.13年の月日が流れ,今度は日本の学生をザンビアに連れて行き,ザンビア大学の教員を中心にザンビアの獣医学関係者に教育を受けるプロジェクトのお手伝いをすることになった. 北海道大学大学院獣医学研究科では,文部科学省の「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援」の一環である,課程に応じた教育内容・方法の高度化・豊富化の充実を目指した特色ある大学教育支援プロジェクトとして「国際獣医学教育協力推進プログラム ―アジア・アフリカ諸国を視野において― 」(取り組み担当者:前出吉光教授)が採択された.その財政的な支援のもと,平成16年度から4年間の計画でアジア・アフリカ諸国の大学に教員・大学院学生を派遣し,現地において日本では接することのできない家畜伝染性疾病の現状を学ぶと共に,相手大学学生に対して,我が国の獣医学に関する先端的知識・技術を提供するというプロジェクトを開始した.このような活動の目的は,「将来,国際的視野で我が国のみならずアジア・アフリカ諸国発展のために獣医学的見地から貢献し得る人材の養成と,アジア・アフリカ諸国の獣医学教育の向上に貢献すること」である. (参照URL : http://www.hokudai.ac.jp/veteri/Edu_GP/Edu_GP.htm) このプロジェクトのフィールドの一つがザンビア大学獣医学部であった.本国際獣医学教育推進プログラムにおいて,これまで一方的であった発展途上国との教育・研究協力ではなく,本当の意味での教育交流・連携を目指し,将来に向かって第一歩を踏むことになった意義は非常に大きく,これはザンビア大学獣医学部と北海道大学,ひいては我が国にとって,国際協力の成果を示す,他に例を見ない画期的な教育連携であると思われる. 今回の教育プロジェクトにおいて教育の主題とされたのは,感染症を中心とした熱帯獣医学と野生動物生態学であった.学生にとって日本ではみることができないが,今後,脅威となりうる動物疾病,特に人獣共通感染症の生の教材を用いた教育を受けることができ,大変意義深い経験の場が提供された.また,家畜衛生システムが初歩的段階にある国において,その現状と問題点を直に観察できたことは,日本で稼動しているシステムの本質理解に深く思慮する機会を与えることができたものと考えられた.また,獣医師を志すものが憧れる野生動物の本当の姿,その生態系と人間の共存などを模索した野生動物管理の講義・実習は,学生達に非常に興味深いものとなったであろう.将来,地球的環境問題に取り組まなければならない学生達に,非常に貴重な経験にもなったものと思われる. 現在,ザンビア共和国内の登録獣医師はそのほとんどがザンビア大学獣医学部の卒業生である.その数は必ずしも充分ではないが,最低限の家畜衛生システムの構築が可能な状況にはなっている.今回の教育にあたっては,ザンビア大学獣医学部の教員および野生動物局の職員を中心に実施された.当然そのほとんどがザンビア大学獣医学部卒業生であり,何らかの形で過去に派遣された日本人教員に教育をされた獣医師がほとんどであった.彼らが日本人学生に対する教育に真摯に取り組んでくれたことは,教育の一つの醍醐味でもあった. 私は,日本人学生教育に直接関わることはなく,主に臨床獣医学講座において,附属動物病院に来院する動物の診療を担当する獣医師に,臨床技術の指導を行ってきた.具体的には,来院患畜の診察に立会い,そこを担当するHouse Surgeon2名および臨床研修中の学部学生に診断・治療の助言および補助を行った.また,整形外科疾患を発症した動物に対する治療を実施した.ザンビア大学獣医学部附属動物病院は,関係教員の海外留学等により,実際に動物治療に関わる職員数が不足し,診療活動はやや停滞していた.また,ザンビア獣医学界の歴史が浅いため,豊富な臨床経験を有する獣医師が少なく,さらに,機材等も非常に限定されるため,臨床部門はそれ以外の分野の発展に比較して,やや取り残された印象があった.そこで,私は,調達可能な機材・資材を利用した簡易治療法の伝授や将来に向けた積極的な現金収入調達の方法を担当職員等と議論・検討した.同病院に来院する動物の飼い主層にはネイティブのザンビア人の比率が増え,その点からも国内経済の安定化が伺えた.現在のところ,飼い主一人あたり1回の診療で動物病院に支払う金額は日本円にして200円〜500円程度であり,その中で,動物病院の収支を合わせて,教育に貢献させることは容易ではないが,ネイティブ・ザンビア人の比率が増えていることや,市内のスーパーマーケットではいわゆるペット・フードが市販されており,今後,愛玩動物に対する獣医学教育の必要性や,この分野の獣医師の経済に与える影響が拡大するものと考えられた. 今回,本プロジェクトに参加し,我々の日本人学生達やザンビア人職員達だけでなく,私自身も,教育に対する考え方や我々日本における教育の現状を客観的に分析できる非常によい機会となった.ザンビア人の職員達は,実地・現物を用いた非常に具体性に富む教育法を実践してくれた.また,英国色の濃い教育手法は,私には非常に新鮮であった.さらに,10数年前,ここで青年海外協力隊隊員として活動していた頃から現在までのザンビア大学獣医学部についての検証や経過を目の当たりにし,自分自身の大学人としての今後について思慮する機会を持つことができたことは,是非私自身の成長の糧にしたい. 最後になったが,本プロジェクトを遂行するにあたって種々の支援をしてくださった国際協力機構ザンビア事務所関係者の皆様,現地で学生達に優しく接してくれた青年海外協力隊隊員,ザンビア大学獣医学部の教員や技術職員,ザンビアの人々,そして本プロジェクト遂行にご尽力された派遣団長はじめ関連するすべての教員・職員に深く感謝申し上げたい. |
|
| † 連絡責任者: | 奥村正裕 (北海道大学大学院獣医学研究科診断治療学講座獣医外科学教室) 〒060-0818 札幌市北区北18条西9 TEL ・FAX 011-706-5228 |