![]()
|
「生物学的整形外科」の新しい展開( | )
|
岸上義弘†(岸上獣医科病院院長・大阪市獣医師会会員)
|
|
|
|
|
| | は じ め に 従来からの,世にいう「獣医整形外科」においては,まず骨や関節の形状を解剖学的に元通りにすること,そして術後すぐに完全な機能を取り戻すこと,という目標を掲げていたように感ずる.それはそれで,実現できれば非常によいことである.しかし,それらを実現するために,生体に対して生物学的に大きな侵襲を与えてしまったり,力学的に無理のある,段違いに強い固定を実施してきたと感じる.生物学的に大きな侵襲を加えると,創傷を治癒させるための細胞やサイトカインは減弱する.その結果自己治癒能力は減衰し,創傷の治癒は遅くなり弱くなる.そして力学的に無理のある固定をしてしまうと,骨の吸収などの自己恒常性の破綻という現象を招きかねない. 筆者自身も,過去には骨折を治そうとして,大きな創を開き,大きくて頑丈なプレートを装着することに何の疑問も持たなかった.より完璧な整復のためには,なりふり構わなかった.手術後のX線写真を見て自己満足に浸っていた.「なんて綺麗な整復なんだろう.」と感じていた.「手術は大成功です.」と飼い主さんに告げて得意満面だった. しかし多くの症例を経験しているうちに,いくつかの恐ろしい現象に遭遇した.形状は綺麗に整復したのにも関わらず,全然骨癒合が進んでいない.癒合が進まずに停止すると,いつまで経っても荷重は専ら固定器具に掛かり,金属物と骨とが緩みを発生したり,金属が疲労して破損したりするのである.また,緩みを起こさなかったプレート下の骨組織がどんどん吸収され,無くなっていくこともあった. それから時が経て,人医学の学会などで勉強し,自分でも実験や研究をし,判明したことは,確かに起こっているそれらの現象が術者のミスではなく,方法の欠陥による副作用であるということであった.それらの現象は,人医学会では,すでに臨床で起こっていたことであり,討論し尽くされ,動物実験でも確かめられた旧知の事実であった[14]. 従来の獣医整形外科が「完全な形状」を追求したのには,3つの理由があると考えている.ひとつには,かつてのAOという機構の影響を大きく受けたことに起因する.現AOはPerrenらが率いており,生物学的治癒を目指しているが,かつての旧AOはMullerらが先頭に立ち,「第1期癒合」や「直接的癒合」という現在では死語となった概念を振り回していた[5].今からさかのぼること約30年前の話である.骨折した骨片同士を圧着し,強固に固定すれば,術後翌日から歩くことができ,骨折部は仮骨を出さず直接癒合し,形状も完璧となる,と説いた.しかし現実には,癒合遅延や再骨折が頻発し,激しい討論の末に,その概念は下火となったのである. かつての獣医整形外科が,その古い概念に振り回されたのには,もうひとつの理由があった.その時代には,動物という,聞き分けのない患者の骨折部を支えるためには,頑丈な内固定しか方法がなかったからだった.いま,優れた創外固定法や横止めスクリューのある髄内釘などが台頭したので,頑丈なプレートでなければならないという理由はなくなった. 3つ目の理由として,獣医師が大きく開創する手術において,まさか自分の手で細胞やサイトカインを阻害して骨癒合を妨害しているとは,思いもよらなかった,ということであろう.大きく開創し,筋組織を𧄍離し,空気に触れさせ,光を当て,金属によって筋組織と骨を遮断することによって,骨折部を治そうとする生体の自己治癒能力を術者自らが削いでいるとは,気がつかなかったのである.治癒が悪くなり,獣医師は「より完璧な整復と固定」をせざるを得なくなってしまったのである.いつしか獣医師は自分のやっていることを省みず,「骨折の治療には,完璧な解剖学的整復と固定が必要」という呪縛に惑わされてしまったと感じるのである. 筆者自身も,かつて橈骨・尺骨両方にプレートを装着したり,大腿骨全体に及ぶような大きなプレートを使用したりと,今から振り返れば思わず冷や汗が出てきそうな仕事をしていた.そういうことをすれば,癒合不全や癒合遅延,また骨吸収や骨壊死という結果を招きやすいということは,すでに人医学では臨床や動物実験で分かっていた事実であったのだ. 綺麗な整復,強い固定,そして手術翌日に歩く,それで治癒したと思い込んではならない.「整復固定,即治癒」という短絡的な思考におちいってはならない.整復・固定というのは,治癒のための最初のお膳立てであり,スタートラインであり,そこから長い治癒期間が始まるのである.骨折がどのような機序で,どのようなスピードで,どのような強さに到達し治癒するかは,その初日の整復・固定のためにどんな方法を選んだかによって左右される.綺麗に整復できたからと言って,また手術翌日に歩いたからと言って,数カ月後の治癒した骨の強度が強いとは,誰にも保証できないのである.「骨折が治癒する」ということは,プレートなどの副子を生体内に入れて歩くことではない.何も支え無しで歩けてこそ治癒である.頑丈なプレートを装着して,翌日から患者が歩いたとしても,あまり意味はない.頑丈な副子を使ったら,それなりにストレスが骨に掛からない時期が長くなり,骨吸収も起こることがある. そもそも骨折治癒のための要素は6つあるといわれている.そのうちの機械的要素2つが整復と固定である.残りの4つの要素が生物学的要素と呼ばれており,幹細胞・サイトカイン・細胞の足場・血行である.閉鎖環境がこれらの生物学的要素を温存させる.これら6つがすべて揃って初めて,骨癒合は順調に進んでいくのである.医師側が骨折部の生物学的要素を破壊し犠牲にして,形状だけきれいに整復・固定しても,治癒が遅れ,強度が弱くなる.もし癒合不全が起こったり,再骨折したりすれば,治療した意味がないことは明白である.もちろん,生物学的要素を追求するあまり,整復がデタラメであれば,骨癒合や機能回復は望めない. この項で述べる「生物学的整形外科」というのは,これら6つの要素を温存した整形外科を指す.まず優先されることは,生物学的要素をできるだけ温存するということ.そして機械的要素も追求するが,もしも完璧な整復・固定を目指すことによって生物学的要素が損なわれるならば,あえて完璧な整復は追求しない.それは,もしも生物学的要素を大きく温存すれば,多少の骨折部のズレが存在しても,とりあえずの強い癒合を果たし,後日ゆっくりと生体自身がリモデリングによって精密な形状を取り戻すからである.関節内骨折ならば,小さなズレがあると可動域制限を起こす可能性があるので,可及的に完璧に整復すべきであるが,骨幹部骨折ならば,筆者の経験から骨折部の80%の接合があれば強い癒合を果たし,以後生体自身のリモデリングによってゆっくりと完璧に整復されていくと考えている. だからと言って,非開創法で解剖学的整復が不必要であるとは思わない.ある程度の精密な整復は絶対に必要である.たとえ骨癒合しても,それが大きな変形癒合ならば,患者の運動機能は損なわれる.骨折部での横ズレ(軸変位)は,ある程度ならリモデリングできるが,大きいものは不可能である.さらにねじれの変形(ローテーション)(回旋変形)は,生体とはいえ,ほとんど元に戻すことができない.折れ曲がりの変形(屈曲変形)もある程度はリモデリングできるが,大きいものは改善しきれないし,関節面の角度が変わり負担が掛かる.したがって,手術中,覆布に隠れた足先の方向(アラインメント)には十分注意が必要である.手術が終わったときに覆布を取ってみたら足先があっちの方向を向いていた,ということがないよう厳重に注意しなければならない. いま世界の医学は,生体の損傷部の閉鎖環境に重点を置き始めている.皮膚の創傷の治療においても然り,乾かして治すのではなく,閉鎖・湿潤・細胞・サイトカイン,これら4つはこれからの皮膚形成外科にとって重要なキーワードとなる[13].骨折の治療の方法も,大きく開創したり,大きな異物を残すものではなく,小侵襲の非開創型の手術が薦められている. |
|
| || 骨 折 1 骨折治癒のための6要素 骨折したとき,骨折部の断端間には骨組織は無かったはずである.その部分に骨組織を再生するのが骨折の生理学的な治癒機序である.つまりわれわれは,骨組織が再生しやすいことを利用して,骨折の治療をしながら再生医療を実施しているとも言える.骨折部の出血・壊死・炎症などの現象を通して,細胞やサイトカインが働き,仮骨を新生し,新しい骨を作り上げる.過去に,人為的に圧迫を加えて骨折部の間隙をなくすという考え方が存在したが,癒合が遅くて弱いなどのいろいろな問題が発生したため,現在では変遷や改良を繰り返し,まったく異なる理論が展開されている. われわれの臨床において,その生体が骨を癒合する力を有するかどうか,往々にしてこれが重要な問題となる.骨が癒合する可能性を持つかどうか,あらかじめ全身状態・骨折部の局所状態を推察しておくのは臨床医にとって重要な事項であろう.覚えておかなければいけないことは,この骨癒合力というのは,手術の回数を経るたびに,加速度的に低下していくということ(図1).つまり,「この手術でうまくいかなかったら,次はあの手術で行こう.」という考え方は,生体の自己治癒能力を過大評価している.開創すれば骨癒合力は一気に低下すると考えておくべきである.開創しなくても,おおよそ一定の期日で,サイトカイン・カスケードは進行していき,そして停止する(図2).このことを踏まえ,現代の人医学整形外科領域においては,生命の維持は優先されるものの,できるだけ早い時期にとりあえずの整復と固定だけはするようになって来ている.初回でもこのような状況であるので,2回目の手術において,同じように骨癒合を進めていくシステムが働くかどうか,全然保証はない.骨折は初回の手術や治療で治したい. 骨折の手術をする前に,その患者の全身状態,骨折部のX線画像,過去の手術のデータ(手術回数とそれらの方法)などを総合的に考慮し,以下の各要素について検討すべきであろう.その上で,今回どのような手術が必要か(または必要でなかったり,不可能であったり)を決定するべきであろう. 私見であるが,私が新鮮骨折の患者を診るときには,シャーカステンの前に立って,3分間,「なんとか非開創で治療できないものか……」と思いを巡らせる.非開創で整復固定できるものを,ことさら開創する必要性もないし,非開創であれば治りが速くて強いのである. 骨折治癒のための6要素について検討してみよう. (1)幹細胞の供給があるかどうか いずれ骨細胞に分化していく間葉系幹細胞は,骨を形成するには不可欠である.これは末梢血にも少量存在するが,これを最も多く含むのが骨髄である. 骨折部をはさんで,近位側と遠位側の骨髄の連絡があれば,そしてそれらの骨髄が壊死していなければ,おそらく骨折部の幹細胞の供給があるといえる.しかし,骨折部に偽関節や瘢痕組織・筋組織 が存在すると,両骨髄は遮断されていると考えてもよい.また,極端な老齢であったり,骨髄が線維化している場合,これも有効な幹細胞の供給は望めない.もしも発症から時間が経過しており,骨折部にX線透過性の領域があり,骨性の組織がその領域を迂回して存在する場合,それは骨折部に瘢痕組織が存在する場合が多い.固定状態が悪く,微小新生血管が形成されては動揺によって断裂するという機序を繰り返すと,瘢痕組織・軟骨組織が形成される.このような場合にも,骨髄の連絡は望めない. 非開創操作下に順行性ピンニング法を行うと,近位・遠位骨髄の連絡を図ることができる.そして,さらに,骨髄液(幹細胞を多く含む)を骨折部に噴出することができる.このことは,骨癒合にとって好都合である. 老齢になると骨髄の中の幹細胞が少なくなり,そのことが骨癒合力を低下させている原因の一つとなる.そこで活躍するのがサイトカインである.サイトカインの中には,幹細胞を増殖する役割を持つものが有り,老齢であっても,非侵襲で治療すれば,サイトカインは生き残り,骨癒合を可能にする. |
|
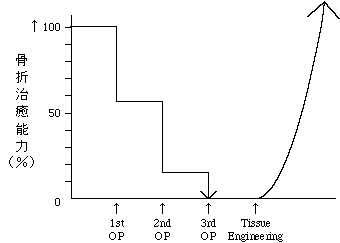
|
|
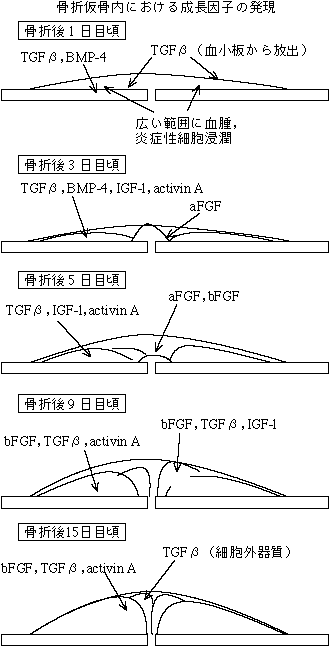
|
|
(以降,次号へつづく) |
|
|
|
| † 連絡責任者: | 岸上義弘(岸上獣医科病院) 〒545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-6-1 TEL 06-6661-5407 |
|
|
|