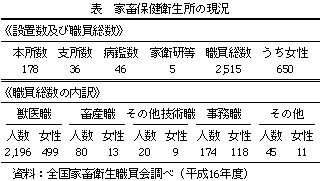![]()
|
家畜保健衛生業務の将来像
|
山下 稔†(岡山県岡山家畜保健衛生所所長・岡山県獣医師会会員)
|
|
|
|
|
| 2.家畜保健衛生所の現状と課題 (1)現 状 家保は「家保法」と都道府県条例により全国の都道府県に設置されている行政機関である(表).
つづいて,昭和40年代に入りわが国の高度経済成長とあわせ国民の動物性蛋白質の摂取増に伴い,畜産の生産現場においても経営の大規模化,集団飼育化が進展してきたことから,疾病の発生態様も複雑・高度化してきた.これらに適切に対応・指導していくためにも高度な技術が要求されることとなり,家保の統合が進められ,施設整備とあわせ高度の診断技術が駆使できるよう職員の専門技術の向上が図られた. 現在,家保は家畜伝染病予防法(家伝法)に規定する家畜の防疫対策を主体とした事務を行っているが,不明疾病に対する病性鑑定能力は格段の進展をみており,農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所と連携のもとに鑑定対応システムが整備されてきている.さらに,良質な生乳生産指導をはじめ,生産性を阻害する諸要因の調査・研究等を地域の畜産関係組織(農業共済組合家畜診療所,畜産団体,JA,関係行政部署等)と協働して展開しており,名実ともに地域における家畜衛生の中心的存在となっている. そして,わが国の家保を末端のネットワークとする家畜衛生組織は,平成12年のFMD発生に係る防疫措置について国際獣疫事務局(OIE)からその活動内容の評価を受けたところである.しかしながら,それまでの家保はその衛生技術をとおして安全な食の生産に寄与していたにもかかわらず,地味な防疫業務が主体であったため,国民から広く認知されるにはいたっていなかった. (2)課 題 昭和40年代後半に至り,わが国の家畜伝染性疾病対策はワクチン開発,抗菌性物質の進歩に加え畜産農家の飼養管理技術の向上と相俟って,家畜伝染病の発生は鶏のニューカッスル病,豚コレラ等の一部の発生以外全般的に減少しており,家畜防疫事務は発生予防にシフトしてきた.国が家伝法を改正し,自衛防疫の考えを打ち出し,各県に自衛防疫団体の組織化を働きかけたのもこの頃である. さらに,このことに呼応して家保に生産振興・指導奨励的な事務の導入が始まった(当時の「畜産総合対策事業」).すなわち,家伝法による検査・摘発・淘汰事務とあわせ,今度は逆に「畜産振興事務」の推進となったのだから大いに戸惑ったものである.その後,この国庫補助事業は総合食料対策事業と名称を変えて実施されている. 家保は日常の防疫業務,病性鑑定業務等を通じて管内の,また近県,国内,世界の家畜伝染病,畜産経営上留意しておかなければならない各種伝染性疾病の現況を常時把握し,場合によっては畜産農家をはじめ関係者に必要な防疫指導・指示を行う等疾病の管理・コントロールをしておかなければならないが,近年,専門化,企業化,広域化する畜産業に対して先述の事業が肥大化するに従って家畜防疫の的確な実施,安全な家畜衛生管理を担保することに不安を覚えるようになってきた. このような中で,最近では平成12年のFMD,平成13年のBSE,平成16年のHPAIと立て続けに家畜伝染病の発生があり,家保は関係機関・団体の協力・支援,家畜飼養農家の理解を得ながら家伝法の規定に沿った防疫活動を展開し,FMDに関しては,発生から6カ月で終息宣言が,BSEに関しては世界でも最も厳しい全頭検査実施体制と24カ月以上の死亡牛BSE検査体制ができた. ここ数年間で起きた未経験の新興感染症対応は,幸いにも従来の家保体制で蓄積してきたパワー,能力等で凌いでこれたが,今後,ウエストナイルウイルス感染症(WNV),ニパウイルス感染症等の共通感染症の侵入,発生が懸念されている.これらの新興感染症の多くは動物由来の感染症であり,家保は地域の家畜防疫機関として,迅速な診断が下せる病性鑑定能力の涵養に努めておく必要がある.そのためには,現在,地方分権,農政改革等の枠組みが議論されているが,地方の行政機関として位置づけられている現行家保組織について,地域の家畜防疫機関としての目的が担保されるよう人的・組織体制の面からの検証が必要な時ではなかろうか. |
|
| 3.地方分権改革と地方自治体の行財政改革 (1)家畜防疫事務の効果的執行の確保 一方,国の構造改革の一つである地方分権・三位一体改革の進展状況にも無関心ではいられなくなってきた.平成12年施行の「地方分権一括法」により機関委任事務が廃止された.家保の主要事務であった家伝法による事務も法定受託事務と自治事務とに整理され,発生予防措置に関する事務は自治事務とされた.そして現在,この分権改革とあわせて議論されているのが地方の財源措置に関しての「三位一体」改革である.現在のところ,この三位一体改革論議の行方は不透明であるが,家伝法の第二章に規定されている発生予防措置は都道府県知事の裁量で実施することとされている.家畜伝染病が発生した場合のまん延防止措置は,他に及ぼす影響も考えられることから国の関与が残された法定受託事務扱いとされた.一応,もっともらしく整理されているように思えるが,家畜防疫の世界では都道府県の境界はあまり意味がない.家畜伝染病予防事業の執行には,家畜防疫員の旅費,需用費(検査・診断薬),機器の整備等各種の経費が必要である.相応の財源が伴わなければ予防事務の適正執行が確保できなく恐れがある. つまり,自治体の裁量での発生予防措置にはその実施対応によっては,自治体間で防疫活動に濃淡が生じてくることも危惧される.地方自治体は今後,独自の判断,創造性が求められているが,家保の主たる事務である家畜伝染病予防事業の執行に支障がでないよう制度改正とあわせた財源措置を要請したい. また,家畜伝染病予防事業の効果的執行に関しては,市町村の支援が肝要であるが,今のところ「家畜防疫を総合的に推進するための指針」(平成13年9月6日公表)の中に努力規定が見られる程度である.こちらも法的根拠の確立とあわせた財源措置の担保が必要である. (2)行財政改革 現在,地方自治体で行財政改革(行革)が行われている.ある県では出先農林事務所の畜産部長が家保所長兼務の形態をとっているところがある.農林事務所の看板の下で,農業改良普及員等の他職種との交流を行いながら,広く管内の情報に接して効率的な家畜衛生行政を進めていくのである.このような家保は制度資金,種々の補助事業も所掌していると聞いた.担当家保職員は大変な激務であろうが,管内の関係者間にはマルチプレイヤーで評価も大いに高いと聞いた.これも行政サービスの形であろうが,多様な業務に忙殺されており本来の衛生業務の方が少々心配である.との所長の話が私としては少々気になっている. 各地で行われている行革については,自治体独自の行政課題・目的があり一概に意見は述べられないが,行革によって家保の統廃合,人員の縮小,兼職等が進められ,家保の本来の行政目的が薄くなる,果たせなくなってくるような行革になっていないかどうか.不安の一つである. |
|
| 4.望ましい家畜保健衛生業務の将来像 平成14年4月2日,国の「BSE問題に関する調査検討委員会」は,BSEの発生は農水省の重大な失政と指摘した.このことを契機として日本の農政は,消費者に視点をおいた方向にシフトされた.そして,BSE対策の個別法としての「牛海綿状脳症対策特別措置法」をはじめ,「食品安全基本法」,「牛の固体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法(牛肉のトレサ法)」ほか関連4法律が食品安全5法として相次いで制定され,家畜衛生行政も従来の家畜の防疫を主体とした家畜保健衛生業務に加え,消費者に視点をおいた業務展開にシフトを始めた. 現在農水省で検討されている「農政改革基本構想」の中でも,BSEやHPAIのまん延防止対策や家伝法の改正をはじめとした家畜防疫体制の強化が食の安全・安心の確保の観点から検討されている. 最近,国(農水省)は消費・安全局の衛生管理課を来年度から検疫と家畜伝染病の予防を担当する動物衛生課と食品や飼料の安全性を担当する動物安全課に組織改正する予算を要求中であると発表した.一方,私が調査した範囲では,県段階の課レベルで所掌事務を衛生(防疫),生産指導(安全)等に区分している県は全国に5県である(BSE発生以前からの体制を含む). 確かに県段階では,各県の諸事情により国段階の組織改正をそのまま導入するわけにもいくまいが,国のこの考え方は是非,検証したいものである. (1)家保組織の位置付け 現在の家保職員は,6年生のカリキュラムを履修した獣医師が6割近くを占め家保の施設整備も充実しており,不明疾病に対応する体制はかなり整備されてきた.このような専門的な技術者集団で組織されている機関は県内組織には見当たらない.私はこの組織がそのマンパワーを最大限に発揮して家畜衛生はもとより,公衆衛生に関わる危機管理事案にも対応できる行政機関であって欲しいと願っている.そのためには,現行の家保組織を獣医師専門職員(家畜防疫員)の技量が十分発揮される組織への特化,深化を検討すべきではなかろうか. さらに,家保現場で対応している動物は家伝法に規定している対象家畜のみではない.野生動物,学校飼育動物指導と多種,多様化してきた家保の事務内容に如何様な態度で臨むことが,今後の家保の在り様のベストチョイスとなるのか.名は体を表すである.家保の名称変更についても日本獣医師会の五十嵐幸男会長も提言されており,必要であれば家保法はじめ関係法規の改正を検討する時期到来であろう. (2)高度専門組織としての組織体制強化 最近,地方自治体の危機管理体制の内容が論評されているが,SARS,HPAIに代表される人と動物の共通の新興感染症も人の健康に関する危機としてその所掌事務に含んでいる自治体が多い.新興感染症の多くは共通感染症といわれている.人の健康を確保する医師とわれわれ獣医師相互に専門性を発揮しながら連携と協働が図られるような危機管理体制の構築も検討しておかねばならない.家保は直近に予想される新興感染症の発生対応について,人の保健所とともに地方自治体の危機管理活動の中心的な組織として機能することが期待されている. 一方,家保は獣医師という専門職を配置しており,家畜伝染病の発生による経済的被害,社会的損失を迅速・的確に沈静化せしめるというその所掌事務の性格から家畜衛生の専門性の高い組織としての位置付けとあわせて,指揮命令系統の独立性も同時に確保しておかなければならない. 最後に,われわれ家畜保健衛生に関わる動物医療技術は以上の論述のように多種,多様化の中で展開されているが,今後は「家畜の生産性の向上」,「人の健康に関わる公衆衛生」,「動物愛護関連技術」の3点に集約されると考えられる.全国各地域に法的根拠のもとに設置されている家保の技術は,これらのいずれにも対応できる正に地方の獣医衛生技術の中心的な役割を担っていることの使命をわれわれは自覚しなければならない. |
|
|
|
| † 連絡責任者: | 山下 稔(岡山県岡山家畜保健衛生所) 〒709-2123 御津郡御津町河内2770-1 TEL 0867-24-3880 FAX 0867-24-3884 |
|
|
|
 1.は じ め に
1.は じ め に