![]()
|
判例に学ぶ〜犬の糖尿病治療と損害賠償請求訴訟
| 岩上悦子†,勝又純俊,押田茂實(日本大学大学院医学研究科社会医学講座法医学部門) |
| 近年,人の医療事故の報道が増加する一方で,いまや家族の一員としての地位を確立してきた犬,猫等の家庭動物に関わる動物医療問題が数多く報道されるようになってきた[1].その中には,損害賠償請求訴訟にまで発展するものもあり,その件数は年々増加しているといわれている[2]が,詳細は明らかでない.われわれが検索できた獣医医療事故判例は13件あるが,今回,最新訴訟事例について報告する. 犬が糖尿病治療を受けたが,獣医師がインスリンの投与を怠ったために死亡したとして,東京都大田区の夫婦が,治療を担当した動物病院の院長らに対し損害賠償金の支払いを求めた.この訴訟は人の医療訴訟を主に扱う東京地裁医療集中部(民事30部)において審理され,平成16年5月10日に約80万円の支払いを命ずる判決が下された.この事件はマスコミに大きく取り上げられており[2],関心のある臨床獣医師も多いと思われるので,その概略を紹介する. |
| 東京地裁判決によると,診療経過の概略は以下のとおりである.原告らは患犬(日本スピッツ犬,当時約10歳)の飼主夫婦であり,被告は平成11年4月から原告らがかかりつけとしているD獣医科病院の院長Aと,同病院に勤務する獣医師B・Cである.原告らは,平成14年12月28日に本件患犬を連れて伊豆への旅行中,本件患犬が少量嘔吐したことから熱海のF動物病院を受診,血液検査で血糖値338(F動物病院正常値75〜117),GOT60(41未満),GPT201(123未満),ALP2900(132未満),K3.0(4.4〜5.4)であったので,同病院の獣医師から,かかりつけの獣医師にインスリンの投与量を決めてもらうように指示された.そこで原告らは同日東京に引き返し,D獣医科病院で患犬の診療を受けたところ,血糖値365(D獣医科病院正常値50〜124)であり,タウリン,バナジウムウォーター,ヒルズw/dを処方され,帰宅した.原告らは,翌29日にも同病院を受診し,患犬を同病院に入院させた.その後,原告らの希望により平成15年1月2日にE動物病院(横浜市)へ転院して治療を受けたが,同月3日午後10時20分に本件患犬は死亡した.この間の診療経過を,診療経過一覧(表1)に略記した. このようなD獣医科病院の診療に対し,原告らは,同病院の獣医師らがインスリンの投与を怠ったために患犬が死亡したとして,治療を担当した獣医師らに対し,350万円の慰謝料を含む438万余円の損害賠償金を請求する民事訴訟を提起した. 判決では,犬の糖尿病の診断と治療を次のようにまとめている.犬の糖尿病は,「発症機序に不明な点が多く」,「病状が進行した状態で発見されることがほとんどであるため」,大部分が「インスリン依存型糖尿病であるとされている」.「糖尿病と診断されるのは,文献によって多少異なるが,空腹時血糖値が130又は150を超える場合であり,180程度を超えると糖尿病の臨床症状が出現し始める」.治療については,「体重コントロール,適切な食事管理,適切な運動に加え,大部分の例でインスリンの投与が必要となる」が,「初診時に血糖値が300台であれば,インスリンを投与するとは限らないとの意見がある」とも示した.インスリン分泌を促進する経口血糖降下剤は,「効果的に作用するにはまだ膵臓β細胞のインスリン分泌能力が残存していなければならない」が,犬の場合「糖尿病と診断された時点では,大多数はβ細胞が既に破壊され,インスリンの分泌が極端に少なくなった状態になっていることから,その効果は余り期待できない」,また犬に対する「毒性は明らかでなく」,投与については「十分な注意が必要である」とした. 判決では,被告らの注意義務違反を以下のように認定した.「平成14年12月28日の時点で血糖値が300を超えており,糖尿病であったことが認められるので,同日時点でインスリンを投与するという治療方法をとることが検討されるべきであるが」,「血糖値が300台でとどまっていたこと,インスリン投与による低血糖等の副作用の危険性があること,同日時点では活動性は保たれていたと認められることを考えると,インスリンを投与せず」,「食事療法や運動療法によって,ひとまず血糖値の推移や臨床症状の様子をみることも,治療方法の一つとして認められる」とした.一方で判決では,28日,29日の血糖値の推移を検討した上で,「同月29日には血糖値の上昇がみられ,持続的な空腹時高血糖があると解され」るとし,また,「同月28日早朝及び同日夜から翌29日朝にかけて6回嘔吐があったこと」,尿糖,ケトン体,高血糖を指摘して,「同月29日には既に糖尿病性ケトアシドーシスを発症していたものと考えるのが最も合理的」と判断した.その上で,「糖尿病性ケトアシドーシスは,発症すると病状の進行が急速で」,「早急に治療が必要で」あり,被告A・Bは28日,29日には「患犬の治療にかかわっており」,「患犬の状態を把握していた」のであるから,「29日,遅くとも翌30日の診察開始時には」,「患犬の状態を監視しながら,輸液療法及びインスリン療法を行い,重炭酸塩療法の実施を検討すべきであった」とした.そして,「インスリンを投与する場合,特に厳重な監視が必要となる」が,「被告病院は大田区でも有数の動物病院であり」,その診療体制を検討して,「これらの治療を行うことは人的・物的設備の面からも可能であった」と認めた.また,同月30日以降「オイグルコンの投与が行われているが,犬の糖尿病はインスリン依存型が大部分であることから余り効果が期待できず,かえって病状を悪化する危険性も指摘されて」おり,「糖尿病性ケトアシドーシスを発症している本件患犬に対し,インスリンの代わりにオイグルコンを投与することが適切な治療であったと認めることはできない」とした.被告らは,カリウムの低下がありそれだけでも心不全の危険があるので,インスリンの投与は危険だとして行わなかったと主張したが,「本件患犬は既に糖尿病性ケトアシドーシスに至っており,放置しているとケトン体の蓄積が進んで生命に危険が及びかねないことから,緊急な治療が必要な状態で」あり,「インスリン投与を躊躇すべきような状態であったとは認められない」とし,病院側の主張を退けた. 「重度の糖尿病性ケトアシドーシスの犬や猫のうち,約30パーセントが死亡するか,最初の入院中に安楽死させることになるとする文献がある」が,「注意深く監視しながらきめ細かい治療を行えば,糖尿病や糖尿病性ケトアシドーシスに対する治療効果を上げることが可能であるとされており,治療開始が早ければ早いほど救命可能性が高くなると考えられ」,「本件患犬は平成14年12月27日以前の段階では何ら臨床症状が認められておらず,平成15年1月1日までは活動性がある程度維持されており」,「遅くとも平成14年12月30日の診察開始時に本件患犬に対するインスリン投与が開始され,糖尿病・糖尿病性ケトアシドーシスに対する積極的かつきめ細かな治療が開始されていれば」,「少なくとも糖尿病性ケトアシドーシスの急速な進行による本件患犬の死亡は避けられたものと認められる」との判断を示した. 以上により,東京地裁は被告A・Bにはその診療に過失があると認めた.被告Cについては,平成15年1月2日に「それまで本件患犬の治療を担当してきた被告Bと一緒に治療を行ったもので」あり,「同日の時点で,自らの判断で直ちにインスリンを投与しなかったことに過失があるとまでは認められない」とした. 損害賠償金の認定は以下のようになされた.本件患犬は血統書付きで,日本スピッツ協会から種犬認定を受け,多数の表彰等を受けている,繁殖可能な年齢の犬であると認める一方で,原告らは本件患犬を売却したり繁殖させたりする意思はなかったことは明らかで,本件患犬の交換価値を算定することは困難であるし,逸失利益が発生したと認めることもできないが,前記のような犬であったことを慰謝料の算定において考慮するとした.治療費については,D獣医科病院において行われた各治療は全く必要のないものであったともいえないので,同病院における治療費の半額(3万余円)を損害と認め,E動物病院における治療費は,全額(6万余円)損害と認めた.慰謝料については,原告らが本件患犬を「我が子同然それ以上に溺愛し」,「愛犬を失い,計り知れない精神的苦痛を味わった」と主張したことに対し,「原告らの生活において,本件患犬はかけがえのないものとなっていた」と認めた.また,原告らは定期的に健康診断を受けさせるなどしてきたにもかかわらず,約10年で本件患犬が死亡することになったものであって,「本件以降原告がパニック障害を発症し,治療中であることからみても,精神的苦痛が非常に大きい」と認め,慰謝料を60万円とした.さらに葬儀費用1万円,弁護士費用10万円が認められ,合計80万余円の支払いが命じられた.その後被告は控訴したが,平成16年6月2日控訴を取り下げ,この判決は確定した.なお,この判決文は裁判所ホームページ(http://www.coarts.go.jp/)より入手が可能である. 犬,猫等の動物医療訴訟において高額判決が出た判例としては,平成14年宇都宮地裁での猫の避妊手術死亡事例がある(裁判所ホームページ参照).判決では,この猫は30万円でブリーダーから譲り受けた雌猫であり,優秀な血統でショーキャットとして入賞した実績のあるアメリカンショートヘアー種であるが,繁殖については考えていないことから,5歳で死亡した時点での財産的価値は50万円が相当であるとし,慰謝料は,単なるショーキャットとしてだけではなく家族の一員ともいうべき愛情を注いでいたことを認め,20万円を相当として,その他を合計し93万余円の損害賠償金の支払いを命じた. いわゆるペットは,法律上「物」にすぎない動物であるが,平成11年に『動物の愛護および管理に関する法律』が成立し,動物は「命あるものである」ことが重視されるようになり,今回の判決でも「動物は生命を持たない動産とは異なり,個性を有し自らの意思によって行動」し,「飼い主とのコミュニケーションを通じて飼い主にとってかけがえのない存在」になると認められるほどになった. 本件での損害及び損害額の判断においては,スピッツ犬の寿命が約15年で,約10歳ならば繁殖可能であると認められたこと,原告は本件により非常に大きい精神的苦痛を受け,「パニック障害を発症し,治療中である」と認められたことなど,議論の余地もあるかと思われるが,今回認められた慰謝料60万円は,検索できる犬,猫等の動物医療訴訟における慰謝料認定額としては最高額である. 現在の訴訟ブームとコンパニオンアニマルとしての犬,猫等の家庭動物の社会的地位の確立によって,今後さらに動物医療事故訴訟が増加することは必至であろう.これらの判例は,獣医師にとって,わが身を振り返り,飼主との間にトラブルを生じさせず,1頭でも多くの動物の生命が救えるように,より一層の注意を払って日々の診療に携わっていくべく警鐘となろう. |
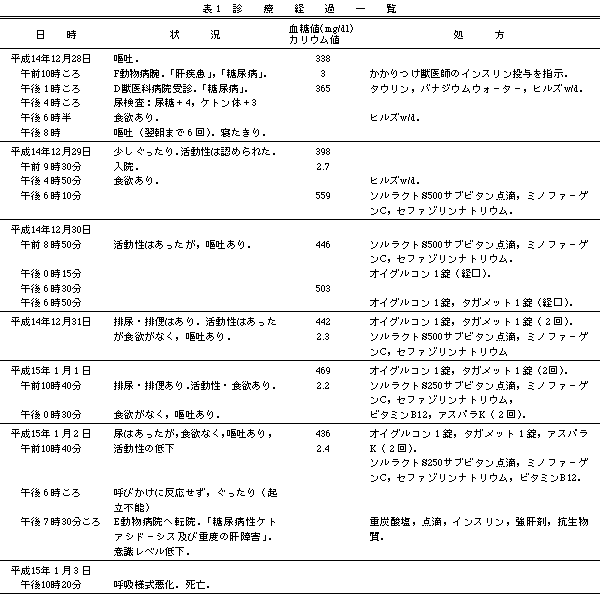
引 用 文 献
|
| † 連絡責任者: | 岩上悦子(日本大学大学院医学研究科社会医学講座法医学部門) 〒173-8610 板橋区大谷口上町30-1 TEL 03-3972-8111(内線2277) FAX 03-3958-7776 |