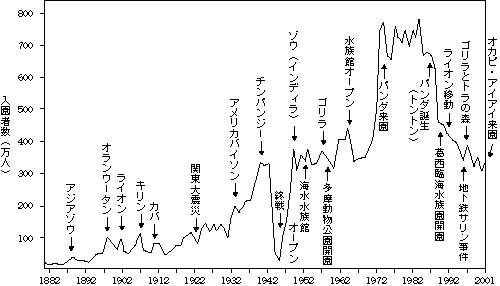![]()
|
動物園の機能と社会的役割
菅谷 博†(前東京都恩賜上野動物園園長) |
||||||
 1.は じ め に 1.は じ め に動物園,水族館は今新たな時代を迎えている. 21世紀は環境の時代といわれる中,かけがえのないこの自然豊かな地球環境をいかに次世代へ受け継いでいくかは,今を生きる私達の責務である. 動物園,水族館は自然への扉,環境学習の場として,そこに持てる希少野生動物をその素材として活用し,自然に親しみ,慈しむ新たな世代の育成に積極的に取り組むことが使命となっている. しかしながら,動物園,水族館がその社会的役割を十分に発揮していくためにはいまだ多くの困難な課題を抱えている. 本稿では動物園を中心としてその機能と社会的役割について論じつつ,課題解決のための方向性を探ってみたい. |
||||||
| 2.歴史的背景から わが国と動物園先進国である欧米諸国の動物園との相違点を歴史の中から考えてみる. (1)世界の動物園 古い記録としては,すでに紀元前1000年頃にエジプト,インド,中国等に王侯貴族に動物コレクションの存在が知られているがこれは一部特権階級の興味や娯楽,権力の象徴としてのものであり,一般市民と係わりをもった自然科学の場,教育の場としての登場は15世紀以降に始まるヨーロッパにおける自然科学の勃興をまたなければならない. 15世紀末のコロンブスによる新大陸の発見は未知の文明,自然に対して人々の関心を高め,18世紀の英国のジェームズ・クックの大航海は海軍力と科学と帝国主義があいまってめざましい経済発展をもたらし,19世紀,ビクトリア朝の大探検時代に繋がっていく. それらの時代を通じた数々の探検から得られた膨大な海外からの資料は,やがてこれを研究する学会を生み,1788年にはリンネ学会,1826年にロンドン動物学会,1833に昆虫学会が誕生している. ヨーロッパの動物園はそのような幅広く歴史ある科学的土壌に育まれた機関ということが言える. この時代の動物園で今にその名残を止めているのは,オーストリアのシェーンブルン動物園(1752)(図1),フランスの国立自然博物館ジャルダン・デ・プランテ内動物園(1793)(図2)である.
前者はウイーンにあるシェーンブルン宮殿の動物コレクションを一般に公開したのが始まりで,世界最古の動物園とされている.後者はフランス大革命を機に誕生した「動物学研究」のための最初の国立機関として知られる. 19世紀に入ると「科学の進歩を願う市民の意志により計画」された,これまでなかった画期的な民間の研究組織である動物学協会によってロンドン動物園が創設(1828)された. その設立の趣意書には「動物の特性,習性を研究・教育する重要な役割を果たす.そして,収集した動物は見せ物ではなく科学研究の対象とする」旨が謳われている. ここに近代動物園の第一歩が記されたと言える. 事実,ロンドン動物園は学会直属の科学研究の場として機能し,リチャード・オーエン,チャールズ・ダーウイン等多くの研究者がこぞってここを利用し各種動物学会のセンター的役割を果たしたのである. この地において実際に動物学等を学んだ経験のある中川志郎先生(元上野動物園長・現茨城県自然博物館長)によれば,比較医学研究所および比較生理学研究所が併設され80名に近いスタッフが研究に従事し,動物関係蔵書も20万冊の図書館を持ち重要な定期出版物を出し続けていることに強い衝撃を受けたとのことである. 翻ってわが国の動物園の歴史を辿ってみよう. (2)日本の動物園 わが国最初の動物園である上野動物園は国立博物館の附属施設としてスタートしている. 江戸から明治への激動期に文明開化が叫ばれる中,欧米文化の流入した中に動物園が文化施設の一つとして紹介された. 具体的な動きでみると,ウイーン博覧会に出品するため,全国各地から日本産の動物が東京麹町山下町にあった博覧会事務局に集められ,やがて収集動物の公開も計画され次第に拡張していった. 明治10年上野に博物館が建設され,明治15年(1882)農商務省所管の博物館の附属施設として動物園が開園した. 外形的には博物館の一施設であり,自然系博物館を目指して開設されたことは間違いないが,長きにわたる鎖国政策などもあり欧米の博物館や動物園のように圧倒的な博物資料,それに基づく知的集積のないままにスタートを切らざるをえなかったのである. このため,制約された環境の中で,いかに健康で保管展示するかという「動物飼育学」は発展したが,欧米でみられる自然科学の研究の場,包括的な動物学を構築するまでは至らなかった. 一方,海外からのトラやキリン等の野生動物の移入展示や芸の披露により,娯楽性・大衆性の高い都市文化として多くの国民から支持されてきたことは,動物園の発足以来の入園者数の動向(別表)に示すとおり間違いのない事実である.
しかし,上野動物園が開設時に目指した方向性が政治的・社会的な動きに翻弄され,先人達の思いと違った歩みを辿らざるを得なかったことが今日でも,ともすると動物園は娯楽施設であるという観念を人々に植え付け,なかなか文化施設的な意味が理解されない要因ともなっている.動物園を評価するうえにおいて,前にも触れたが,それは必ずしもマイナスの評価とすべきではなく,動物園の持つ大衆に支えられた楽しく健全性の高い娯楽的要素は今日でも動物園を支える大きな柱となっている. |
||||||
| 3.動物園機能と今後の展望 動物園は「レクレーション」「教育(環境教育)」「種の保存(保護)」「調査研究」4つの機能があると言われ国際的にも定着している. (1)レクレーション 都市において動物園は自然と市民を繋ぐ装置であり,市民が生きた希少野生動物を自分の目で見られる数少ない場所である. そこでは,親子やカップルが展示された動物を眺め,観察し,語り楽しく一時を過ごす憩いの空間となっている. レクレーションは,心に快よさや知的好奇心の充足感あるいは非日常空間での開放感を呼び起こす等,動物園を利用する人々の精神面での要素が強くからみ,簡単なようでなかなか難しい面がある. レクレーション機能を十分に発揮させるためには,展示動物の選択,展示施設の構造と展示方法,適切な説明・解説等を通じて来園者に満足できるメッセージを伝える事が重要である. その他,利用料金の設定,接遇,便所の数,食堂のメニューに至るまで,ハード,ソフトの多方面にわたる総合的な対応が要求される機能と言える. (2)環 境 教 育 近年,動物園の機能として大きくクローズアップされているのが環境教育である. 野生動物の展示を通し来園者に驚きと知的好奇心を満足させながら自然への関心を高め,野生生物と人間との関わり,さらには生命の大切さを学ぶ媒体として動物園はきわめて有効な存在である. 国際自然保護連合(IUCN)が発表した「世界保全戦略・World Conservation Strategy1980」では,野生動物を飼育展示するための原則と勧告を掲げ動物園の担うべき役割として「野生動物の展示は,丹念に用意された教育計画に基づき,その展示種が生態系の中で果たす役割を理解させるものでなければならない」としている. しかしながら,この指針によりわれわれが積極的に推進すべき環境教育はなかなか難しい課題でもある. 環境教育の大切さは動物園界でも理解されつつあるが,それをどのような手法で実施するのかいまだ試行錯誤の中にある. 上野動物園内においても,人的には動物解説員(動物園協会専門職),ボランティア,普及および飼育担当職員によるもの,あるいは動物標識,解説版,パンフレットさらにはインターネット等さまざまな媒体により環境教育が行われている. これはこれとして評価すべきものであるが,「教育」という専門的見地から見た場合には果たしてどのような評価を受けるのか興味深い. 環境教育は昔から動物園の機能として持っており,これまでもそれなりの活動は行ってきたが,それを動物園の核となる事業として前面に打ち出してきたのは比較的新しく,すでに先駆的に取り組んでいる施設もあるが,人材の養成,プログラムの開発,教育センターの設置,学校教育者との連携,展示施設の改善等はこれからの整備・開発に負うところが多い. 環境教育については,総合学習への対応,生涯学習の推進など具体的な社会的背景を持つ中で,動物園は積極的な取り組みを行いその役割を果たしていくことが,社会的に新たな評価を獲得するチャンスともなるであろう. (3)種 の 保 存 種の保存はいうまでもなく,希少野生動物の保護増殖であり,生物多様性の保全への取り組みである. 国際自然保護連合(IUCN),国際環境計画(UNEP),世界自然保護基金(WWF)による「世界環境保全戦略」により,「動物園や水族館は,種の保存や遺伝子の多様性の保存,さらには環境学習の面でも貢献できる」との勧告が出され,世界の先進的な動物園はこの勧告に基づき動物園での種の保存事業や環境学習に力を入れた活動を行っている. 絶滅の危機に瀕したアラビアオリックスを野生復帰まで回復させたフェニックス動物園の偉業は富みに有名であるが,サンディエゴ動物園,ワシントン国立動物園,イギリスのジャージー動物園等も希少野生動物の野生復帰に向け積極的な取組みを行っている. これらの動物園においては,多くのスタッフを抱えた各種繁殖研究施設を持ち,人工繁殖技術の開発と応用,遺伝子レベルでの研究等の最先端の科学技術をも駆使し,受精卵移植,性別判定,親子判定,母系解析等,さまざまな形で実際に利用されている. 日本の動物園でもこの世界の潮流に応じ,(社)日本動物水族館協会が1988年「種の保存委員会」を発足させ全国規模の繁殖計画を策定した. 都立動物園では1989年,独自に都の重要事業として位置づけし,長期計画「ズー2001構想」を策定した. ズー2001構想では「種の保存」と「環境学習」を大きな柱とし,その目標に沿って都立動物園・水族館を総合的,体系的に整備しようとする構想である. 「種の保存」は,「ズーストック計画として50種の希少野生動物を選びそれぞれ分担し繁殖に取り組みニホンコウノトリの繁殖等野生復帰をも計画される大きな成果をあげている(図3). 希少野生動物の野生復帰計画は日本においても「トキ保護増殖計画」など幾つかあるが,その実現には今暫く時間がかかるであろう.これは当該動物の採餌・給水・営巣等,また,放鳥を行うエリアの選定やそのための整備もあるが,地域住民の生活,産業等に密接に関係し,大きな影響を及ぼすため国や地方自治体,住民,研究者等多方面にわたる理解と連携が重要である.このため長期的総合計画のもとに実施される.
(4)調 査 研 究 動物園には多種多様な貴重な「生きた野生動物」が多くいる. そこから得られるさまざまな情報は野生下での観察では得ることが困難なものも多数ある.たとえば同一個体を追跡し,生理的機能をみるあるいはさまざまな飼育環境をコントロールして行動の変化を観察するなどは動物園の方がはるかに行いやすい. このように動物園で野生動物を飼育するという特性は,野生動物に関わる繁殖・生理・病理・行動学等さまざまな分野の学問の発展に寄与している. これまでその研究を担い,核となってきたのが獣医師である. 獣医学を修めた専門性の高い職員は都の動物園には飼育職員の2割を占める. しかし,動物病院に配属できるのは,定数の関係で都の動物園全体で10名程度である.他の獣医師は,教育普及活動や飼育現場に配属されているがそのセクションでも専門的知識は十分に活用されている. 動物園で診療獣医師として一人前になるまでには14〜15年程はかかる.小鳥から象までの多くの野生動物の多様な疾病と,その治療を経験するまでには相当長い年月を要する.対象動物が比較的限定的な,家畜やペット診療行う獣医師と同様な高い技量を身につけるためには不断の努力と少々の運(ジャイアント・パンダやゾウが病気になり,治療することなどは,そうやたらにあることではない)もある. 都の動物園では調査研究を専門とする職員の配置はなく,本来業務の合間をぬって行われている.仕事と密着した部分が多いため,あまり抵抗感もなく行っているが,学会等の発表前に昼間の仕事で疲れた体で懸命にパソコンに向かっている姿をみるに付け,頭が下がる思いと同時に,専門職員を置いた研究センターの必要性が痛感される. 動物園で蓄積された研究成果は動物園に止めることなく,時間の許すかぎり各種学会等にも発表するなどしているが数は少ないのが現状である. また,大学や研究機関との共同研究も行われ新たな知見を得る機会も多い. 今後,調査研究の重要性を考えると組織的な改革,人材の育成に早急に取り組む必要がある. |
||||||
| 5.お わ り に 日本は世界有数の動物園王国である.世界の動物園数は1000園以上あると言われているが,わが国の(財)日本動物園水族館協会に加盟する動物園だけで90(水族館は68)あり未加盟園館を含めると100園にも達する. そこを利用する客数は年間,動物園で4000万人,水族館で2700万人となっており,日本国民の二人に一人が年一回は動物園水族館に足を運んでいることとなる. このように豊富な資源を持った動物園・水族館が時代の要請に応え,社会教育施設としての役割をいかに果たしていくかが今問われている. 長い歴史を誇り,私達の身近で,強い組織力を持った獣医学的技術集団である日本獣医師会の皆様には今後ともより一層のご支援ご協力をお願い申し上げ終わりと致します. |
||||||
| 参 考 文 献 中川志郎・2001動物園ゼミナール資料 |
| † 連絡責任者: | 菅谷 博 〒194-0211 町田市相原町597-48 TEL・FAX 0427-73-3650 |