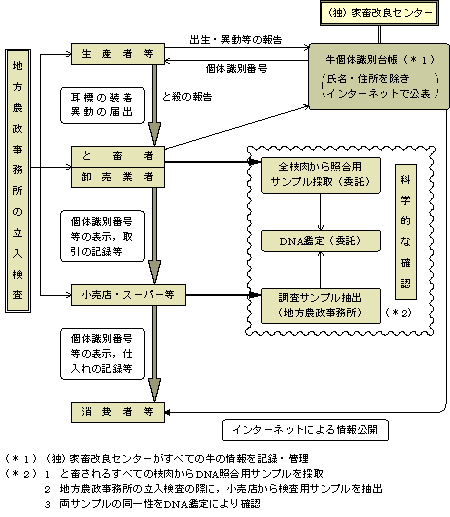![]()
|
牛の個体識別と牛肉トレーサビリティの概要
田中宏昭*† (農林水産省消費・安全局衛生管理課 牛トレーサビリティ監視班係長) |
||||||||||||||||||||||||
| I.法制定の背景と趣旨 平成13年9月,わが国で最初のBSE発生に端を発し,食肉の産地偽装やBSE対策として実施した牛肉在庫緊急保管在庫事業を悪用した事件等により,国民の牛肉に対する不信感や行政に対する批判を受けたところである. 農林水産省としては,BSE発生以降,厚生労働省をはじめとする関係機関と連携し,と畜場におけるBSE全頭検査,特定部位の除去及び焼却による牛肉の安全性の確保,肉骨粉の使用禁止による新たな感染経路の遮断等の措置を講じてきた.また,平成15年4月からは,24カ月齢以上の死亡牛の全頭検査も実施してきたところである. これらの施策に加えて,食品の安全・安心確保を強力に推進する農林水産省の重要な課題として,BSEのまん延防止措置の的確な実施と牛肉の安全性に対する信頼確保の観点から牛肉トレーサビリティについての法制定の検討を始めた. BSEは,他の家畜伝染病と比べ,潜伏期間がきわめて長いため,患畜発生時において,同居牛や疑似患畜の特定にはその所在や異動履歴等の記録を過去に遡って確認することが必要になる.まん延防止措置を的確に実施するためには,牛1頭ごとに所在等の情報を一元管理し,患畜発生時に迅速に検索できるシステムを構築する必要がある. また,牛肉については,BSEの発生により大きく減退した消費がいまだ発生前の水準にまで回復しておらず,「全頭検査でも不安」という消費者が多数見られる実態にあり,酪農及び肉用牛生産の安定のためにも,牛肉に対する消費者の信頼をさらに高めることが重要となっている. 他方,BSEの発生により大きな社会的混乱を経験したヨーロッパでは,牛肉流通の透明性の確保により,牛肉に対する消費者の信頼を確保するため,2000年9月1日以降にと畜された牛肉について,個体識別番号等の表示が義務化されている. このようなことから,牛の出生から死亡・と殺までの個体情報を個体識別番号により一元的に管理するとともに,と殺・解体処理された牛肉について,流通の各段階で個体識別番号等の表示を義務付けることによって,牛肉の個体情報を確認できる仕組みを構築することが必要との趣旨から,平成15年2月7日閣議決定され国会に提出された. 国会では,農林水産省関係の食の安全・安心関係法案の1つとして平成15年5月8日,13日及び15日の3日間,衆議院農林水産委員会で審議され同月16日の衆議院本会議で可決された後,参議院に送付され同月27日,29日及び6月3日の3日間審議され6月4日の参議院本会議において可決され成立した. 法律の名称は,「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号.以下「制度」という.)である.平成15年6月11日に公布され,生産段階については,平成15年12月1日から施行され,流通段階は平成16年12月1日から施行される. |
||||||||||||||||||||||||
| II.制度の概要 1.基本的な仕組み
2.制度の主な対象者
平成14年6月の「食品安全行政に関する関係閣僚会議」において食品安全行政の見直しが決定されたことを受け,農林水産省では,リスク管理部門と産業振興部門が分離されることとなり,消費・安全局が設置された.また,地方農政局に消費・安全部安全管理課,地方農政局の所在地以外の都道府県には食糧事務所から再編された地方農政事務所が新たに設置されるとともに,家畜改良センターにも新たに個体識別部が設置された. 本制度はリスク管理のためのもので,消費・安全局の衛生管理課(旧畜産部衛生課)が所管することになり,平成16年12月1日の完全施行に向けて一体となって準備を進めているところである. 具体的には,制度の信頼性確保のために生産から流通の各段階において耳標の装着,出生や異動等の届出,個体識別番号の表示等が適正に行われているかどうか地方農政事務所による確認を行う. 必要な届出や虚偽の報告があれば罰則が適用されるが,制度を的確に実施することにより,国産牛肉に対する消費者の信頼確保を通じてわが国の牛肉産業の発展に大きく資するものと考えている. 5.DNA鑑定の実施 制度の信頼性確保のためには,個体識別番号が正確に伝達されなければならない.このため,前述したとおり地方農政事務所による確認が行われるが,科学的な検証としてとDNA鑑定による同一性の確認を実施する. 具体的には,図4のとおり,と畜されるすべての牛の枝肉から照合用サンプルを採取し,一定期間保管しておく.全国の小売店等から一定の割合で調査用サンプルを採取し,照合用サンプルとの間で同一性をDNA鑑定する. 実際のDNA鑑定の実施機関であるが,農林水産省から照合用サンプル採取は社団法人日本食肉格付協会へ,照合用サンプル保管とDNA鑑定は社団法人家畜改良事業団にそれぞれ委託する.小売店等からの調査用サンプル採取は地方農政事務所が計画的に行う. 小売店等での個体識別番号の表示は平成16年12月1日からであるが,それまでの間,試験的に実施することとし,鑑定の結果の利用や技術的な問題等を解消していきたいと考えている. 6.個体識別情報の公表 (独)家畜改良センターは,個体識別台帳の記載事項のうち,管理者の氏名等を除く情報を,これまでと同様に,図5のとおりインターネットを通じて公表することになる.消費者,流通事業者,生産者等は,個体識別番号から牛の生産履歴情報が検索することが可能となる. |
||||||||||||||||||||||||
| III.制度に期待される効果 本制度に期待される効果は,BSEをはじめとする各種疾病のまん延防止が図られるとともに,牛肉にかかる牛の情報が正確に伝達され,消費者等の牛肉に対する理解が深まり,牛肉の需要が増加することが期待される.消費者からみれば,購入あるいは提供を受けた牛肉の生産履歴を遡及・追跡することが可能となることは,牛肉に対する大きな安心材料であると考えられる. また,個体識別番号をキーとして,これまで別々の番号で管理されていた血統情報,泌乳や産肉等の能力情報,疾病や診療履歴等のさまざまな個体情報が統合され,その一体的な利用が可能となり,経営の高度化や牛の改良の促進が期待される.さらに,個体識別を必要とする畜産関係団体の業務の効率化により,結果として団体のサービスの向上及び団体へ支払うコスト負担の低減等のメリットに加え,牛個体の識別を必要とする制度及び補助事業の適正かつ効率的な執行が確保されることも大きな効果として期待される. さらに,牛の個体識別番号が正確に伝達・記録されることとなれば,食中毒等の食品事故等が発生した場合においても,流通経路を遡ることも可能となり,製品回収にも活用しうると考えられる. |
||||||||||||||||||||||||
| IV.制度と獣医師 本制度が構築された背景から期待される効果までを記述したが,制度を円滑かつ適正に推進していくためには,牛肉の生産から流通までの各段階で活躍されている獣医師の協力が必要なことはいうまでもない. BSE発生以来,「食の安全・安心」が大きく注目されるようになり,個体識別番号の伝達以外にも飼料給与歴や投薬歴等や生産履歴の情報開示が急速に進んでいる. 獣医師は,家畜の診療や疾病予防という重要な責務を果たさなければならないのはもちろんであるが,今後は,「食の安心・安全」確保のため生産者と消費者との架け橋として両者に情報発信することが重要と考えられる. 最後に,獣医師の協力なくしては本制度を円滑かつ適正に実施していくことが困難と考えているので,理解と協力をお願いいたしたい. |
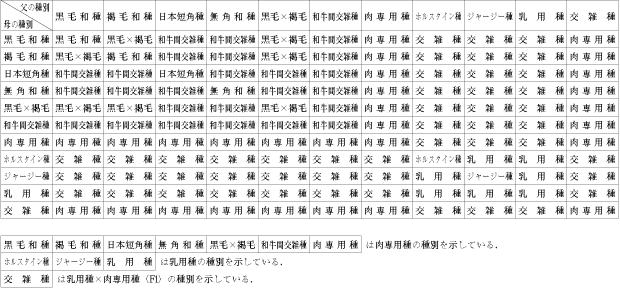 |
図2 牛肉トレサ法に基づく種別区分の整理(父牛・母牛に基づき種別を分類した場合) |
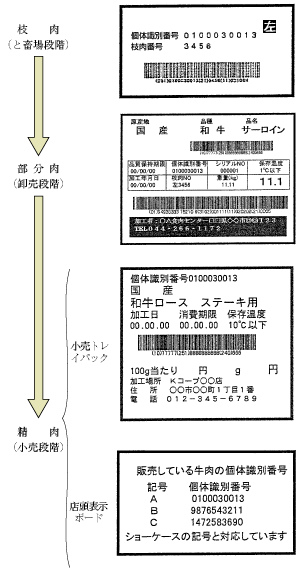 |
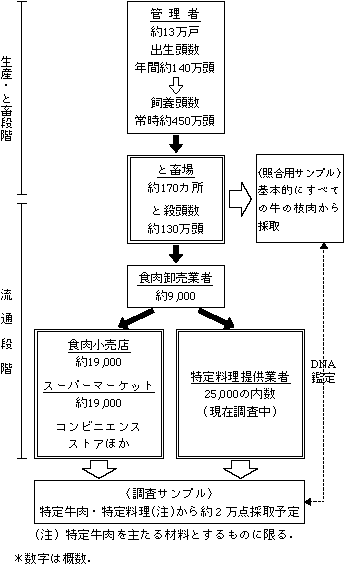 |
図3 個体識別番号等の表示・伝達のイメージ |
図4 DNA鑑定のためのサンプル採取の対象者 |
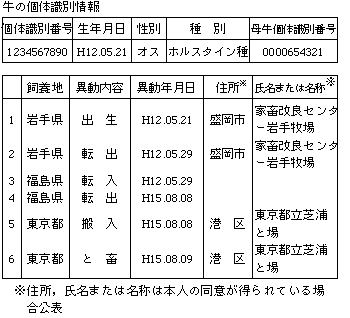 |
図5 インターネットを通じた情報公開 |
| † 連絡責任者: | 田中宏昭(農林水産省近畿農政局消費・安全部消費生活課) 〒602-8054 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル TEL 075-451-9161 FAX 075-414-9910 |