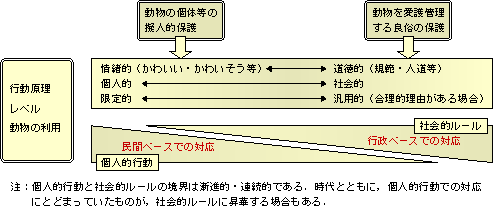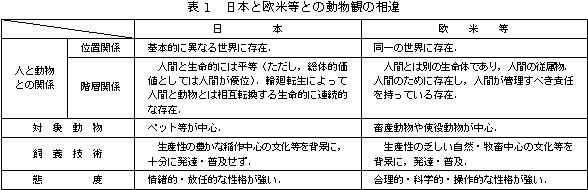東海林克彦†(環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長)
|
 冒頭から私事で恐縮だが,3年前から猫を飼い始めた.ペット禁止の官舎暮らしが長かったため,動物を本格的に飼うのは,約30年ぶりである.田舎育ちなので,子供の頃は,犬,猫に始まり,ウサギ,チャボ,カナリア,コイ,熱帯魚,スズムシなど,実にいろいろなものを飼った経験がある.久しぶりに猫を飼ってみて驚いたことは,まさしくペットが「家族の一員」になっていることである.ここでいう家族の一員とは,「心と時間と空間の隙間を埋めてくれる存在」という意味である.「心」とはやすらぎや優しさをもたらしてくれること,「時間」とは話し相手や遊び相手になってくれること,「空間」とは添景として生活空間にほのぼのとした暖かさを醸し出してくれるということである.しかし,バンビシンドローム問題に象徴されるように,過剰な擬人化は人と動物の双方にとって好ましくない.ということが頭では分かりつつも,その愛らしい姿を見ていると,愛情を注ぐことと一定の距離を置くことのジレンマに陥ってしまう.本稿では,このジレンマを問題意識の基調としつつ,つれづれなるままに動物の愛護管理に対する所感を,個人的な見解として述べさせていただくこととする.雑駁な総説で恐縮至極であり,本誌の品位と格調を損なうことが危惧されるが,獣医学には縁遠い門外漢のざれ言としてご容赦を頂きたい. 冒頭から私事で恐縮だが,3年前から猫を飼い始めた.ペット禁止の官舎暮らしが長かったため,動物を本格的に飼うのは,約30年ぶりである.田舎育ちなので,子供の頃は,犬,猫に始まり,ウサギ,チャボ,カナリア,コイ,熱帯魚,スズムシなど,実にいろいろなものを飼った経験がある.久しぶりに猫を飼ってみて驚いたことは,まさしくペットが「家族の一員」になっていることである.ここでいう家族の一員とは,「心と時間と空間の隙間を埋めてくれる存在」という意味である.「心」とはやすらぎや優しさをもたらしてくれること,「時間」とは話し相手や遊び相手になってくれること,「空間」とは添景として生活空間にほのぼのとした暖かさを醸し出してくれるということである.しかし,バンビシンドローム問題に象徴されるように,過剰な擬人化は人と動物の双方にとって好ましくない.ということが頭では分かりつつも,その愛らしい姿を見ていると,愛情を注ぐことと一定の距離を置くことのジレンマに陥ってしまう.本稿では,このジレンマを問題意識の基調としつつ,つれづれなるままに動物の愛護管理に対する所感を,個人的な見解として述べさせていただくこととする.雑駁な総説で恐縮至極であり,本誌の品位と格調を損なうことが危惧されるが,獣医学には縁遠い門外漢のざれ言としてご容赦を頂きたい. |
1.自然環境行政との親和性
平成13年1月の省庁再編に伴い,動物愛護管理法は総理府(現在の内閣府)から環境省自然環境局に移管された.これは,内閣府にとっては「内閣府行政のスリム化」,環境省にとっては「動物行政の一元化」などといったメリットが期待されていたものである.今だから言えることかもしれないが,正直なところ,動物愛護管理行政の環境省への移管の話を初めて耳にしたときは,晴天のへきれきに近いものがあった.環境省において自然環境行政に携わっている同僚も同じ気持ちであっただろう.また,後で分かったことであるが,このことは動物の愛護管理に関わっておられる多くの団体の方々についても,似たり寄ったりの気持ち(反応)であったらしい.
しかし,実際に動物愛護管理行政を担当してみて,その印象はがらりと変わった.今では,環境省にこそふさわしい行政分野であると考えている.これは,意外に思われるかもしれないが,その基本的な部分については自然環境行政との類似点が多く,極めて親和性が高いことによる.主な類似点としては,次の2点が挙げられよう.
| [1] |
行政目標が人・地域・時代によって変わること
双方とも,公害行政などのように絶対的かつ定量的な基準や目標を定め難い,人の価値観に基づく行政分野であること.動物の愛護管理の目的等に関する考え方は,「自然環境の保全(景観や野生生物の保全を含む)」と同様に,人・地域・時代によって異なる多様なものであり,絶対的かつ固定的な一定の解を見出せるものではない. |
| [2] |
行政手法及び実行主体が多種多様であること
人の価値観に依拠する行政分野であることから,社会的に認知された「理念」のもとでの意識や行動の改革を行うための普及啓発が重要であること.こういった意味では,規制的手法は過渡的な対症療法的性格のものである.警察行政や社会資本の整備行政等と異なり,「学」や「民」の果たすべき役割が大きいことから,官・学・民の連携(政策実行主体の多様化)が必要不可欠となる. |
|
2.動物愛護管理のパラダイムの構築
| (1) |
ロマン主義的動物愛護管理行政からの脱却
狩猟や漁労が中心であった縄文時代には思いもよらなかったことであろうが,動物の愛護管理は,時の経過とともに,動物愛護の精神が国民の間に普及・定着し,社会的規範として法制化されるにいたっている.動物愛護管理法の目的は,「国民の間に動物を愛護する気風を招来し,生命尊重,友愛及び平和の情操の涵養に資すること」,「動物による人の生命,身体及び財産に対する侵害を防止すること」の2つとされている.この目的から見て取れるように,動物愛護管理法制の基本的な部分を構成してきた虐待や遺棄の禁止規定の法益は,動物の生命・身体の安全そのものを直接の保護法益としているものではない.わが国の国民の間に一つの法規範にまで高められた動物の愛護管理の精神を一つの社会的秩序として保護しようとするもの,すなわち,動物の愛護管理の良俗を保護しようとするものである.
このような動物の愛護管理の良俗は,人間に備わっている基本的な道徳律の自然な拡張であると考えることもできる.多くの文化・個人の倫理観の根底的な部分には「自分がして欲しくないことを相手にしてはならない」,「他人をむやみに苦しめてはならない」という道徳律が存在する.人類の倫理の歴史は,これらの道徳律等にいう「相手」や「他人」の範囲を拡張することで進んできており,こうした拡張を人類という種の境界で終わりにする理由はないと考えられている.
しかし,このように法規範にまで高められている割に,その理念や哲学は,茫漠としたままにとどまっている.情緒に頼りすぎているきらいが強く,論理的に整理されていないという言い方もできる.動物愛護という言葉が,一般的には,情緒的・感傷的・個人的なニュアンスが強い言葉として受け止められがちであることや,野生生物の保護などが種レベル〜個体群レベルを主対象にしているのに対して,動物の愛護管理は,動物の個体を主対象にしていることなども影響していよう.もちろん,動物をかわいい・かわいそうという気持ちは大事である.これがすべての根源的原理になることはいうまでもない.しかし,かわいい・かわいそうという思いだけに依存して,ときとして刑罰を課すことを必要とされる行政を行うことはできない(図1参照).かわいい・かわいそうを含みつつも,これを凌駕した動物愛護理念の構築が必要ではないだろうか.たとえば,花鳥風月という言葉があるが,人が人として生きるために身近な自然(緑)が必要とされているように,犬やねこの存在も健全な社会・社会人の形成にとって欠かせない存在なのかもしれない.また,ペットという人類が長年かけて作出してきた愛玩動物は,人類にとっての社会的・歴史的財産であるということなのかもしれない.
余談であるが,昭和時代の自然環境行政は,「なぜ,自然を保護しなければならないのか?」といった命題との闘いの歴史であったと思っている.現在は,地球環境問題に象徴されるように,人類の生存基盤である環境を守らなければ,いずれは人間自体も生存できなくなるなどということが,一般常識として市民権を得ている.時代の変化には驚かされるばかりである.しかし,稀少種であるトキやシマフクロウの保護のような個体レベルの問題,里地里山の保全のような地域的な問題になると,依然として「資源利用や学術研究対象としての潜在的な有用性又は生態系の構成要素としての未知の機能」という苦しい(?)説明にとどまっており,ある意味「ロマン主義的自然保護」の域を脱しきれていない感が強い.このような状況においては,ましてや個体を対象とした動物愛護管理行政がロマン主義にとどまっているのは必然であるかもしれない.この課題は,自然環境行政と動物愛護管理行政の双方において,多分に同時決定的に整理されるものであろうし,答えを導き出すための糸口には共通項があるような気がしてならない. |
| (2) |
日本の社会風土にあった動物愛護管理の模索
わが国における近世の動物の愛護管理の思想や活動は,日本在住の欧米知識人によって主導されてきたものである.しかし,日本人と動物とのかかわりの歴史をみると,欧米諸国に比べてわが国の動物の愛護管理が内容的に劣っていたわけではなく,文化的な背景の違い等に起因する動物に対する意識(動物観)の違いが大きく影響していたと評価する人が少なくない.実際,各種の著述や調査研究によっても,日本と欧米諸国における動物に対する意識(動物観)の違いがあることが明らかにされている.表1は,その違いを概括的に示したものであるが,日本の風土や国民性を踏まえた動物の愛護管理の思想の存在が垣間見られる.
こういったことを踏まえて,単純な欧米追随にとどまらない,日本ならではの動物の愛護管理を構築する必要があると考えている.いわゆる和魂洋才である.しかし,気をつけなければならないのは,アニミズムや仏教思想の影響を,すぐれたこととして過重に評価することである.わが国における人と動物(自然)との関係に関する考え方や態度の特徴は,[1]「不殺生戒」に基づく動物の殺傷の罪悪視,[2]「山川草木悉有仏性(さんせんそうもくしつうぶっしょう)」思想による,人間と動物とは生命的に平等であるという考え方,[3]「輪廻転生」思想による,人間と動物とは生命的に連続であるという考え方の3つであるといわれている.しかし,この考え方は総論的な理念であり,「畜生(道)」という言葉に象徴されるように,人間と動物とはすべての面において同値(対等)としてみなしているわけではないという平等主義をとっているものであろう.
また,現実生活の中では,人間は動物等を食料としなければ生きていけないことから,動物の捕獲等を許容するとともに,供養や供儀などといった形で,動物の捕獲等に伴う「罪責の思い」や「心の痛み」を解消・軽減する方法(いわゆる免罪方法)が組み入れられているといった柔軟な思想体系を形成しているといわれている.
このようにわが国の動物愛護管理の考え方は,人間と動物とは生命的に平等であるとする総論的理念と,動物の捕獲等に伴う罪責の思い等を免罪するシステムの並立という柔軟性に富んだ体系になっている.しかし,このような多義的な複合構造になっているが故に,これらの間のバランスがくずれた場合には,色々な形で歪みが生じるおそれがあることを指摘しておきたい.わが国では不殺生戒が浸透しており,動物の供養をすることが慣習になっていることから,動物愛護管理が国民意識として定着しているという理解は,あまりに単純かつ皮相的に過ぎるきらいがあるというのは言い過ぎであろうか. |
|
3.動物の愛護管理のあり方の検討
自由民主党では,この3月から動物愛護に関する小委員会(北村直人委員長)が動き出した.動物愛護管理法の改正を視野に入れつつ,検討を進めていく予定であるといわれている.他の党派においても関心が高まりつつあるようである.環境省でも,平成11年の法改正時に付けられた附則や附帯決議に適確に対応できるような準備作業を行うために,動物の愛護管理のあり方検討会(竹内啓座長)を設置して,動物愛護管理法の施行状況等に係る調査検討を始めているところである.今夏には中間報告をまとめるとともに,遅くとも来年の春までには報告書をとりまとめる予定である.
動物を命あるものとして位置づけ,動物取扱業の届出規制や周辺環境の保全勧告等の措置を導入した平成11年の法改正は,マイルストーンになるであろう画期的な法改正であった.しかし,動物愛護管理行政の裾野は広く,深遠である.動物取扱業のさらなる適正化,個体登録措置の推進,近隣への迷惑の防止,災害時対策,実験動物や畜産動物の福祉の向上,動物の殺処分数の減少,産官学民の連携のあり方などの課題が山積している.
早いもので,動物愛護管理行政が環境省に移管されてから3年が経過した.石の上にも3年というが,環境省の力量を問われる時期にさしかかっている.自然環境行政の一分野として,環境省においても明確なポジショニングができているとは言い難い状況であるが,動物愛護管理行政は,将来的な発展可能性の小さくない行政分野であると思われる.環境省への移管が,適切な歴史的評価を得ることができるように精励しなければと身の引き締まる思いである.末稿になるが,引き続き,獣医師諸兄のご指導とご協力をよろしくお願いする次第である. |
![]()
 冒頭から私事で恐縮だが,3年前から猫を飼い始めた.ペット禁止の官舎暮らしが長かったため,動物を本格的に飼うのは,約30年ぶりである.田舎育ちなので,子供の頃は,犬,猫に始まり,ウサギ,チャボ,カナリア,コイ,熱帯魚,スズムシなど,実にいろいろなものを飼った経験がある.久しぶりに猫を飼ってみて驚いたことは,まさしくペットが「家族の一員」になっていることである.ここでいう家族の一員とは,「心と時間と空間の隙間を埋めてくれる存在」という意味である.「心」とはやすらぎや優しさをもたらしてくれること,「時間」とは話し相手や遊び相手になってくれること,「空間」とは添景として生活空間にほのぼのとした暖かさを醸し出してくれるということである.しかし,バンビシンドローム問題に象徴されるように,過剰な擬人化は人と動物の双方にとって好ましくない.ということが頭では分かりつつも,その愛らしい姿を見ていると,愛情を注ぐことと一定の距離を置くことのジレンマに陥ってしまう.本稿では,このジレンマを問題意識の基調としつつ,つれづれなるままに動物の愛護管理に対する所感を,個人的な見解として述べさせていただくこととする.雑駁な総説で恐縮至極であり,本誌の品位と格調を損なうことが危惧されるが,獣医学には縁遠い門外漢のざれ言としてご容赦を頂きたい.
冒頭から私事で恐縮だが,3年前から猫を飼い始めた.ペット禁止の官舎暮らしが長かったため,動物を本格的に飼うのは,約30年ぶりである.田舎育ちなので,子供の頃は,犬,猫に始まり,ウサギ,チャボ,カナリア,コイ,熱帯魚,スズムシなど,実にいろいろなものを飼った経験がある.久しぶりに猫を飼ってみて驚いたことは,まさしくペットが「家族の一員」になっていることである.ここでいう家族の一員とは,「心と時間と空間の隙間を埋めてくれる存在」という意味である.「心」とはやすらぎや優しさをもたらしてくれること,「時間」とは話し相手や遊び相手になってくれること,「空間」とは添景として生活空間にほのぼのとした暖かさを醸し出してくれるということである.しかし,バンビシンドローム問題に象徴されるように,過剰な擬人化は人と動物の双方にとって好ましくない.ということが頭では分かりつつも,その愛らしい姿を見ていると,愛情を注ぐことと一定の距離を置くことのジレンマに陥ってしまう.本稿では,このジレンマを問題意識の基調としつつ,つれづれなるままに動物の愛護管理に対する所感を,個人的な見解として述べさせていただくこととする.雑駁な総説で恐縮至極であり,本誌の品位と格調を損なうことが危惧されるが,獣医学には縁遠い門外漢のざれ言としてご容赦を頂きたい.