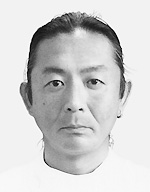![]()
|
獣害問題とそれに関わる獣医師の役割
今井康仁†(秋田県獣医師会会員)
| バブル期に青春を過ごした都会暮らしの申し子のような私達が,白神世界遺産のお膝元のこの町に引っ越してすでに4年が経過した. 大自然の中での生活はすべてが想像を絶することばかりだったが,一番驚いたのは人間より圧倒的多数の野生動物たちに毎日囲まれて暮らすことだ.少し前にも近くの海でタコ捕りをしていた人が熊に襲われた.熊のテリトリーが山から民家を通り越して海岸線まで到達しているのである.自然が豊かだなと,のどかに感動していられる場合ではない.命にかかわることである.動物と背中合わせに生きる人間の緊張感を生まれて初めて実感することができた.都会では想像したこともない厳しい現実である. この町はまた,猿の被害も半端ではない.毎日耕作地のどこかに猿の群れが出没し作物を食い荒らしている.カボチャ畑や豆畑は毎年ほぼ全滅である.なかには畑に出ると猿に脅されるため耕作地を放棄する人もいる.私の家の周辺にもたびたび,猿の群れが出没する.その数たるや圧巻で,まるで猿山に人間が住んでいる感じである. あまりにも猿の被害がひどいので獣医師として何かお役に立てればと,引っ越して以来,県に学術研究捕獲の許可を頂き,役場や地元の方々の協力も得て猿害の研究を続けてきた.そして,2年前程からその実績が認められ,役場と二人三脚で本腰を入れた猿害対策を研究,実施するまでに至った. 野生動物の食害の研究自体は別段目新しいものではないのだが,実際に携わってみて獣害対策に獣医師が携わる必要性を強く感じることがたびたびあった.その実態について現場での現状も交えて以下に述べてみたい. 獣医師がすぐにでも提唱しなければならない問題は,猿害と潜在的に存在する人と動物の共通感染症の危険性についてである. 近年,SARSやニパウイルスのような新種のエマージングウイルスによる新たな共通感染症の脅威が話題となっている.特に,ニホンザル等の霊長類は古くからエボラ出血熱,マールブルク病,Bウイルス病,猿痘等の致死率の非常に高い感染症の媒介者として広く知られている.このようなウイルスや新種のエマージングウイルスがひそかに上陸し,野生のニホンザルに蔓延してしまうことはもはや絵空事とはいえない段階にある. 事実,Bウイルスは国内で検査したニホンザル67頭のうち11パーセントが陽性であったとの報告がある.Bウイルスは咬まれたり,引っかかれたり,傷口や粘膜に猿の唾液が付着したり,猿の血液の付着した針の刺入等で感染する他,人間同士の伝染も確認されている致死率の非常に高い感染症である. 通常,野生動物の行動域を調査する際には麻酔をかけ,発信機の付いたカラーを装着する.この処置を施すに当たって,相当数の現場では獣医師免許を持たない者が麻酔等を行っている.そのため,処置中の麻酔等による事故がしばしば起こっていると聞く.さらに,感染の可能性等に注意しながら処置を施さなければならないという情報も行き渡ってないため,素手でニホンザルの処置をし,その後の消毒などもまったく行われていない.驚くことに,動物同士の感染を助長する使用済み注射針の使い回しや,現場での針の遺棄も一部では行われているらしい.また,劇薬指定の麻酔薬もその多くが獣医師の管理に委ねられないまま放置されており,いつ盗難等の事件が起こってもおかしくないという危険にさらされている. さらに,被害地では日本猿の唾液,糞尿による農作物汚染の可能性も深刻である.ニホンザルは耕作地に入ると必ずと言っていいほど糞尿をしてまわる.特に収穫期間際にはいると,農家は気が付かないまま糞尿や唾液のついた作物を収穫してしまう.収量の少ない作物なら糞尿の異臭で気が付くこともあるがほとんどは気がつかれることもなく,唾液や糞尿の交ざった不衛生な作物が出荷されてしまっている.感染症と直接の因果関係は明らかではないものの,衛生的にはきわめて危険な状態だと思われる. また,観光地で猿に咬まれたりしているテレビ報道がよくあるが,一般の人にウイルス感染の危険性について緊急に情報公開するべきではないだろうか. 次に,提唱しなければならない問題は捕獲した動物の処置方法である.ある地方では,安楽死と称していまだに撲殺等の殺害方法をとっており,そのような地域では安楽死の概念自体を一から啓蒙しなければならない. このように,野生動物の保護管理の内情は獣医学的に見ても,まだまだ前時代的と言わざるを得ない状況である.また,行政は行政のみ,サルの専門家はサルの調査だけ,駆除の担当者は駆除だけ,という典型的な縦割社会が獣害の現場ではいまだに大手を振って通用しており,本当に救済しなければならない被害者はまったくお座なりになったままという状態もしばしばである. このような状況を改善するために,獣医師も野生動物との軋轢の現場に立ち,人間にも動物にも配慮できる公平な立場で,獣害問題全体を公衆衛生学的な観点も含め積極的に提唱する必要があるだろう. 害獣としての野生動物に対して,獣医師が組織としての関わりが希薄であったことは諸外国と比較しても特異なことであり,獣害問題における獣医師の使命のあり方を今すぐ検討しなければならない時期に来ているのではないだろうか. 獣医師諸兄の活発な議論が待たれるところである. |
|
| † 連絡責任者: | 今井康仁(八森動物診療所) 〒018-2605 山本郡八森町岩館塚の台86-6 TEL 090-9321-9213 |