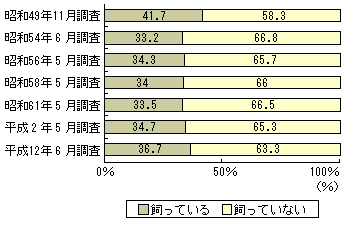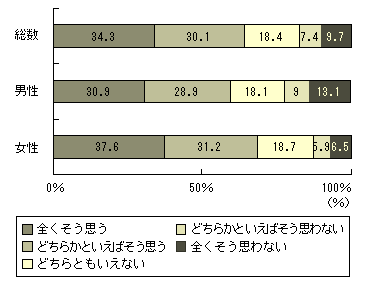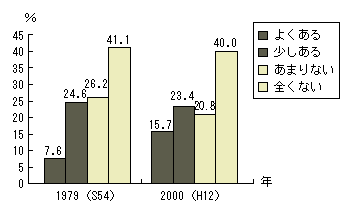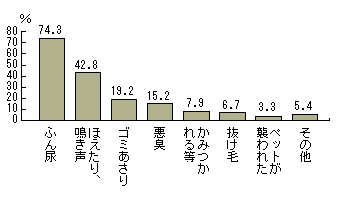![]()
|
家庭動物の飼養保管基準の徹底に当たって
獣医師に期待するもの
神田修二†(環境省総合環境政策局環境影響評価課評価技術調整官 前自然環境局総務課動物愛護管理室長) |
||||||||
 1.は じ め に 1.は じ め にペットブームと言われ,動物飼育志向の高まり(図1),家庭における動物の位置付けの高まりを背景として,人と動物が共生できる社会づくりが課題となっている.その実現には,飼い主一人一人の責任の自覚と実践による適正飼養の確保が不可欠であることから,環境省では,改正動物愛護管理法に基づき,適正飼養の新たな規範となるべき「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(家庭動物等の飼養保管基準)」を平成14年5月28日決定した.本基準の詳しい内容については,本誌第55巻第5号320〜327頁において,本基準の作成作業に携わってこられた(社)日本動物保護管理協会事務局長 山口安夫先生が解説されているので,そちらをご参照いただくこととし,本稿では,そのねらいとポイントのみをあらためてご説明させていただきながら,目下の大きな課題となっている基準の周知,徹底の上で,特に大きな役割を担っていただくことを期待している獣医師の方々の役割について,思うところを述べてみたい.
2.家庭動物等の飼養保管基準のねらいとポイント 都市化や核家族化の進行,さらには少子高齢化は,ペット動物に対するわが国の国民意識に大きな変化を与えてきたと言われている.家庭で飼育される動物が,ペットとして愛玩の対象となるだけでなく,家族の一員さらには人生のパートナーとして認識されるようになってきている(図2).ペットブームが言われているが,必ずしもそれは飼育される動物の数の増加として,現れているのではなく,むしろ飼育する人間にとっての動物の位置づけ,認識の変化に表れていると言える.
家庭における動物飼育の志向は,今後,さらに高まるものと考えられるが,一方で,動物を巡るトラブルが近隣の迷惑問題として全国的に広まっていることも,また事実である(図3,4).
ブームにのって,ペットについての一面的な情報のみが氾濫し,飼育のために必要とされる基本的知識,認識が不十分なケースも多いなど,動物飼育に関する国民の認識は残念ながら未成熟といわざるを得ない.このような現実を反映して,世論調査(平成12年6月実施 動物愛護に関する世論調査 総理府)では,動物愛護政策の要望の第一が「飼い主の迷惑行為に対する規制や指導を強める」となっているのである(図5). |
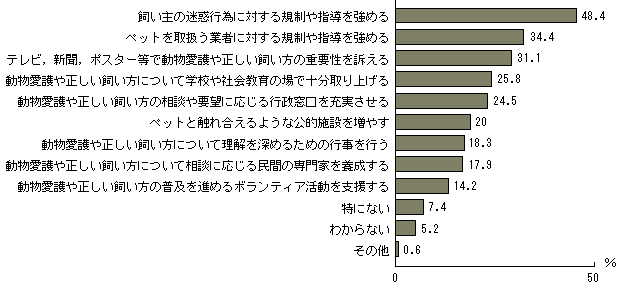 |
| 図5 世論調査(平成12年6月調査) 設問:「動物愛護政策に対する要望」 |
| 「家庭動物等の飼養保管基準」は,このような背景のもと動物愛護管理法の目指す人と動物が共生できる社会実現へ向けた,適正飼養の新たな規範として,策定したものであり,飼い主責任による適正な飼養のルールとしてはもちろんのこと,行政の施策面では飼い主に対する普及啓発,指導の基本として,さらに動物飼育に関する社会共通の目標となることが期待されている. 基準の主なポイントとしては,1)すべての不適正飼養の元凶といえる動物の衝動飼(買)いの防止,2)多頭飼育の弊害防止,遺棄防止,行政による犬猫の引取数の抑制等のために不可欠である不妊去勢等繁殖制限の徹底,3)飼養者責任による人への被害(迷惑害を含む)防止の徹底,4)飼養者責任の明確化のための所有の明示(個体識別措置),さらには,ペット動物等の不適正飼養が移入種問題の原因となっていることを踏まえた,5)自然環境保全への配慮,等があげられる. |
| ◎飼養に先だつ配慮 そのうちでも,最も重要かつ基本的なものとしてあえて,強調したいのが,飼育開始前における必要な知識の修得と,それに基づく飼育の慎重な判断を求める規定である.「命ある」ものである動物の生涯を預かることへの正しい準備(と覚悟)を求めること,が家庭動物をめぐる問題解決の最も基本となると考えられるからである. 「今すぐに飼いたい」,「かわいい」,「珍しい」といった一時的な感情や衝動的な動機のみで,十分な知識のないまま安易に飼い始め,結果として,飼い主が飼いきれなくなる例は,後を絶たず,そのような理由で,都道府県等が引き取らざるを得ない犬と猫の数は,(近年着実に減少しつつあるものの,)合わせて全国で39万頭に及んでいる.また,遺棄された動物が野生化し,在来の野生動物を捕食したり圧迫する等,自然環境保全上の問題も全国各地で生じている.飼育の放棄に至らないまでも,このような安易に飼い始めた者に対しては,適正な飼養を後から求めることは,至難の技と考えるべきで,当然トラブルや虐待を引き起こす一因となり,そのしわ寄せは近隣のみならず,動物に及ぶ結果となる.このため,改正法では動物販売業者に,動物の購入者に対し当該動物の適正な飼養保管の方法について,必要な説明を行い,理解させる責務を新たに課したところである.本基準においては,それに対応し,購入者に対しても,購入に先だって,当該動物の生態,生理(寿命を含む),飼養方法等の動物の特性に関して十分な知識をもとに,現状での飼育の可能性,さらには,住宅環境や家族構成の変化など飼い主の将来的な生活設計を踏まえ,終生飼養ができるかどうか,慎重に判断,選択することを求めている.つまり,動物の飼育についてのネガティブな側面についても考えることを求めているわけで,伴侶,コンパニオンとしての存在,癒しの効果などといったポジティブな側面がもてはやされている社会の流れに,ある面で水をさす内容といえる.動物は誰でも飼えるわけではない,命を預かる以上,その意志や力がない者は,飼うべきではない,自らの責任で飼える者だけが,飼うべき資格があると言外に言っているからである.動物を飼う自由,動物との生活を享受し,恩恵を受けることができる自由は,経済的に可能であるかどうかではなく,また法的に禁じられているかどうかだけでもない,命ある「動物を飼うこと」の意味,責任から必然的に制限されるべきであることを特にここで強調したいところである.現在,起きている動物飼育を巡る多くの問題を総合的に見据えると,動物の飼育の本質を見直すことが,今,求められているのではないか.法や基準では,「いかに飼うか」は問うことまではできても,どういう場合に飼うべきか,また,どういう場合に飼うべきでないかといった,飼育を通じた人と動物の関係のあるべき姿まで提示することはできない.今こそ,この点の本質について,広く関係者の間で議論され発信されることが求めらていると思う. 獣医師の方々は,人と動物との関係の中で業務を行ってこられている,人と動物の関係の専門家として,動物の飼育は,いかにあるべきかを訴える上で,重要な役割を果たし得る存在と考えている.先に述べたように動物の飼育効用,恩恵といった点にとどまらず,動物の命を管理する責任を踏まえたトータルな意味であるべき飼育(より良き関係)の姿を是非発信いただきたいと思う.ペットの衝動買いを推奨するかのようなTVコマーシャルが放映されるやいなや,このCMに登場した犬種であるチワワがペットショップにおいて人気が急騰してしまう現実が一方であるのである.また,かわいい写真を目玉にした雑誌のペット特集や,TVの番組は,安定した人気を保っている.なかなか抗しがたいこれらの力とバランスがとれるような「動物飼育あり方」の広い視野での議論と冷静で力強いメッセージが必要となっている.昨年の動物愛護週間中央行事で,「野生動物の飼養のあり方を考える」をテーマにシンポジウムを開催し,野生動物飼育の問題点を浮き彫りにしようとしたのはその一つの試みである.動物愛護週間という「動物愛護」の,伝統ある中心的な普及啓発の場で,飼育の是非まで問うた新しい試みであったが,今後の普及啓発の大きなテーマとなると考えている.このような中,本年3月23日,朝日新聞(地方版)に横浜市獣医師会が掲載した意見広告「野生動物には野生の生活を」は,野生動物をペットと飼育することへの警鐘として説得力あるものであったと思うし,大変心強いものがあった.動物の飼育,動物の生理,生態の専門家集団である,獣医師の方々の,この分野での今後の力強いご支援ご協力を確信させていただいた次第である. |
| ◎飼養者の適正な飼養保管に関する責務 基準において,獣医師の役割が明示されているものをあげれば,「第4の2 健康及び安全の保持」の項において,「疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに,疾病にかかり,又は負傷した家庭動物等については,原則として獣医師により速やかに適切な措置が講ぜられるようにすること.」が規定され,さらに,「第4の7 動物に起因する感染性の疾病に係る知識の修得等」において,「所有者等は,その所有し,又は占有する家庭動物等に起因する感染性の疾病について,動物販売業者が提供する情報その他の情報をもとに,獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ることなどにより,正しい知識を持ち,その飼養及び保管に当たっては,感染の可能性に留意し,適度な接触にとどめるなど,自らの感染のみならず,他の者への感染の防止にも努めること.」と規定されているところである. これらの規定は,獣医療行為を専門とする獣医師の役割として,直接的なものであり,当然の期待されるべきものと考えるが,このほか,「第7 学校,福祉施設等における飼養及び保管」において,「1 管理者は,動物の飼養及び保管が,獣医師等十分な知識と飼養経験を有する者の指導の下に行われるよう努め,本基準の各項に基づく適切な動物の飼養及び保管ならびに動物による事故の防止に努めること.」と,飼育動物に関する知見,経験を有する専門家としての獣医師の役割に期待した規定が設けられている.学校,福祉施設等で飼育される動物の適正飼養の確保については,教育,福祉の場として,その動物の取扱いが,児童生徒等関係者へ大きな影響を与えるとともに,また,家庭と異なって組織としての適切な責任体制が必要であるという性格から,動物の飼養保管が,獣医師等十分な知識と飼養経験を持つ者の指導のもとに行われる必要があると考えられているからである.現在,「学校獣医」を置くなど,各地で地域の獣医師団体の協力のもとに,学校での動物の適正飼育を改善していこうとする取組が進められている.そのような実績をふまえ,盛り込まれた規定であり,さらにこれらの先進的な取り組みが各地に広がることを期待しているところである. また,所有者を明示する適切な措置の推進や,繁殖制限措置の徹底,猫の室内飼養の推進等の規定は,獣医師との明示はないものの,それぞれ,獣医療行為そのものであったり,動物の生理,生態に関する専門的知見に基づく,助言等が不可欠な分野となっている.特に,多頭飼育による弊害防止,遺棄防止,行政による犬猫の引取数の抑制,等のために不可欠となる不妊去勢等繁殖制限の徹底は,重要なポイントである.飼い主が,誕生するすべての命に対し,責任を負うことは一般に困難であるから,原則として繁殖制限すべきことが規定されている.不妊去勢等の手術の実施率は,着実に増加しているものの,まだまだ地域差も大きく,その効果を考えれば,一層の普及啓発が重要な分野である.総理府が平成12年に実施した世論調査では,不妊去勢措置を講じていない飼い主の理由として,最も多かったのが,かわいそうだから(26.3%)となっている.適切な情報提供,助言で,誤解を解いていくことにより,不妊去勢はさらに着実に進められると考えられる. 所有者の責任の自覚,逸走時の識別等を図るためは,改正法で新たに規定された所有者明示措置の徹底も重要な対策であり,基準では,名札,脚環,マイクロチップ等の,耐久性,実績のある適切な方法を例示し,その推進を図る内容となっている.マイクロチップについては,海外では多くの実績があり有効性が示されているが,国内では例がまだ少く,飼い主には,不安が多いと聞く.適切な情報提供が,知見,技術を持つ獣医師から行われることが普及には効果的であろう. さらに,新たに基準に盛り込まれた猫の室内飼養に関しては,猫の健康,安全の保持の観点あるいは,迷惑害の防止に観点から有効であり,実績のある飼い方であるにもかかわらず,まだまだ猫の習性に反すると思いこんでいる飼い主も多い.専門的見地からしても,猫の生態,生理に照らして妥当な飼い方であることを,広く説明し,普及する取り組みがさらに求められている. |
| 3.適正飼養推進に向けた基準の徹底 家庭動物の適正な飼養は,国民一人一人の意識や生活に密接な課題であって,国民の理解と協力がその基礎になければ到底その実現はかなわない.動物愛護管理法では,適正飼養の実現を,違反行為に罰則を課する等の強制的な制度によるのではなく,普及啓発という誘導的な手法によることとされている.このため,改正法で新たに設けられた制度が,動物愛護推進員制度,協議会制度である.これは,地方自治体,関係民間団体の連携のもと,飼い主の身近に,適正飼養の普及,助言等ができる有識者によるサポート体制として,動物愛護推進員を地方自治体が委嘱,配置しネットワークを構築していこうとするものである. 家庭動物等の飼養保管基準により具体化された飼い主の責務,適正飼養を推進していくためには,地域に根ざしたこの動物愛護推進員活動を通じ,効果的に周知,徹底を図っていくことが,今後,重要となっている. 動物愛護推進員は,地域における犬,猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者から都道府県知事等が委嘱する者とされ,推進員の活動としては,(1)犬,ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性についての普及啓発.(2)不妊去勢等繁殖制限措置に関する必要な助言,(3)譲渡のあつせん等の支援,(4)国又は都道府県等が行う施策への必要な協力,があげられている.また,これを支援するための協議会は,都道府県等行政機関の他,動物の愛護を目的とする公益法人,獣医師の団体,その他の団体等から組織され,動物愛護推進員委嘱の推進,推進員の活動に対する支援等についての必要な協議を行うこととされている.このように制度上,動物の健康管理のみならず,動物の生理,生態の専門家,いわば動物と人との関係をつかさどる業務に携わる獣医師及びその団体の協力のもと,はじめて機能する仕組みとなっているのである.この点からも,家庭動物の飼養保管基準の周知徹底,つまり適正飼養の徹底に関しては,今後,獣医師各位の一層のご協力なしには考えられないものである.平成14年度までに,18の都道府県等において動物愛護推進員の委嘱が行われ,さらに,6の都道府県が今後,推進員の委嘱を行うところと聞いている.さらに多くの地域において,推進員活動が展開されることが期待されるが,各地の獣医師会ならびに獣医師の方々には,その中心的役割を果たすことを期待している. 本年2月に開催された平成14年度獣医師三学会の合同年次大会,一般公開合同シンポジウムでも紹介された,沖縄県の「ヤンバルクイナたちを守る獣医師の会」の取り組みは,まさにその期待を裏付ける十分な実績の一つとして挙げられる.独特の生態系を形成している沖縄本島ヤンバル地域では,人が放ったマングースや捨てられ野生化した猫が,ヤンバルクイナなど貴重な固有種を捕食し,深刻な影響を与えている.これを放置すれば種の絶滅など取り返しのつかない事態を招く結果となりかねない.緊急的な対策であるこれら移入種の駆除対策を環境省と沖縄県が進めている中で,沖縄県在住の獣医師有志からなる,この「ヤンバルクイナたちを守る獣医師の会」では,根本的な対策となる猫等の適正飼養,遺棄防止を総合的に進めようとする活動を行っている.やんばる地域の村々での飼い猫の避妊・去勢の実施や,パネル展,HPなどでの啓発活動,個体識別手段としてのマイクロチップの普及活動,捨て犬・猫防止パトロール,室内飼養など猫の飼い方についての普及啓発など,適正飼養の徹底のための獣医師ならではの幅広い活動を,地元地区の方々,学校をも巻き込んで展開されており,まさに,家庭動物の飼養保管基準の目指す適正飼養を地域に根ざした活動により普及するモデルとなっているのである.環境省では,このような活動を参考に,平成15年度から新規事業「飼養動物との共生推進総合モデル事業」をこの沖縄県において実施し,全国のモデルとして展開することとしている. |
| 4.お わ り に 繰り返し述べてきたように,今後,家庭動物等の飼養保管基準を広く的確に周知,徹底していくことが,大きな課題である.このため,国,地方自治体,関係団体が連携して,地域に根ざした,地道で効果的な活動を広げていくことが不可欠であり,地域にあって,適正飼養の活動をリードするに足る専門的知見,経験を有する存在である,獣医師の方々が,そこで果たしうる役割については,これまで述べてきたとおり強調しすぎることはないと考えている.動物飼育のあるべき姿を発信し,リードし,さらに適切な指導,助言で支える,専門家一丸となった一層の活動が期待されているわけである.21世紀の一つの課題とも言える改正動物愛護管理法の目指すところの人と動物の共生できる,潤い豊かな,よりよい社会の実現のための積極的なご協力をお願いする次第である. |
| † 連絡責任者: | 神田修二(環境省総合環境政策局環境影響評価課評価技術調整官) 〒100-8975 千代田区霞ヶ関1-2-2 TEL 03-3581-3351 FAX 03-3581-2697 |