![]()
|
学校動物飼育を通して考える子供の教育
中川秀樹(横浜市 開業,横浜市獣医師会会長) |
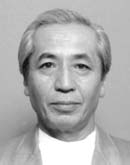 学校における小動物の飼育は,多感な成長期にある児童が動物と触れ合い,世話をしたり観察をすることを通じて,時には生命の誕生や死を経験をすることで愛しいと思う気持ちを育み,生命の神秘を感じることが情操の涵養と優しい心を形成することに効果があるといわれている.文部科学省も学校飼育動物は生活科,理科,道徳といった教科の中で教材として学習効果をもたらす他に,生命尊重,愛護思想,情操,触れ合いといった児童の精神や心を豊かにする教育的効果と重要性を認めて積極的に取り組みを始めた.平成14年度より改訂された小学校学習指導要領の中には『学校飼育動物』について詳細な記述がなされ,かかる問題は専門家である獣医師や獣医師会と相談して対応するよう明記され,学校飼育動物を適正な方法で飼育するために獣医師の持つ専門知識と指導が求められている.こうした教育的意義に鑑みて,予算措置を講じて地域獣医師会と連携して対応に努める自治体が多く見受けられてきたことは,公益的活動を通して社会貢献を目指す獣医師会の目的と整合性を持つものである. 学校における小動物の飼育は,多感な成長期にある児童が動物と触れ合い,世話をしたり観察をすることを通じて,時には生命の誕生や死を経験をすることで愛しいと思う気持ちを育み,生命の神秘を感じることが情操の涵養と優しい心を形成することに効果があるといわれている.文部科学省も学校飼育動物は生活科,理科,道徳といった教科の中で教材として学習効果をもたらす他に,生命尊重,愛護思想,情操,触れ合いといった児童の精神や心を豊かにする教育的効果と重要性を認めて積極的に取り組みを始めた.平成14年度より改訂された小学校学習指導要領の中には『学校飼育動物』について詳細な記述がなされ,かかる問題は専門家である獣医師や獣医師会と相談して対応するよう明記され,学校飼育動物を適正な方法で飼育するために獣医師の持つ専門知識と指導が求められている.こうした教育的意義に鑑みて,予算措置を講じて地域獣医師会と連携して対応に努める自治体が多く見受けられてきたことは,公益的活動を通して社会貢献を目指す獣医師会の目的と整合性を持つものである.一方,家畜保健衛生所も人と動物の共通感染症対策の観点から関心を示し,日本学術会議としても学校飼育動物の勉強会を始めたところである. こうした近年の認識の変化は,永年にわたり動物愛護の観点からこの問題に強い関心と係わりを持って活動してきた獣医師会あるいは獣医師の努力が結実してきているといえる. こうした論理に基づき学校飼育動物が注目される一方で,係わりを持つ関係組織がそれぞれ抱えている問題があることも認識しなければならない. 第一点は,指導要領にそって教育を行う学校現場には,予算不足による施設の不備,動物飼育の教育的効果を理解しつつ実践できる教員の不足,加えて,本年度より完全週休2日制が施行されたことによる休日の動物管理方法などの問題があげられる. 第二点は,支援をする獣医師会側には,学校により関心度に温度差があり,指導や助言が効果的に反映されにくいという現実と,すべての獣医師が関心と専門知識を持ち合わせていないこともある. 獣医師会は輪番ですべての獣医師が携わるのではなく,理解と関心を持つ獣医師によるプロジェクトチームを編成して対応と研鑽を計ることが必要ではなかろうか. 都市型社会では核家族化と少子化が進み,地域社会には子供のコミュニティーが減少し,また,近隣同士の交流や助け合いなども,たがいが干渉しないあるいはプライバシィーに立ち入らないという社会通念が定着してきたがために希薄化している.一方では,大人の自己中心的な考え方と学力偏重教育を押しつけられている子供達には,連携,友愛,思いやり,奉仕といった人間関係や,人間社会で不可欠な心を育む機会がきわめて減少している.こうした状況は,人間愛が希薄になってしまった社会が子供を育てているともいえる. 10歳以下の児童では,動物が好きという意志が90%を超える.その理由は,抱くと暖かい,動作や姿が可愛いなど精神的安定を求める気持ちや,愛しいと感じる純粋な感情の存在が見て取れる.学校での動物飼育は子供の人格形成に,こうした暖かで素直な心情を育む要素を持っていることである. 学校飼育動物に係わるさまざまな問題を解決していくことと,子供を取り巻く環境を整備していくためには,自治体,学校,獣医師会,地域社会がそれぞれの役割を認識しつつ手を携えて結集していかなければならないことは明らかである. その中心となり調整の役割を担えるのは,自治体,地域社会,学校現場と接点を持つ獣医師会をおいて他にはないと考える. 現在,学校で飼育されている動物は,うさぎ,ハムスター,にわとり,あひる,うずら,インコなどの小型動物が主体で,牛,馬,山羊,綿羊などの大型動物はきわめて少ない.大型動物の飼育が高い教育効果をもたらすという説もあることから試みることも必要であろう.また,不思議なことには,世界中のすべての人間社会で評価され飼育されている,身近な犬と猫が学校飼育動物として飼われていることが稀なことである. 学校で調査したところ,家庭に犬や猫がいる小学生は20%程度で,多くの子供達が犬や猫と暮らしたいと希望している. 子供には心の生育に大きな力を発揮する動物と,学校でも家庭でも地域でも触れ合うことができることが望ましい.また,動物の存在は大人と子供あるいは家庭と地域が触れ合う機会を作り,声をかけ合うことで人の輪が広がり,近隣と隔絶しているといわれる現代の人間関係を回復させる可能性も秘めている. 児童に怪我をさせる危険性がある,社会で触れ合う機会が多いので必要性がない,飼育施設や管理に経費がかかるなどさまざまな理由があげられるが,児童が望めば,自由に何時でもコミュニケートできる身近な動物の存在することが必要であろう. 時には,引っ掻かれたり,咬まれたりすることで動物というものを肌で感じ,人と同じように感情表現があることを体験を通じて理解し,思いやりや優しさの大切さが育まれる.施設や経費は他のことと比べれば大きな問題ではなく,教育に必要であれば手当てをしなくてはならない. 教育現場は児童を庇護するあまりに特殊化したり社会と隔絶してしまうのではなく,人の生活性や社会性を色濃く反映させる中で子供達を育成することこそが教育の本来の目的ではないかと考える. 岐阜県にある川上小学校では,昔から地元の保存犬である川上犬を子供達が学校で飼育して保存に貢献するとともに,人と犬の関わりを通してさまざまな体験を得ている.日本の中にもこうした教育現場があることも考慮すべきであろう. |