紹 介
日仏獣医学学術交流の定期化の兆し
―第6回日仏獣医セミナーの報告―
福 地 克 男1) 早 崎 峯 夫2) 1)おゝい動物病院(〒356-0051 入間市大井町亀久保705-7)
2)山口大学農学部(〒753-8515 山口市吉田1677-1(日仏獣医学会事務局))
| 日仏獣医学会(長谷川篤彦会長,日本大学教授)は1989年の創設以来,フランス側対応学会の仏日獣医学会(シャルル ピレ会長,アルフォール獣医大学教授,元学長,世界獣医師会フランス代表)と獣医学学術交流を重ねていて,日仏獣医セミナーの開催はこれまでに日本にて2回,フランスにて3回の計5回行われてきた(日本獣医師会雑誌,52(8),536-537,1999). このたび,仏日獣医学会主催により,第6回日仏獣医セミナーがフランス,ニース市にて9月15〜16日に開催され,日本からは,五十嵐幸男日本獣医師会会長をはじめ多数の方々が参加され,有意義な学術交流を持つことができた.このセミナー出席旅行にはリヨン獣医大学訪問も日程に組み込まれていて,実に興味深い訪問となった. 第6回セミナーの開催は,昨年束京恵比寿の日仏会館にて開催された第5回日仏獣医セミナーへの出席のためにフランス各地の獣医大学の教授ら4名とともに来日されたピレ教授が,滞在中に次回の開催を提案してこられたのを受けて,今年日本から学会出席ツアーを組んで出掛けて行ったものである.フランスには,アルフォール獣医大学(パリ・メゾンアルフォール),リヨン獣医大学,トゥールーズ獣医大学,ナント獣医大学の4つの国立獣医大学があり,本会はこの4校と1985年以来の交流の歴史を持っている.特に,アルフォール獣医大学とリヨン獣医大学には多くの親日派の教官がおり,われわれの重要な友人となっている. 第6回日仏獣医セミナーは第1日(9月15日)は日仏双方から計12題の学術発表が行われ,第2日(同16日)はフランスの獣医系ワクチンなどの製薬会社として世界的に有名なビルバック本社(Virbac)の研究所を副社長のC. Karst氏(リヨン獣医大学卒)のご厚意で訪問見学させていただいた. 第6回セミナーへのフランス側の参加者(発表者を含む)は,Ch. Pilet(ピレ)教授,C. Karst(カルス)博士(Virbac),G. Bourdoiseau(ブールドワゾ)教授(リヨン獣医大),P. Druilhe(ドルイーエ)教授(パリ・パストゥール研),A. Aubert(オベール)博士(Virbac),P. Devauchelle(デボシェル)教授(アルフォール獣医大),G. Andre-Fontaine(アンドレhフォンテーヌ)教授(ナント獣医大),G. Bufala氏(Virbac),J.P. Marc氏(Virbac)の9氏,日本側の参加者(発表者を含む)は,五十嵐日本獣医師会会長,長谷川日仏獣医学会会長,早崎峯夫教授(山口大),池田忠生教授(日大医),白井淳資博士(動衛研),小野寺 節教授(東大),新城敏晴教授(宮崎大),斎藤 聡先生(石山通動物病院,札幌市),福地克男先生(おゝい動物病院,埼玉県入間市),福地恭子氏(仏語通訳翻訳家),斎藤久美子先生(斎藤動物病院,浦和市),鹿田順子先生(アリス動物クリニック,埼玉県入間郡),臼井玲子先生(臼井犬猫病院,宇都宮市),それにアルフォール獣医大午後コース1年生灘波裕之君(本年3月東京農工大獣医学科卒,入試試験を合格して入学)・志津子さん夫妻の15氏の計24氏(写真1)で,少数ではあるものの,学術発表時のみならず昼食会や晩餐会での話も弾み,学術交流と友好親善の絆を強めるにはむしろちょうどよい人数であった.学会は,ピレ先生の歓迎の辞から始まり,五十嵐先生の答辞,続いてピレ先生から五十嵐先生へガストン ラモンGaston Ramonの肖像を彫ったブロンズメダルが贈呈された.ラモンはアルフォール獣医大卒の獣医師でかつパリ・パストゥール研の第4代所長(1940〜1941)を務めた高名な微生物学者で,アナトキシンの発見と免疫におけるアジュバントの役割についての研究で著明である.学術発表は長谷川先生の開会の辞でスタートした(表1).コーヒータイムも省略しても時間オーバーになるほど熱心に発表が続き,最後に早崎先生による閉会の辞と記念品(参加者一同から有田・伊万里焼きの皿,また白井先生からダルマさん)の贈呈が行われて和やかなうちに閉会した. 次の訪問地であるリヨンへは飛行機を使わずにフランスの地方の沿線風景を楽しむためにTGV(フランス新幹線)の5時間半の旅を選んだことはむしろ賢い選択であった.国土の約8割が平坦地で世界でも有数の農業・牧畜国フランスの,TGV沿線の雄大にして緑豊かな台地の連なりは,国土の8割が山岳か山間部であるわが国のそれとは一味も二味も違い,この国の「土」が滋味豊かで豊饒であることを思い知らされる. リヨン獣医大学では,学外交流委員会の副委員長M. Rachail-Bretin(ラシャイユ・ブルタン)女史(理事待遇)の出迎えを受け学内を案内していただき,また旧知のP. Delatour(デラトゥール)教授(中毒学),G. Keck(ケック)教授(臨床中毒学),さらにはこの6月にアルフォール獣医大学からリヨン獣医大学へ移ったJ.P. Cotard(コタール)教授(内科学),またフランス出張中のメリアルジャパン社社長のM. Lachauss仔(ラショセ)氏(フランス出張中),メリアル社のB. Saint-Marc博士(リヨン獣医大学卒,昨年まで福島の日本全薬メリアル社勤務),また新任のC. Chauve教授(寄生虫病学)らの歓迎を受けた.大学臨床施設の見学も印象深いが,パリ・アルフォールの先生たちのスマートで洗練されたパリジャン(パリっ子)の気風とまた一味も二味も違う,リヨンの先生たちの気さくで人情味にあふれるリヨネ(Lyonnais,リヨンっ子)の気風に触れて旅の疲れも飛んだ. リヨン獣医大学のケック教授の講座(臨床中毒学)は10年ほど前からEU領域における動物中毒110番センターとしても活動していて,EU内の各国から入る電話,ファックス,Eメールなどによる専門家や一般からの問い合わせや事故通報に24時間体制で受け付け,解毒・治療・予防法の指導を行っていることは実に興味深いものがあった.すなわち,わが国の臨床家の診療レベルも,分野によるが,世界と肩を並べるところまで到達した分野は少なくない.そのような現状の中で,獣医大学がいかに社会に求められる大学へと変貌して行かなくてはならないかという問題を考えるとき,特に臨床家が二次診療機関として頼りにする大学へと改善していかなくてはならないとき,臨床家がなかなか手を伸ばしきれないような,こういった臨床中毒学も大学こそがしっかりと押さえておくことは,今後の獣医大学が社会へ向かって目に見える形で貢献していくための1つの形(フォーム)として大変参考になった. 今回の訪仏で,われわれと仏日獣医学会会長ピレ教授の間で,今後このセミナーを2年ごとに日本とフランスで交互に開催していくことが申し合わされたことは,本会活動の一歩前進を示すものといえよう. 夜中(午後11時頃)に出発するわれわれをドゥゴール空港まで奥さんとともにわざわざ見送りに来てくれたピレ教授と次回のセミナー開催を約してフランスを後にした. 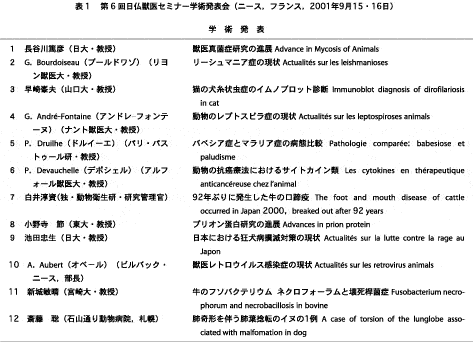
|
