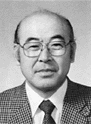 日本学術会議から「獣医学修業年限延長」の勧告(1971)が出されてから,学校教育法が改正(1983)され,12年を経過して6年一貫教育となった.しかしながら,獣医学教育が6年に延長された際に,教育内容を充実するための施設・設備や人的補充あるいは予算的な裏付けがないまま今日まで23年間を経過した. 日本学術会議から「獣医学修業年限延長」の勧告(1971)が出されてから,学校教育法が改正(1983)され,12年を経過して6年一貫教育となった.しかしながら,獣医学教育が6年に延長された際に,教育内容を充実するための施設・設備や人的補充あるいは予算的な裏付けがないまま今日まで23年間を経過した.
この間,日本における社会的な変化やグローバル化によって,獣医師に対する社会的要請が多様化すると同時に,動物医学の高度化が要求されてきている.また,国際的に対応できる獣医学教育の必要性が高くなっているが,現状の獣医学教育体制では,社会的または国際的に対応できる教育体制を構築することはきわめて困難な現状にある.これを改善するために国立の獣医学科は再編整備を行い,私立の獣医学科は自助努力によって獣医学部を構築し,教育内容の充実を図る努力がなされているが,いまだその成果
があがっていない.その成果を期待するには獣医界全体が一丸となってこれを支援する必要がある.また,日本獣医師会が試行する生涯研修事業や将来の専門医制度の施行にしても,わが国の獣医学教育の教育体制を学部教育とし,臨床応用獣医学の実務教育を充実して,これらの事業と連携すべきである.
さて,獣医学教育に対する社会的な要請と国際的な対応とは,どのような教育内容であるのか現実的な問題として取り上げてみると,それは動物医学や応用獣医学について現実の社会で実際に役立つ教育が要望されていることである.卒前教育で基礎獣医学や教養を身につけることはきわめて重要であるが,獣医学教育体制として動物病院や現場の実習で,実際に疾患動物に接した実務教育や海外研修等による諸外国の獣医学教育を体験し,卒後に職場で獣医師としての現実的な仕事ができるような教育体制を構築することが重要なのである.欧米の獣医大学で動物病院が発達した理由は,4学期後半の2年間を動物病院において指導教員のもとに実際に疾患動物の診療に当たり,卒後は独立して診療業務や現場の仕事に対応できる実務教育を行うことによるものである.欧米とわが国における獣医学教育体制の著しく異なる点は,動物医学教育として,基礎獣医学教育と応用または臨床獣医学教育に大きな差があることである.欧米諸国の教育時間数はおおむね5,000〜6,000時間であるが,その内容は講義時間数が全体の1/3,演習・実習等の実務教育時間数が2/3である.わが国ではその反対で,実務教育の時間数や教育施設・設備あるいは教育スタッフが極端に貧弱なのである.このような教育体制では,6年制の獣医学教育を受け,獣医師の資格をもって実社会に出れば,獣医学教育に対する批判が起こることは当然であり,実務的に未熟な卒業生は直接その批判を受ける結果
となる.学生は動物に対して興味をもち,最小限獣医師の資格を取得して社会に頁献できることを信じ貴重な学納金を収めて勉学しているのである.わが国における獣医学の卒前教育が,欧米における獣医学教育と実務教育の点で著しく相違があることは,教育を受ける学生の立場で社会的または国際的な対応を考えれば,根本的に教育体制の転換を図らなければならないことは至極当然なことである.
しかしながら,担当科目と単位数にこだわり,教育体制の転換を図らなければ,教員の自己主張によって卒業単位 の182単位を消化するだけで,現状の教育体制は今後も変わることはないであろう.また,教員や教育体制を第三者的な立場から外部評価を受け,研究業績に偏ることなく多面
的に評価すべきである.特に実務的に活躍する新卒獣医師の約70%を輩出している私立大学においては,動物臨床医学の実務経験や社会活動あるいは卒後教育経験等も高く評価すべきである.さらに獣医科学の研究は大学院で行うこととし,獣医学部では教育のための研究は必要であるとしても,実務教育に主点を置いた知的職業人としての獣医師を養成しなければ,今後における獣医師の社会的地位
がきわめて不安定なものとなるであろう.
|