紹介
獣医師会と連携している行政予算を伴う
学校飼育動物対策事業
―平成12年度報告書―
日本小動物獣医師会・学校飼育動物対策委員会日本小動物獣医師会学校飼育動物対策委員会では,全国各地の皆様のご協力により,お寄せいただいた情報から,今年7月現在までの契約状況をまとめたので報告する.情報をお寄せいただいた各地の皆様に深く感謝するとともに今後,各地における契約の参考にしていただければ幸いである. |
|
| 日本小動物獣医師会では,地元自治体が学校動物の飼育支援事業を行っている実例を毎年報告しているが,昨年の報告から新たに14例が明らかになり,また,これから連携される予定の自治体も2例報告されているのであわせて報告する.また,報告された事業例の内容を分けて要約し,代表的な活動内容と予算についても報告する.これまでの例の内容について,本年度の変化,これまでの連携の内容の傾向,および将来の展望もあわせて記載した. われわれ委員会が,実質的に活動を始めた平成10年の4月には,これらの事業例は全国で18例程であったが,平成12年度6月には50例を数えている.文部省も平成11年度に「学校と地域獣医師との連携」を学習指導要領の解説書に明記し,また,本会学校飼育動物対策副委員長と日本獣医師会から2人の獣医師が関わって作られた教師向け飼育指導マニュアル「望ましい飼育指導のありかた」が,本年度,全国の小学校に配布されるが,この本にも獣医師との連携が記載されている.今後は全国で急激に連携事業が増えると予想されるが,この子供の身近に動物を確保するための連携が永く安定して行われるためには,獣医師個人に負担が掛かり過ぎないように注意する必要がある.現行の学校への嘱託医師制度,嘱託薬剤師制度を参考に,常識的な契約をするべきであろう. なお,学校の飼育を支援する獣医師会の活動に際し,以下の3点が特に重要と考えられる. 学校獣医師制度(学校への飼育支援体制) *学校の相談に対応する. 地元の動物病院を指定して,いつでも学校の相談にのる. *飼育指導(教師向け),年に1〜2回の定期学校訪問指導,または講習会. 動物との交流,飼育,衛生環境,管理など,獣医師の知識と技術を提供する. 定期学校訪問指導と,教師を集めての講習会による指導がある. 効果が大きいので,可能な限り現場で指導する. *教育委員会と校長会と3者で協議会を設ける. この事業についてお互いに成果 と問題点を確認する. その他,子供への語り掛けはことに重要であるが,教師と獣医師がこの活動に慣れ,学校との信頼ができてからでも遅くはない.これをふれあい教室として授業で行うか,普段の飼育指導の一環として行うかは,学校の要望による. | |
1)自治体行政の予算を伴う獣医師会との連携例の活動別の要約(現在までの連携事業例を表1に示す) 表1のうち,多いのは東京都(14市区),岐阜県(9市町),神奈川県(8市町)である.
多くの活動例では十分な予算がないため,現在のところ活動は獣医師の個人的な情熱に支えられている場合が多い.またこの表1のほかに,まったくの無償で地域の保健所と一緒にまたは個人で飼育支援活動している獣医師は全国にみられる.
しかし子供達から動物を取り上げないように,獣医師会と自治体との協力体制を安定して維持するためには,どちらにとっても無理のない契約が結ばれる必要がある. 2)自治体予算を伴う獣医師会との契約数の推移(平成12年7月まで) 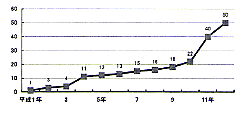 |
|
| 平成元年までに,神奈川県相模原市が学校飼育動物の治療費について地元獣医師会と協定を結んだ.平成3年には「飼育指導と治療の委託契約」を,東京都保谷市が獣医師会(北多摩支部)と契約をした.その後,北多摩支部で盛んに獣医師に対して情報を流し,少しずつ契約数は増加した.平成9年度,日小獣の学校飼育動物対策委員会に現在の委員が揃ったが,文部省を訪問するなど本格的に活動し始めたのは平成10年4月からである.また,この年,群馬県が「学校に獣医さんを校医として置きます」との新聞広告を全国的に流したこともあり,平成11年度には,全国での契約数が飛躍的に伸びた.また,平成11年春には,日本獣医師会も「積極的に獣医師は学校に関わる」との方針を打ち出し,平成11年5月には,文部省も新学習指導要領の解説書生活科編に「飼育の際には,獣医師との連携が必要」と明記した.その結果
,現在,獣医師会と連携している自治体は50例になっている. この50例のうち,5例は政令指定都市であり6例は群馬県,東京都,福岡県,北海道,茨城県,大分県の県単位 の契約になっている.これらの市町村の数を考慮すれば,例えば群馬県は70市町村であるので,現在獣医師会が学校に関与している自治体は,130を超えている. 3)全国の50例のうち,代表的な教育委員会と地元獣医師会との連携実例の今年度の契約内容 現行の教育委員会など行政と獣医師会との連携事業のうち,代表的な4例を表2に記載する. 保谷市は8年間の無料診療の後,教育委員会が治療費に見合うだけの予算をつけ,飼育指導と治療を行っている.獣医師会員は一人年間約10万円の顧問料で治療まですべて賄うが,無料診療の時代に比べれば負担感なく協力できる.獣医師会員2人1組で近くの小学校に,年に1,2回訪問して教師,児童と交流する.1組の獣医師は3,4校を訪問する.また,最寄の学校の担当獣医師として,相談を受け治療など対応をする.連携事業を始めてから今年で9年目だが,この3,4年市内の飼育動物はゆったり暮らし,教師も動物の見方を児童に楽しみながら伝えることができるようになっている. 渋谷区の例は,年に1回の定期訪問のほかに,学校の希望に従い年に4回も学校訪問をする獣医師もあり,学校側の動物への関心は高まり,以前は治療されずにいた軽度の怪我でも病院に相談するようになっており,治療件数は増加している. 教育委員会はこの連携事業を大事にしており,獣医師会が特に予算の増額を要求していないのに今年度,実績を再評価し予算を是正してくれた. 蕨市の例は学校の嘱託獣医師方式で嘱託医師制度と同じである.獣医師会を通 じて,市は各会員と学校指定獣医師の委嘱契約を結ぶことになる.この制度は昨年議会を通 り,平成12年度,獣医師会員が指定申請をして任じられた.委嘱獣医師は,学校の相談相手になることと年に1回以上学校を訪問して,教師や児童,または父母と交流し児童の心の教育を助ける.謝礼は1校5万円であり,会員は1人で2,3校を受け持つことになる.委嘱医師制度と同様,訪問旅費と治療費は別 になるが,治療費は今年度も実績調査のため無料診療を行う. 蕨市の例は行政と獣医師との連携法として無理がなく,全国にこの制度が広まることが望まれる. 群馬県の例は,獣医師が教師とともに動物とのふれあいを主題に授業を担当し,直接動物の知識やぬ くもりを児童に伝えている.県行政は,事業の成果を評価し,初年度平成10年に500万円で始まった予算が翌平成11年度は1,000万円に増加し,平成12年度は1,300万円を計上した.県獣医師会はこれに予算500万円を加えて,合計1,800万円の事業費で行っている. なお,群馬県獣医師会の担当委員長は,群馬大学の教育学部(教職専門課程,生活科)で学生に「動物とのふれあい」を教えており,根底から動物と人の関係を是正できるように教師を育てる活動をしている. 4)昨年4月以降に報告された平成12年6月までの新しい契約(表3) その他東京の清瀬市,千葉の柏市で新しく始まる予定.これらの地区では,これまで毎年獣医師会からの無料診療などの実績報告をしており,行政は獣医師会の学校への協力実績をよく把握していた. なお,以前から行われていたが,報告されていなかった活動例が新たに判明したので表4に示す. 各地で獣医師会が,子供達を思って活動している.新しい契約だからといって,個人獣医師の負担が少ないというわけではない.今後の継続性を考えるなら,個人獣医師が心配なく学校に関われる連携が望まれる. 5)昨年までの活動例で,今年度内容に変更のあった事例 <東京都> *渋谷区では,獣医師会は契約内で指導,治療,訪問活動を行っているが,通 常料金の実績集計を毎年区に報告している.獣医師会は予算の増額を求めてはいないが,区は動物を通 じて獣医師の児童への働きの実績と効果を認め,獣医師会に約30%の増額を伝えてきた.29施設で130万円になる. *世田谷区での獣医師会と区の取り決めでは,いままで高額治療に対し行政の予算に20万円の上限が設けられていた.しかし今年度から,事前に教育委員会の了解を得て治療すれば,全額支払われることになった. *東久留米市は平成4年以来市獣医師会と協力してきたが,平成12年度にはじめて「市立小学校・幼稚園における飼育動物の診療及び飼育指導委託契約」を取り交わした. *練馬区では,区教育委員会と獣医師会の関係が改善され,区が独自に行ってきた教師向け講習会をこれからは獣医師会に講師の派遣を依頼することになった. <神奈川県> *相模原市では,昭和53年度から制度化されていたことが判明.平成12年度,対象校は60校,飼育指導と治療(不妊手術を含む)を行っており,治療費が治療後に支払われる. *秦野市では以前から連携が行われていたが,平成9年度になって正式に「学校飼育動物診療及び飼育相談委託事業」として契約が結ばれた.また,対象施設数は27になった. *今年度,神奈川県獣医師会は県教育委員会と連携して県内全校に飼育の実態調査を行う予定. <埼玉県> *川越市では,昨年度の衛生調査の結果今年度から,ニワトリへのワクチン接種も事業内容に加えることになった(ワクチンは市が用意する). <新潟県> *新潟市での協力体系は円滑にいっており,毎年事業予算は増額されている.63施設に対する治療費が約15%増額され86.9万円になった. 6)連携事業の傾向についての考察 1.早い時期に連携したものでは,おもに治療や去勢だけをカバーしている例がほとんどである.それまでの無料診療の実績を行政に報告していなかったことが多く,行政は十分に予算を確保できず,今でもほとんどの獣医師が多くを負担している.しかし,獣医師会がきちんと実績を報告しているところでは,徐々に予算が是正されてきている. 2.診療実績を通常料金で報告してきたところでは,5年ほどで行政が治療費をまかなう契約を申し出てきている.しかし,政令指定都市などは横並び行政ともいわれているが,学校数が多いこともあって,一律95万円から100万円になっている. 3.最近は,獣医師による学校訪問指導や子どもへの働きかけが求められている.獣医師が学校を訪問する際,旅費として2万円手当てされるようになってきている. 4.訪問指導や治療などの実績をきちんと報告している例では,年々予算が是正されてきている.特に訪問指導の効果 が喜ばれている. 5.契約に診療費を含めないところも増えてきている.つまり,指導についての事業契約を行い,診療費は別 に考えるということである.診療費については,年間の額が流動的でありきちんと予算化することは難しいので,現在予算化に向け実績を収集するために無料診療をしているところが多い. 7)学校獣医師制度の将来への展望 学校飼育動物は,子供達が愛情を持って,小さな動物の幸せのために仲間と工夫しながら動物を世話してともに暮らすために存在する.つまり,子供達にやり甲斐のある楽しい作業を通 じて,愛情,癒し,科学的刺激など数え切れない効果を現す存在であり,体験が少なくなってきている現在の子どもたちに必要だと文部省も考えているのである.そのため,学校獣医師制は,単に動物の病気を治す存在としてではなく,子供達に動物の気持ちを理解させより深い交流を助けまた,衛生上でも安全な体験学習を得させることが期待されている.それには現在のように事業を委託される業者との扱いではなく,蕨市の例のように,医師,歯科医師,薬剤師と同じように身分を委嘱されるのが望ましいし獣医師に無理が掛からないだろう. しかし,獣医師も子供達に直接話しかけるのには馴れていないため,初年度から完全に遂行することを不安視する獣医師が多くみられ,獣医師会内部の意見がまとまらないことが多い.しかし実は,開業獣医師は患畜の飼い主と話し合う経験が豊富なため,子どもに話し掛けることに直ぐに馴れることができる.実際に現在,飼育指導やふれあい教室など,子供達に直接語り掛けている活動例では,どこでも子どもと教師に感動を与えることができている. なお,予算的には,現行の委嘱医師は1校20万円位,薬剤師は15万円位である.このことから,最初に教育委員会と連携のできた保谷市の例では(便宜上治療費を含めて),獣医師1人10万円になっている.しかし,その後各地で結ばれた例は,行政が動物飼育の意義を低く考えているためか,獣医師の優しさをそのまま受けとめたためか,1校5,000円で全てをまかなう契約まで結ばれているところもある.しかし活動を始める年度には,治療や去勢手術代だけで,1校5万円位 は最低必要であることを覚えておいていただきたい. 学校飼育動物事業の将来については,獣医師の社会的認知のもと獣医師や関与するすべての関係者が,あまり負担感を感じないような制度が確立でき,次代を担う子供達のためにこの支援制度が安定して続くように望みたい. |