「獣医師の職場」(その96) |
| 【名 称】 | |
| 国際家畜研究所 (International Livestock Research Institute;ILRI;イルリ) |
|
| 【所在地】 | |
| ILRI, P.O. Box30709, Nairobi, Kenya TEL +254h2h630743 FAX +254h2h631499 E-mail:ILRI-Kenya@cgiar.org または y.honda@cgiar.org ホームページ:http://www.cgiar.org/ilri |
|
| 【組 織】 | |
| イルリ(ILRI)は,国際農業研究協議グループ(CGIAR)が統括する世界各地に16ある農業関連の国際研究所の一つである. | |
| 【沿 革】 | |
| CGIARは,開発途上国における食糧安全保障の達成と貧困の一掃を目的として,世界銀行,国連食料農業機関(FAO),国連開発計画(UNDP),そして国連環境計画(UNEP)がスポンサーとなって1971年に創設された.イルリは,継続可能な畜産業を実現するための研究を行うことにより,途上国の飢餓,貧困そして環境破壊を減らすことを目的として,それまでCGIARの二つの研究所であったケニアの国際獣疫研究所(ILRAD,イルラッド)とエチオピアのアフリカ家畜研究センター(ILCA,イルカ)が統合されたもので,1995年に活動を開始した. | |
| 【業 務】 | |
| 本部があるケニアのナイロビ・キャンパスでは,おもに反芻獣の寄生虫病や疫学に関する研究を,エチオピアのアジスアベバ・キャンパスでは,おもに畜産や飼料に関する研究を行っている.両キャンパスあわせて,現在35カ国から来ている約100名の研究者と約800名のローカルスタッフが勤務しており,牛に関する研究所としては世界でも有数の非営利の研究所である. 日本は,40あまりの資金供与国(地域・団体)のうち,毎年ベストテンに入る額を出資しているが,日本人は藤田陽衛氏(畜産技術協会常務理事)が理事に就任されているのと,筆者が職員として勤務している他に,国際農林水産業研究センター(JIRCAS,ジルカス)から長期および短期の在外研究員が派遣されているだけである.「日本はお金は出すが人は出さない」という批判は,残念ながらここでも当たっている. アフリカと聞くと「暑い」と思われる方が多いと思うが,ここナイロビ・キャンパスは,標高約1,700mの高地にあるため,ほぼ赤道直下に位 置するにもかかわらず年中日本の春か秋のような気候で,湿度もなく本当に過ごしやすいところなのである.そして,さらにすばらしいことは,牛を使って実験ができることであろう. 1996年11月の「世界食糧サミット」において日本を含む各国政府は,2015年までに現在800万人に達すると推定されている栄養不足人口の半減等を目指した「世界食糧安全保障のためのローマ宣言」と,その具体的な方策を示した「世界食糧サミット行動計画」を採択し,これらの目標を達成するために,各国および国際機関等が協調して取り組むことを宣言した.世界の家畜の3分の2は途上国で飼われているが,家畜生産効率は先進国のわずか4分の1であり,90%以上の家畜が小規模農家の所有となっている.生産性の向上を阻むおもな障害は,伝染性疾患,飼料の供給体制,不十分な市場との結びつき,そして反応の鈍い政策環境等である. ナイロビ・キャンパスでは,具体的にはここアフリカでもっとも問題となっている2つの牛の寄生虫病である「トリパノソーマ症」と「東海岸熱(ECF)」に対するワクチンの開発とトリパノソーマ症に抵抗性の遺伝子の研究をおもに行っている.イルリの家畜研究プログラムは,アフリカだけでなく世界各地にも広がっている.たとえば,近年東南アジア諸国は,めざましい経済成長を遂げているが,食糧の増産はこの地域でも依然困難な状況にあり,人口増加,人口の都市集中,環境破壊,そして畜産品への要求が増大している.これまでこの地域での農業研究は,おもに作物生産に関するものであったが,現在は何百万人もの貧しい農家や,田舎や都会の消費者の利益となる,作物― 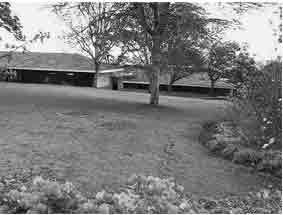 家畜混合農業システムの生産性を向上させるための研究が必要とされている. 家畜混合農業システムの生産性を向上させるための研究が必要とされている.イルリは,現在ナイロビとアジスアベバの二つのメインキャンパスの他に,ナイジェリア,インド,フィリピン,コロンビア,そしてペルーに研究ステーションを置いて研究成果 の提供や情報の収集を行っている. |
|